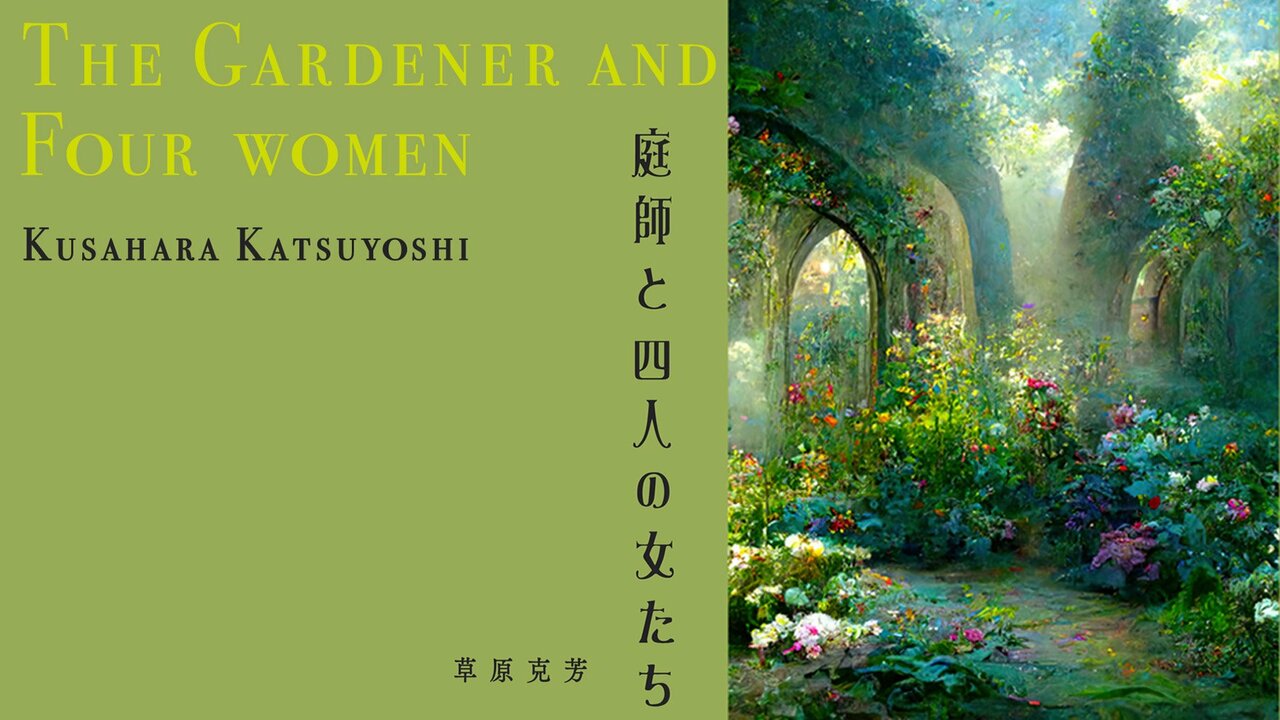庭師と四人の女たち
1
一人暮らしの老婆は、テレビの前に座っていても、ふと訳のわからぬ焦燥に駆られ、不安と孤独でいたたまれなくなって、ついつい「パンタレイ」に足が向いてしまう。ここでは彼女が愚痴のひとつでも放てば、すぐさま、ああでもないこうでもないと、反応が返ってくるのであった。
庭木を掻き分け、裏庭に面している扉から店に入り、いつもカウンター前の指定席に座り込んで、同じように昆布茶を頼む。ときには、うつらうつらとそのまま居眠りを始めるのであった。
「それはそうと、最近、聞こえるの? あっちの方」
睦子は意味ありげに目配せした。
「聞こえるなんてもんじゃないよ。若いってああいうもんかねえ。あたしらだって昔は住宅事情がひどいんで、新婚時代はずいぶん片身の狭い思いをしたもんだけど、いまはぜんぜん、傍若無人だものねえ。普段は可愛い顔してんのに、もう夜中になると、猫とおんなじ。庭中響いて、どうしようもないよ」
「また、あの娘のアパートに来る彼氏が、いつもながら柄が悪いのよねえ」
「アンチャン……だろ」
「茶髪でね。胸開けて、こんな派手な金の鎖のブローチつけて。ま、話してみると案外、素直で、決して悪い子じゃないんだけどさ」
「睦子さん、あのね、おばはんは、埒外なんだよ。上手に、おとなしそうな顔して見せるんだ。若い男ってのは、狩猟犬みたいなもんだからね。同年代の娘には、別な動物なんだから。サーファーって言うんだってね、あの手の人種は。髪茶色く染めて、三角形の筋肉質の体して。
あたしもねえ、これでも昔は、ちょっと、あったんだ。娘時代、湘南の浜辺にたむろしてるような男たちとさ。何しろ、鎌倉に住んでたからね。夏の朝、二階から眺めた海の光景が忘れられないよ。銀色の波、コバルト色の水平線。羽田の近くにあったうちの父親の部品工場が、いちばん調子良かった時代さ」
老婆は悲しそうに目を細めた。