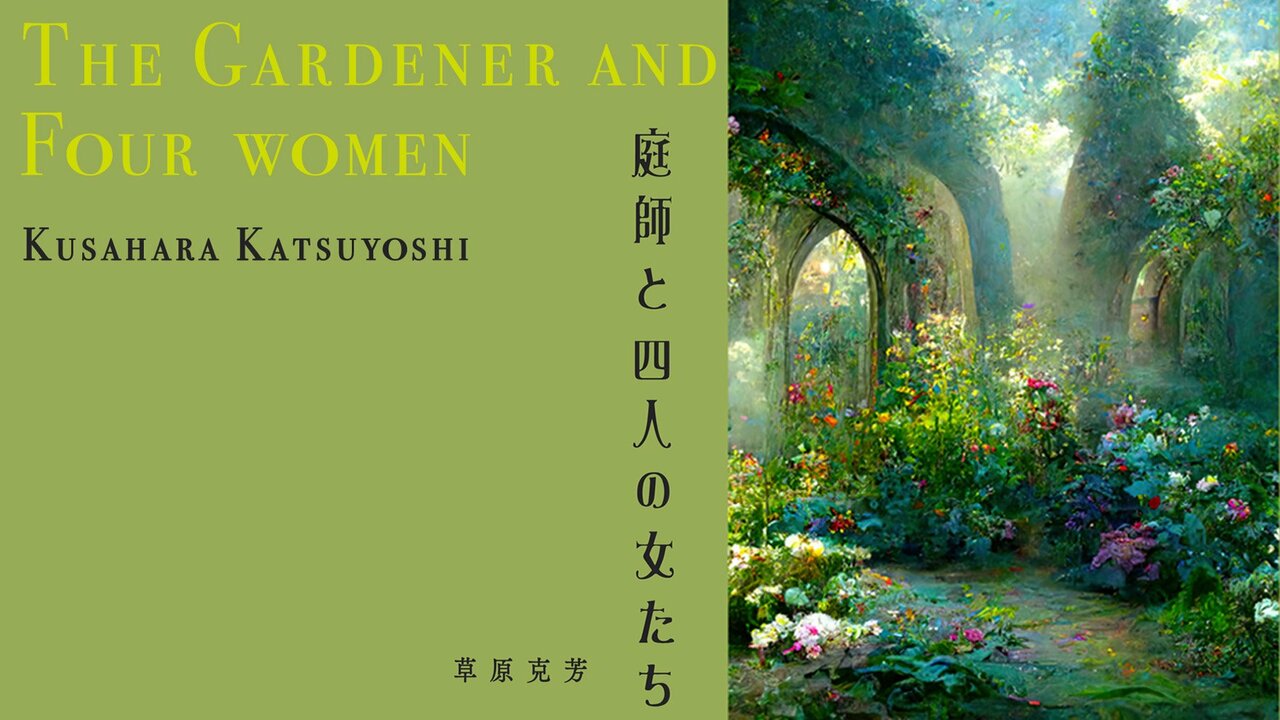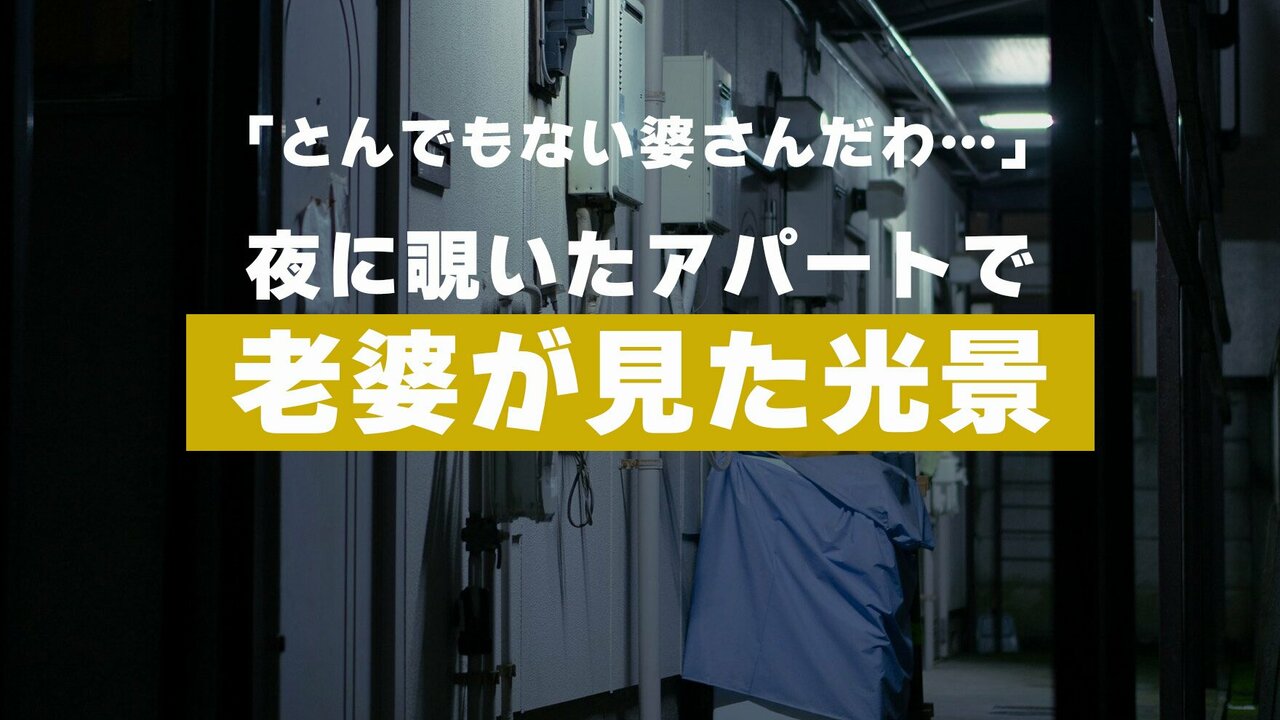庭師と四人の女たち
1
キッチンの端に下げられたグラス類を、陽光が通して影を作る。その薄い半透明の模様が虹色を帯びて美しい。ときおり数軒先から、甘えたような仔犬の鳴き声が聞こえる。
採光の良い南側のガラス窓から、金色の木洩れ陽が床に揺れていた。
大きく枝の影が動いたのは、よくやってくる蒼紫色の野鳥が、いま二羽ほど飛び立ったからだろう。
さっきから話題になっている娘は、中庭のジャングルを挟んでこの喫茶店の東側にあるアパート「樫の木コーポ」の一階に住んでいる葉山彩香という二十代の女だった。
もっともこのうさん臭い名前は、彼女が所属しているプロダクションの登録名で、本名は鈴木郁子という何の変哲もない実直そうな名前なのであった。
豹柄やアニマルプリントの類いが大好きで、とりわけ夏ともなると、露出度が高かった。バッグや時計などの持ち物はブランド品であったが、これは要するに岩手の田舎から出てきて、流行の先端や派手な格好に魅了され、さらにはそれが強迫観念として、染み付いてしまった結果なのであった。
「あたしゃねえ。こないだの夜、あんまり大きな声が聞こえるんで、むかむかしてきて、覗いてやったよ」
「あらら、何てことを」
「抜き足、差し足。あたしのとこが一階で、あの娘が一階で、中庭の木陰を挟んだ向かい合わせだろう。窓辺の影とかも見えるんだよ。……思わず、庭先に出てってさ。と、やってる、やってる。暑いんで、台所の窓少し開けていたんで、そおっと首をのばしたら、男がこう抱えてだよ」
「袋田さん、それ、犯罪だわよ」
睦子はカウンターから身を乗り出して、声をひそめた。「あの娘が、壁のとこで、素っ裸になって、首をだねえ、こうそらして。男の方が、色浅黒い肩甲骨を……」
老婆は重たい体を揺らしながら中腰になり、身振り手振りを入れた滑稽な実演が始まった。
「あらやだ。だけど、そんなとこ見つかったら、警察に通報されるわよ」
「なあに。あんたが通報しなけりゃ、いいだけの話じゃないか。ジジイだったらデバガメで捕まるかも知れないけど、ババアの覗きなんて、誰も本気にしやしないさ。警察なんて、みんな頭カタイんだから。あたしなんざ、夜中退屈すると、よく近所を覗き見して歩いているよ」
「……とんでもない婆さんだわ」
「へッ。どうせ、変態ババアだよ」
マス江はふてくされたように、ミックスナッツを一粒摘んで、乱暴に口に放り込んだ。
睦子は、あらためて袋田マス江のどこか動物的なふてぶてしい顔を眺めた。
こんな老婆が近所にいて、のそのそとペンギン歩きされていたのでは、暇つぶしに何を覗かれているかわかったものではない。そういえばゴミの日の早朝に、この女がよく集積所を覗いているのを見かけるのは、偶然だろうか。