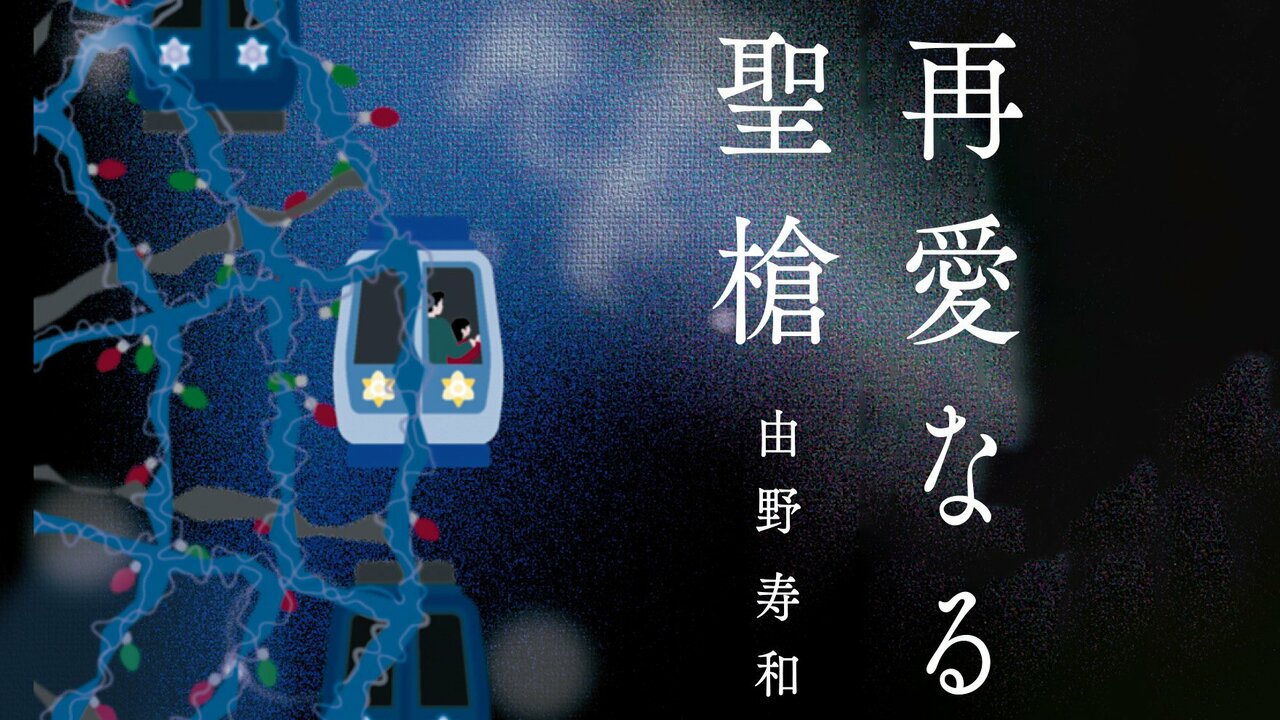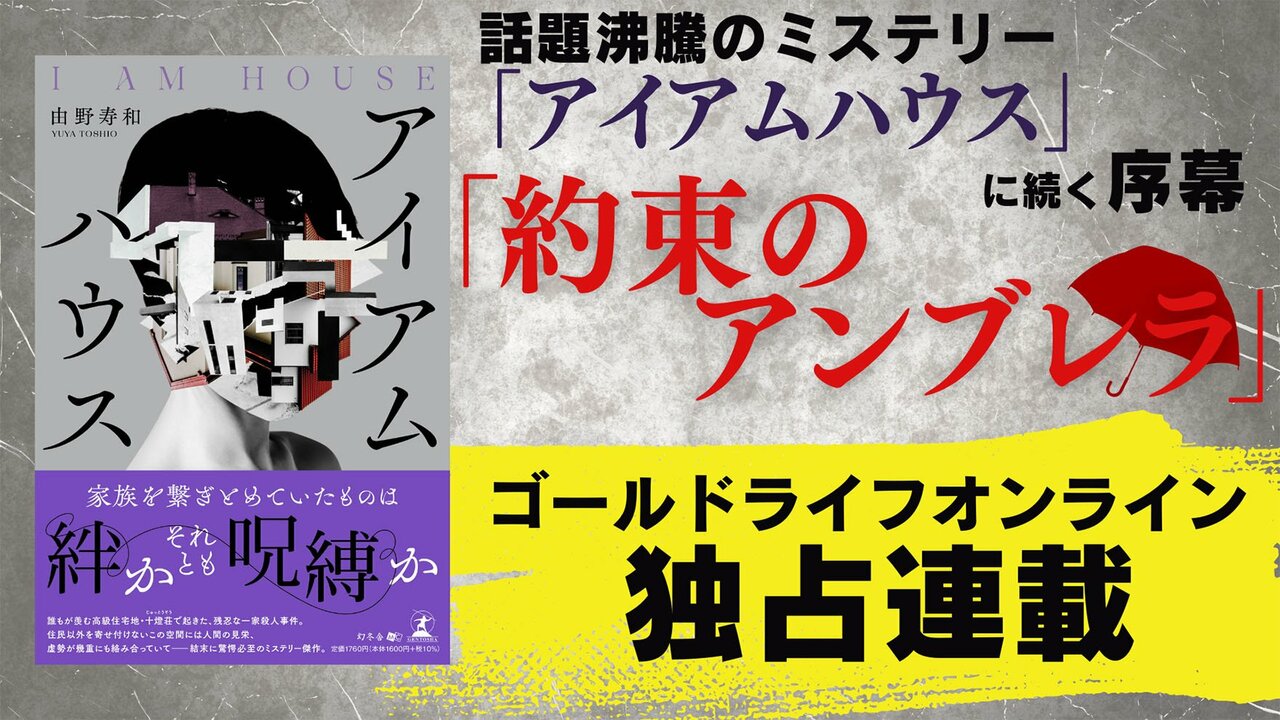一 午前…… 十時三十分 クリスマスイヴ
走っていくと、言われた通りの場所に黄色いコートを着た娘の姿が見つかった。息を荒げながら叫ぶ。
「凛、どこにいたんだ!」
はあはあと呼吸を整えながら、仲山は凛の頬に触れた。
「全く、お父さんは心臓が止まるかと思ったぞ。ダメじゃないか、勝手に離れたら」
「ごめんなさい、だって」
凛はそう何かを言いかける。
「まあまあお父さん、娘さんは風船をもらったようで」と、そこに迷子担当のスタッフが口を挟んだ。
確かに、凛は黄色い風船を持っていた。ふわふわと浮いていて、空に飛んでいかないように凛は紐を指に巻き付けている。
「そうでしたか、ありがとうございました。どうもご迷惑おかけしました。ほら、凛もちゃんとお礼言うんだよ」
二人は深々と頭を下げ、手を繋いで歩き出した。凛は歩きながらも拗ねているようだった。呼吸を整えながら仲山が口を開く。
「なあいいか、凛。別にお父さんは怒ってないんだ。ただな、心配するだろう? ここは広いし大勢の人がいる。いい人ばっかりじゃない。本当に危ないんだぞ、お母さんにも言われてるだろ? なんで勝手に離れたんだ」
凛は両頬に息を溜めてむすっとしながら、風船の紐を引っ張った。つられて黄色い楕円が空中で揺れる。
「どうした、凛?」
仲山は足を止めてしゃがみ、凛の顔をじっと見た。凛は手を握りしめてから大きな声を発する。
「だって、ずっと、計画、計画ってうるさいんだもん! さっき会ってからその紙と腕の時計ばっかり見てる。凛のこと見てないし、凛の話聞いてない」
その瞬間、思わず仲山は息を飲んだ。全く同じことをいつも惟子に言われていたのを思い出したからだ。こんな小さい娘にさえそう思わせたのか。それを思うと胸が苦しくなった。
「そうか、そうだな……。お父さんが悪かった。凛の言う通りだ。寂しい思いをさせたんだな」
仲山は腕時計を外し、予定を書いた紙と一緒にポケットに詰め込む。
「ほら、見ろ。これでもうなしだ」