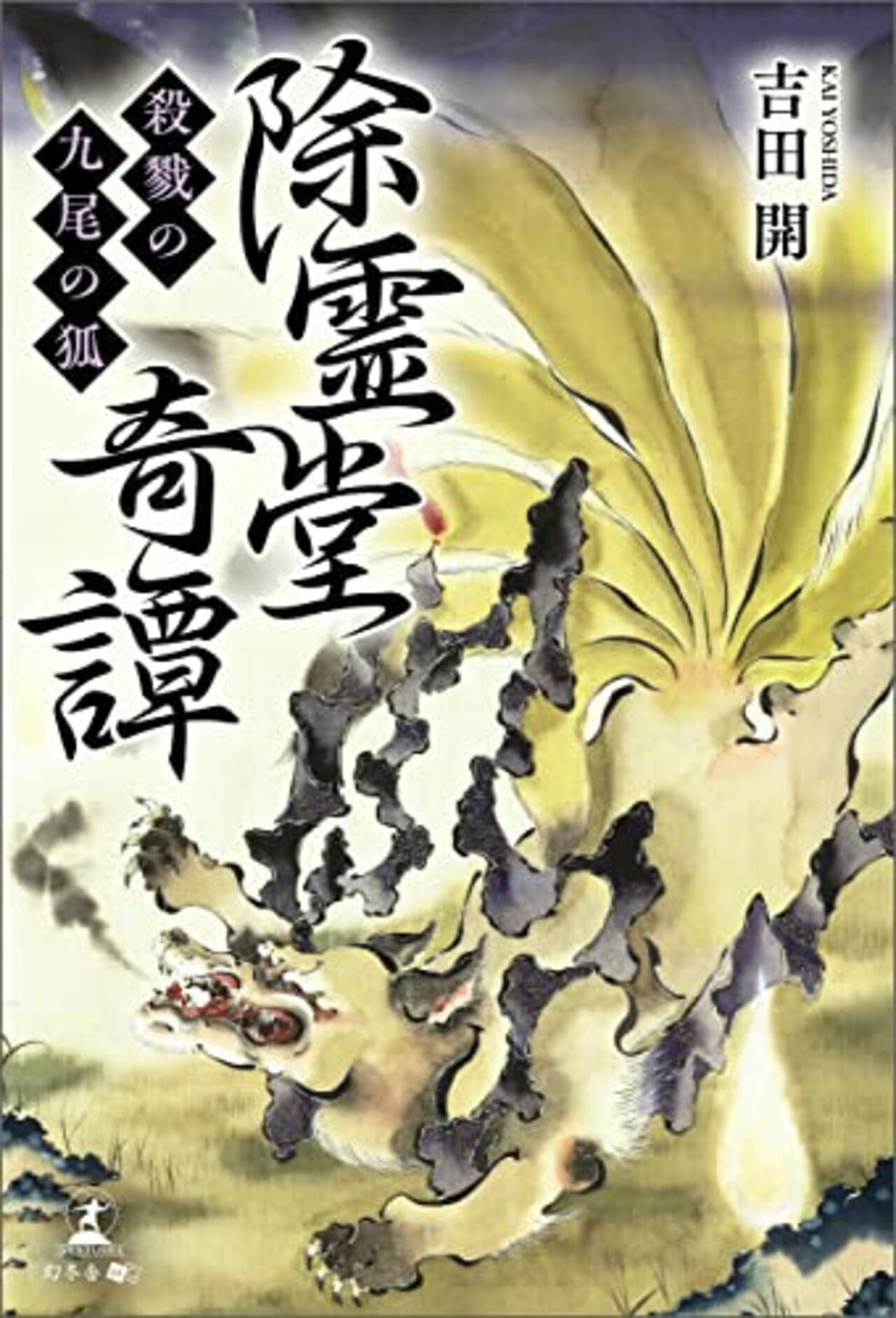序章 三人寄れば地獄行き
一郎は自分がうぬぼれていたと、強く思った。「自分にもっと力があったなら自分の目の前で、四人もの人が殺されることはなかったはずだ」と思った。
一郎は幼い頃から霊媒体質だった。小学生高学年になってから、その忌まわしい体質は強くなり、動物霊などが突然頭や背中に乗ったり、金縛りにあったりするようになった。霊は見えないし自分に何が起こっているのかなど、子供にわかるはずはなかった。
しかし霊が見えないかわりに感覚は研ぎ澄まされ、あちこちに不浄な霊がいるのがわかる。それは自分では祓えないだけに、その恐怖といったらなかったが、周囲には話すことはなかった。祖母だけが理解者だったので、ある日とうとうすべてを打ち明けた。
話を聞いて、自分もそうだったんだよと言った祖母は、どういうつてを頼ったわからある神社の宮司である高倉先生に見てもらえることになった。
そこは函館市から二百キロメートルほど北にある神社だった。
さっそくお願いに上がと、高倉先生は除霊してくれただけでなく、弘法大師との結縁を作ってくださり、それからは霊に苦しめられることはなくなった。それから一郎は自分の霊媒体質のことは、ほとんど気に留めない生活を送ることができた。
高校二年生の春頃から不思議な夢を見るようになった。毎晩夜空を飛ぶ夢である。ところが意識は覚醒していて、現実に空を飛んでいるようなのである。空中から見る家並も非常に現実的で、自分に羽根が生えて飛んでいるようなのだ。そのうち、現実のような夢を見るようになった。
ある時一郎は平原を歩いていた。やがて空から地面まで、真っ白い霧に覆われた壁があらわれた。壁は石でできていてどこまでも続いているので、そこから先へはどうやっても行けないのだ。
不思議だった。自分では完全に目覚めているのに、夢の中にいるはずがないのに、実際に自分がいるのは夢の世界だった。
またある時、一郎は明るい部屋にいた。部屋の中央に腕が一本だけ入るような黒いトンネルがあり、腕を入れるとなぜか、体が縮んで向こうの世界に吸い込まれるような確信がある。そこはすばらしい世界で、どうしても行きたいので手を入れる。
ところがトンネルの中に動物のようなものがいて、それが鋭い爪で引っ搔くので、どうしてもそれ以上行けない。引っ搔かれた右手は、夢なのに現実にとても痛むのだ。