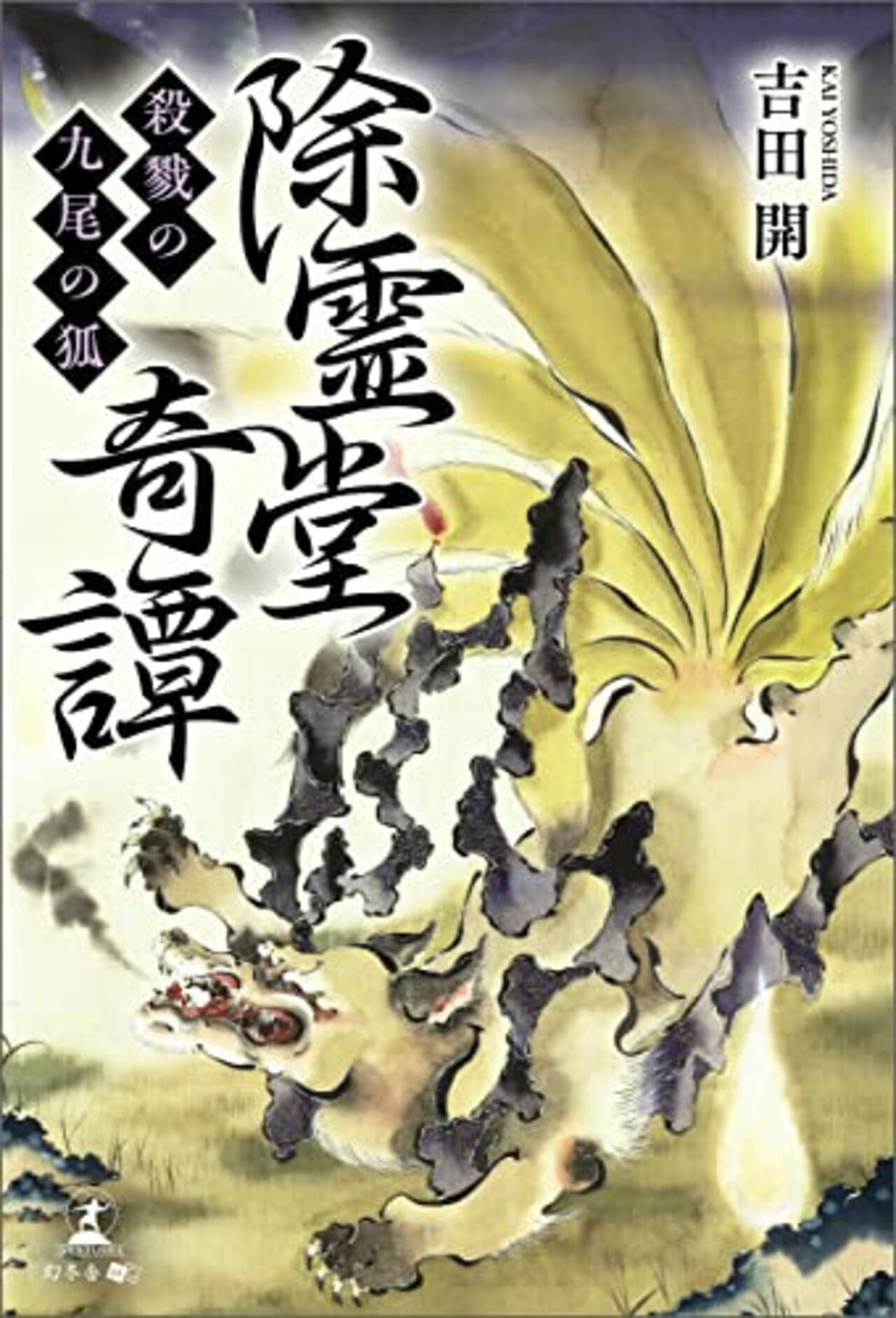序章 三人寄れば地獄行き
私は「千穂!」「千穂!」と大声を出したはずだが、全く音になっていなかった。まるで声帯がなくなったようだった。私は千穂の手を強く握るのが精一杯だった。
千穂も声は出さないが、大変な恐怖を感じているのに違いなかった。千穂も私の顔がぼやけているのだろうか。
前を向くと、前方左手に五十代と思われる和服を着た女が、ゴザの上に座っている。右手には六十代前半くらいの男が、太鼓の前に座り撥を持っている。
太鼓の奥にはカーテンがあり、今は閉まっている。正面には立派な表装の掛け軸が下がっている。掛け軸には絵も墨書きの文章もなく、中心にただ、『ま』とのみ書いてある。
前の六人の客は誰も声を出せず、おとなしく座っている。そのとき、一番前の席右側の客が立ち上がり掛け軸の前に座った。すると女が三味線を弾き始めた。男もどどん・どんと、太鼓をたたき始める。そして女がかすれた声で、妙な節を付けて話し出した。
「たかあまはらにしずまります『ま』のおおかみ あらわれたまいしいまは ともにしもべとなりてえいえんにおつかえするため まずはじごくでしゅぎょうをはじめせしめんと おおせたてまつるなりー」
それから唄い出した。
「三人ー寄れば 地獄行きー」
「三人ー寄れば 地獄行きー」
「三人ー寄れば 地獄行きー」
すると掛け軸の前に座った客が、突然中腰になり立ち上がろうとしたが、そのままばったりと後ろ向きに倒れてしまった。私はなぜかわからないが、その客の心臓が止まっていることを確信していた。その場にいた他の客も、やはり私と同じように思ったに違いない気がした。
私は何とか娘の手を取って逃げ出そうとしたが、やはり体が動かない。千穂の顔は見えるようになっていたが、その顔は恐怖で引きつっている。やはり体は動かないようだ。
先ほどの客が静かに言う。
「もう逃げられないんだよ」
小屋の空気はますます重くなり、頭の奥がしびれてきた。思考能力もなくなっていくようだ。