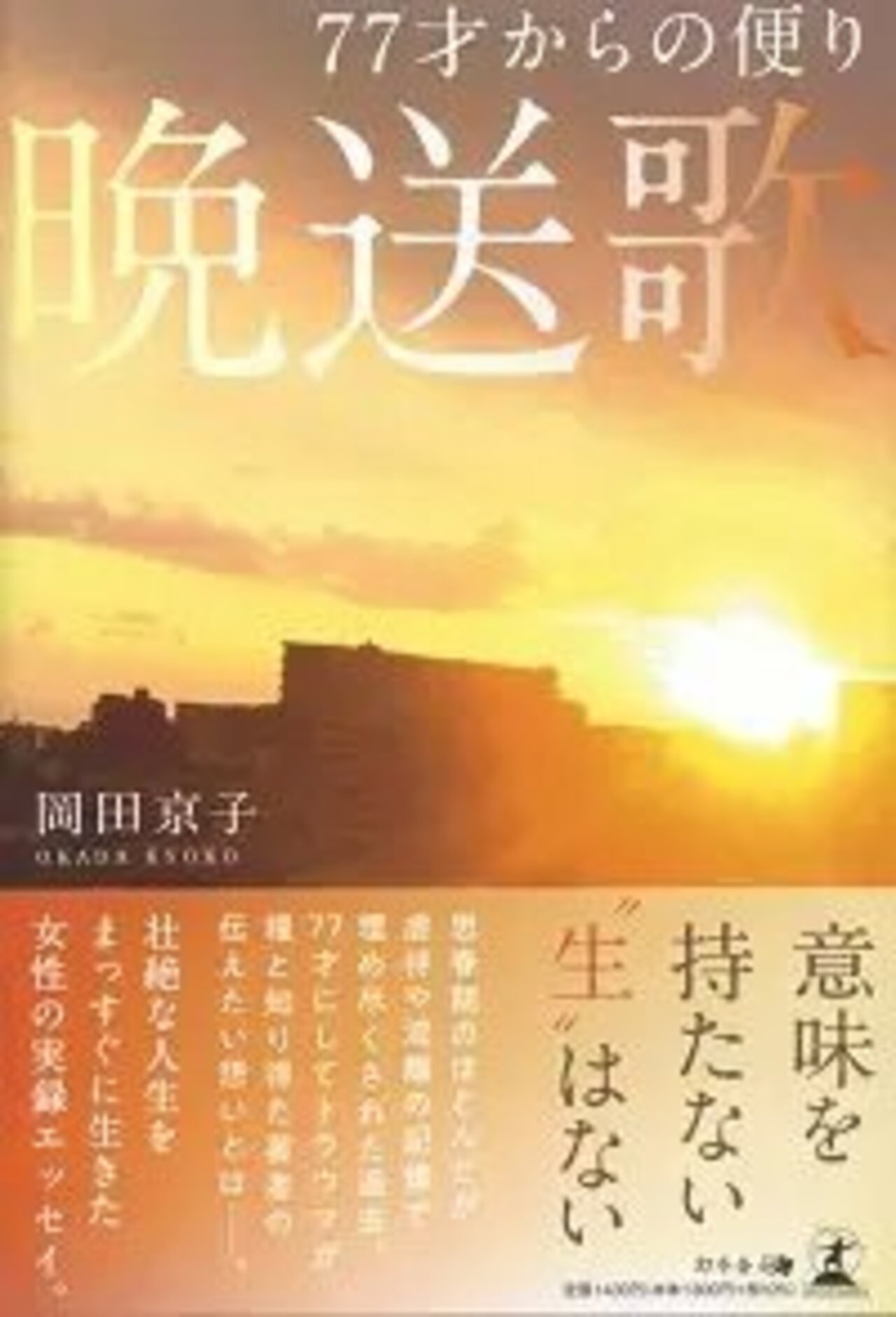【前回の記事を読む】「産みの母と育ての母とどっちがええねん」5歳の少女に突き付けられた言葉の真意
第二章 夕日と……。夢人と……。
天気の良い日の朝礼は暖かくとも体はユーラユーラと夢の中。保健室では常連、それでも給食が食べれる間は体はもっていた。
或る時期、給食代が払えないらしく、その時間は校庭の太い木の幹の陰で誰にも見つからないように石を蹴ったりしながら時を潰していた。
“美夜子、こんなとこおったんか”と先生の声、“こっち来い来い”と付いて行った先は用務員室、先生はアルミの弁当箱を取り出し蓋の上にご飯、何種類かのおかずを取り分け“さあ一緒に食べよう”と割り箸をさいて私に持たせる。
飢えている私は恥ずかしさはあっても無我夢中でむしゃぶりついたに違いない。
或る日、いつもの様に、用務員室に行くと先生が何か容器で米を研いでいる、“先生、何してるん”と聞くと“お前に炊きたてのメシ食わしてやるからな”と火の上に置いた。兵隊さんが持っている様な形をした変わった器だった。
先生は火をおこしたり息を吹きかけたり忙し気だった。“さあ、炊けたぞ”と私より自分が嬉しそうにその器の蓋に湯気でホカホカした真っ白なご飯を入れてくれる。美味しくて、美味しくて。私の顔は輝いていたはずだ。先生の顔も笑いで溢れていた。
或る日、いつも遅くとも帰って来る養母が一晩帰らなかった。暗闇の中、心細くて、灯りをつけると夏のせいで割れた窓から虫が飛び込んでくる。灯りをつけたまま冬布団から目だけを出すようにして夜を明かした。
明け方、彼女は帰ってきた。疲れは顔からも体からもあふれていた。幼い私にトツトツ話しだしたこと。“昨日警察に捕まって一晩留置場にいれられた”こと、“よりによって一番売上が多い日やった”と。彼女は競馬か競輪の切符をもぐりで駅の階段下で売っていたのだ、このことは前に聞いていた、警察に見つかったらつかまると。本当に嬉しくて私に初めてのおみやげも買ったと。朝、警察官が云ったらしい“売り上げをみんな置いといたら帰したる”と。
彼女の心のさすらいが見える気がした。目の前のかつてない売り上げが露と消える口惜しさ、又、どうして食べていけるのかの悲しさ、それ以上に一人待つ私への憐憫、答は出ている。残されたもの、一人待つ私への初めてのおみやげ、それだけはさすがに警察官も取り上げず“持って帰ってやれ”と。帰ってから彼女の袋から出されたもの、黄色い縦長の箱「森永ミルクキャラメル」。
70才を超えた今も箱を見ると切ない。6才の私に喜びはなかった。彼女の切なさが箱の中に詰まっていると思えた。それでもやっぱりカナヅチを取り出して来てキャラメルを割りだした、20個の四角いキャラメルは倍以上の数になった。