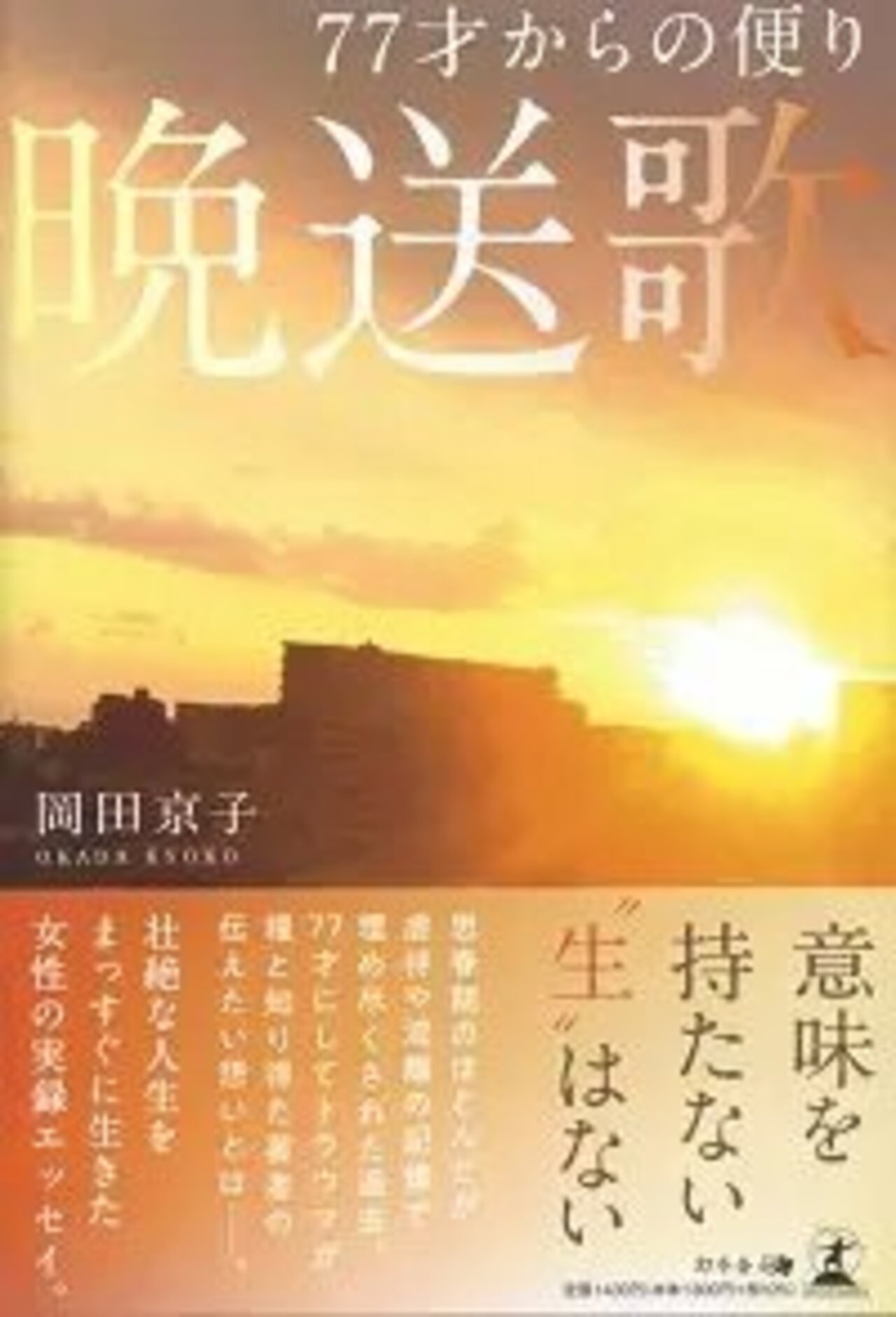第一章 父と信じて、母と信じて。
引き裂かれる心。
肺炎になった。
母は父(養父)に知らせたらしく、彼は私の傍に寄り心配そうに顔を覗き込む。ウナギの焼いたのや肉などを持って逢いに来ていたが、回復とともに来なくなった。そしてその時が私が憶えている限り唯一親と感じられた人との最後の別れだった。
然しここでも天はドラマを見せつける。
私にとっては最初の心つぶれることが待ち受けていた。程なく、多分程なくしてそれは起きた。割れたガラス窓からは冬の終わりでも未だ冷たい風が吹き込み私達親子は夜のとばりの中、もう布団の中にいた。母がポツンと云った。
“美夜子は産みの母と育ての母とどっちがええねん”
何のことか深くも考えず“そら産んでくれたお母ちゃんがええわ”と答えた。それは「お母ちゃんが一番」の答えの代わりだった。
そしてそれは全く突然に起こった、“そらそーやろ、ほんまのお母ちゃんがええやろ、どうせ私は育ての母や、ほんまのお母ちゃんとこに帰り、毎日おいしいもんも食べれるし、きれいな白いレースの服かて着れるからな、そらほんまのお母ちゃんがええやろ”とわめく様に叫ぶ。
私は訳も解らず“育てのお母ちゃんがええ、育てのお母ちゃんがええ”とそれしか答えられずクチャクチャの壊れた人形の様に体が、心が、引き裂かれていた。
彼女の無情の日々は、止めようのない口惜しさは、彼女の心身を痛めつけ、その切なさは未だ5才の私に向けるしか無い程の孤独だった、と今は解る。私は只、泣きじゃくり自分の世界は消えていた。
その日から養母の意味もわからずに、朧げながらに知ってしまった「他所の人」……私の心も壊れだし孤独の衣を纏う永い年月の始まりだった。
暫くはどう過ごしていたのか、記憶に無い、只、70才の今解るのは記憶に無い時のことは平穏であったといえる。その日、知らない女性が“今日、お母ちゃんご機嫌ええから会えるよ”と、呼びに来た。養母は同じアパートの人の世話になっていたのだ。私は嬉しくて飛び跳ねるように会いに行った。
彼女は布団の上にはんてんを着て私に背を向けて座っていた。“お母ちゃん”と背中にぶつかる様に抱き着いた。その肩に置いた右手を取って云った言葉は、聞こえた言葉は“あんた帰ってきてくれたん”の甘い声。私は不思議な気がして、彼女の顔をのぞきこんだ。
次に聞こえたのは“お前誰や、何しに来たんや”の怒号だった。後はどうしたのか、誰かが部屋から連れ出してくれた憶えがある。そして、私達二人はきっとそんな人達のお陰で又命をつないだと信じる。