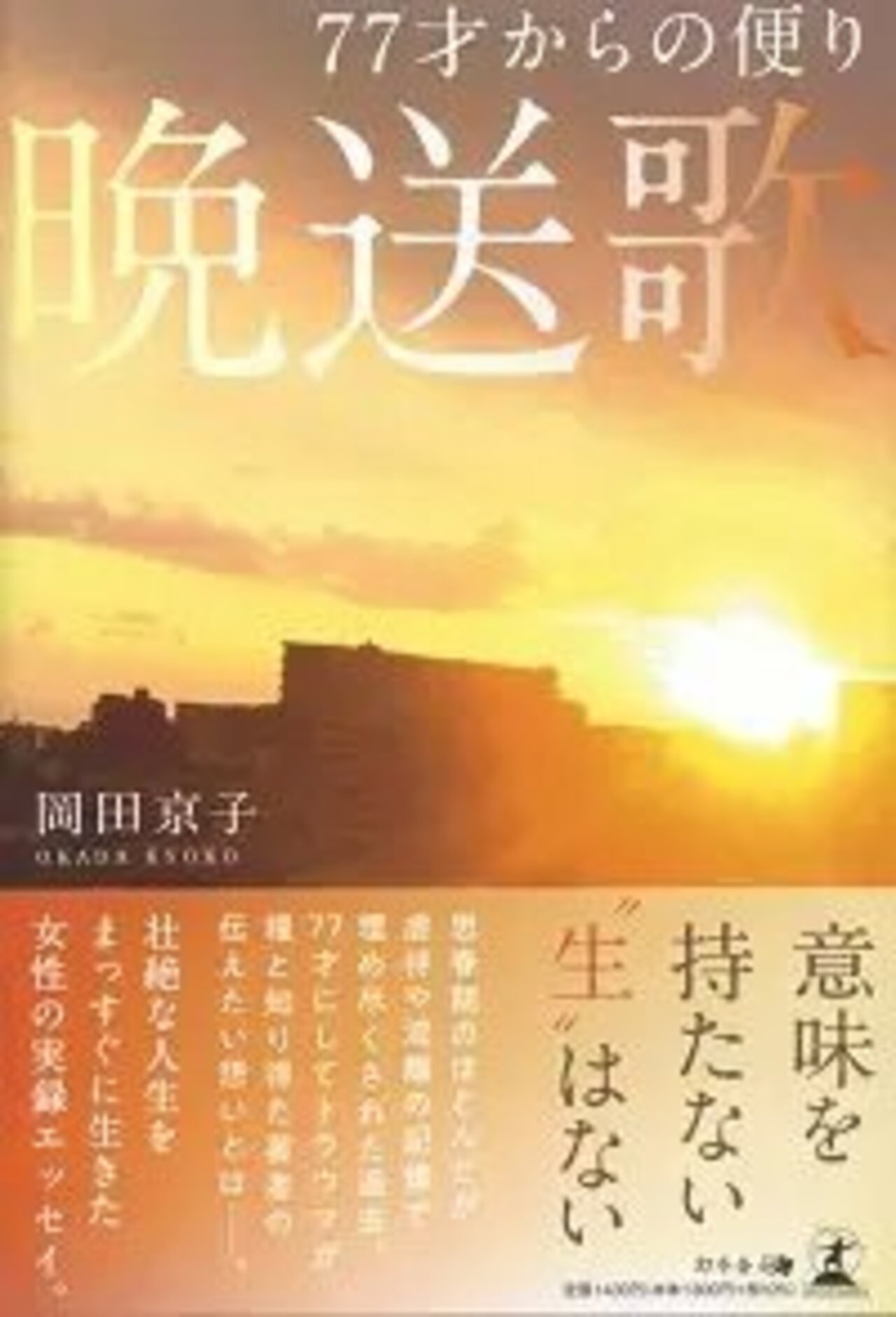第一章 父と信じて、母と信じて。
父はかげろう。
その頃は有った町内揃っての大掃除の日、畳まで干して一斉に“コレデモカ”とばかり、大阪弁で表すと“シバキタオス“のである。信子は普段自分のしていることが近所の話題になっているらしいのには頓着ないのか、私は初めて家の外に出された。
私は壁にもたれて燦々と降り注ぐ太陽の光の中、別世界に居た。近所のおばさんたちの囁く声がした“あの子やで虐待されてんの、警察に知らせたったらいいんちゃう”と私を見ている。それは同情に満ちた表情で、私は恥ずかしいよりもその日の太陽の様に優しく思えた。
一人のおばさんが私の手を取りみどり色のまんじゅうを乗せ、そっと両の手で私の手をつつみこんだ。
“一人で食べるんやで見つかったらあかんで”
と耳もとで囁いた。それは両の手いっぱいの大きさだった。私はその意味を理解できず自分のものとして嬉しくて“おばちゃんにもらった”と報告した。
程を待たず私の手の平から消えた。相変わらず叩かれていた、いつもの長い竹の物差しだ、何故だか痛みは憶えていない。いつもより長い折檻のせいか又布団の上に吐いてしまった。それを見て又彼女は振り下ろす。叩かれながら“ええねん、今日お母ちゃん来てくれるねん”と心がキュンとなる想いだった。
それは聞こえた。遠くから遠くから、お母ちゃんの履いている下駄の音が。カンカンなのかトントンなのか段々近くなる。1階の引き戸の開く音がして
“こんにちはー”
と何度か云い
“美夜ちゃん”
と呼びながら2階の私の置かれている部屋の襖が開けられた。
その日から私の居場所は変わった。実父と知らなかった父の知人宅にお引っ越し。母と思っていた養母から何十年後に聞いた話。”何か気になって顔だけ見るつもりで行った、あまりのひどさに置いておかれへんかった”と。かく云う彼女も私と一緒には住めなかったのだろう。
新しい居場所には2人の男の子が居たが物静かで叩かれることは無かった。でも私はそこには居ないが如く誰とも話さず、食事は一人。時にはおやつ、食事時に、中庭に出され障子にはめこまれたガラス窓から一家団らんを見ていた。おじさんと云う人の憶えは和服姿の二度程か。そこにも優しくとも小さな痛みがあった。
或る日、中庭に出されていると、雪が降ってきた。私は辛くは無かった。そのせまい閉ざされた、でも美しい中庭での白い小さな花の様な雪は夢景色の様で、それだけで満たされた。Yさんと云うおじさんのお家、小さな傷と美しい雪を憶えた静かな家族だった。