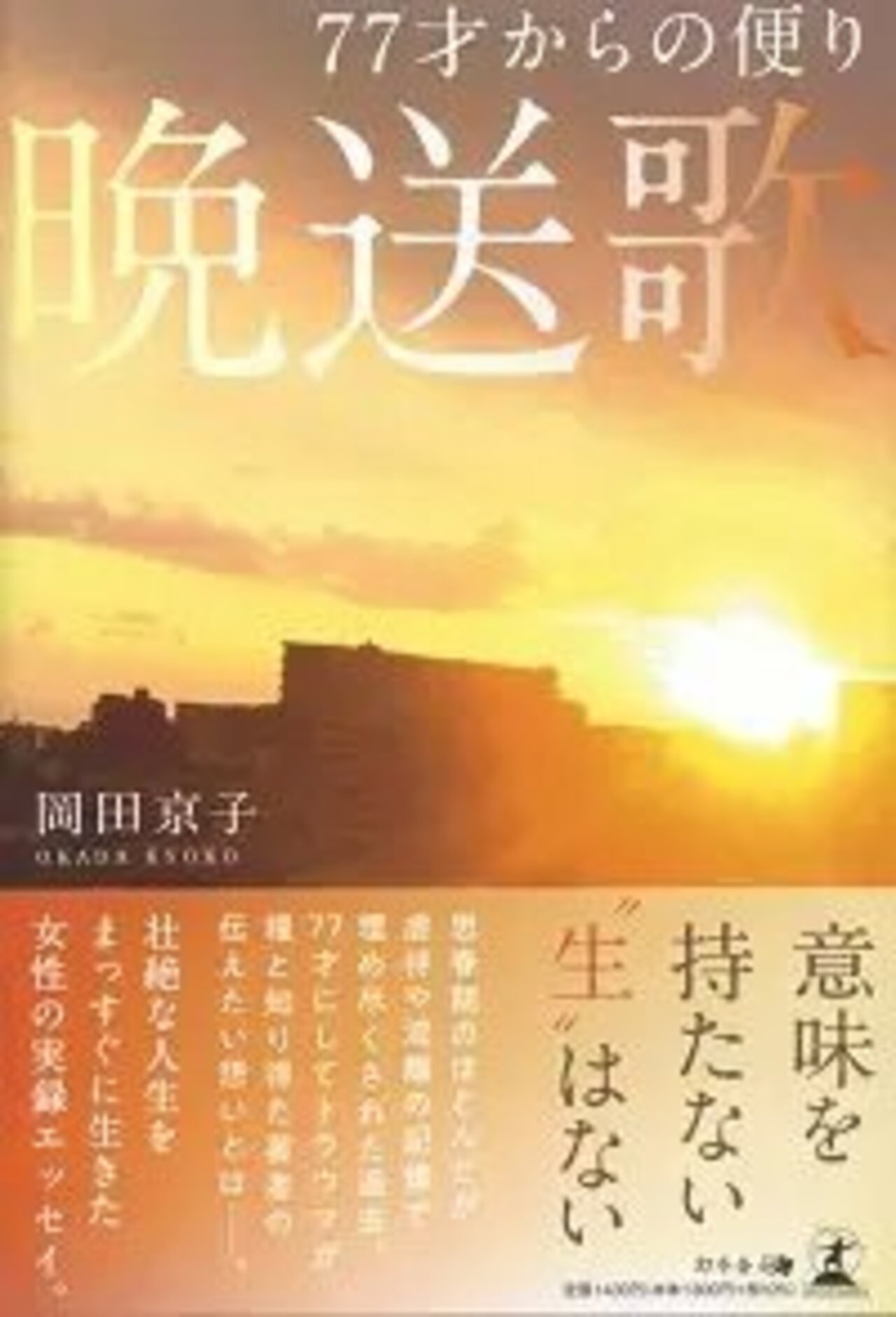第一章 父と信じて、母と信じて。
父はかげろう。
その日私は父(後に知る養父)が買った着物を、思えば父の愛人が買ったかも知れぬ着物を着せられ母と雨上がりのぬかるんだ道を水たまりもさけずに只々歩いていた、何故か履いているのは運動靴だった。一足ごとのぬかるみは母との別れを告げる如く重みを増す。
解っていた、どこかに連れていかれ置いていかれるのだと。母の私の手を握る強さが私を悟らせる、私も滑らない様、こけない様一生懸命母の手をつかんで歩いた。お母ちゃんは私が居てると困るんや、ダダをこねたらあかんねんと、泣き声は出さずにいてもウッウッと喉が鳴り涙はあとからあとからこぼれた。
辿り着いたのは、何年か後に知る実父の家、これから先に父と云う人は彼なのである。父は実母と別れた何年か後、信子と云う女性と再婚して未だ間が無かった。当然信子にとっての私は重荷以外の何者でも無い。手を強くつなぎ合った母は何時消え去ったのか。
その時から知った肉体的虐待、精神的虐待、なぜ憶えてしまっているんだろう、馬鹿な私。私の居場所、2階の三畳程の広さか、布団以外何もない部屋は私に広く感じさせたのかも。
然しそこはその日、その時から牢獄になった。窓もなくあるのは隣の部屋をつなぐ襖のみ、彼女はほとんど私の居場所には入ってこない、入って来る時は1mほどの長さの竹尺を持ってくる、おねしょをする私を折檻するために、あるときは理由も無く。太ももの傷跡は今も時ともなく疼く。何度かに1度はあまりにも叩かれて空のお腹でも吐いてしまう。日に日にくさく汚物にまみれる私の居場所、それでも彼女は布団を干したり拭いたりしない。その異臭は今も鼻に残る。
父の手前か、たまに夕食を共にする。幾度あったのか、憶えているのは1度だけ、3人揃っての食事、カレーライス、美味しくて美味しくて〝お代わり〟の皿をそっと出したら私を下から舐めるように見つめる、父は何も云わない、何も云えない。ちゃぶ台の横は押し入れ、いつも開けっ放し、そこにはいつも並ぶ3つのガラス瓶、彼女はそれを空にしたことがない。
私はホッとして横目で見る、命の綱なのだ。信子の目線も恐れぬ程の空腹に耐えかね、ドロボウの如く口に運び命をつないだ。3つのガラス瓶の中には、だしジャコ、だし昆布、そして何よりのもの、宝石よりも〝キラめいているざらめ〟、黄金色の輝きはこの上なく甘美で、指にのせて舌まで運ぶ恐怖の一瞬は私にとって小さな幸せのひと時だった。