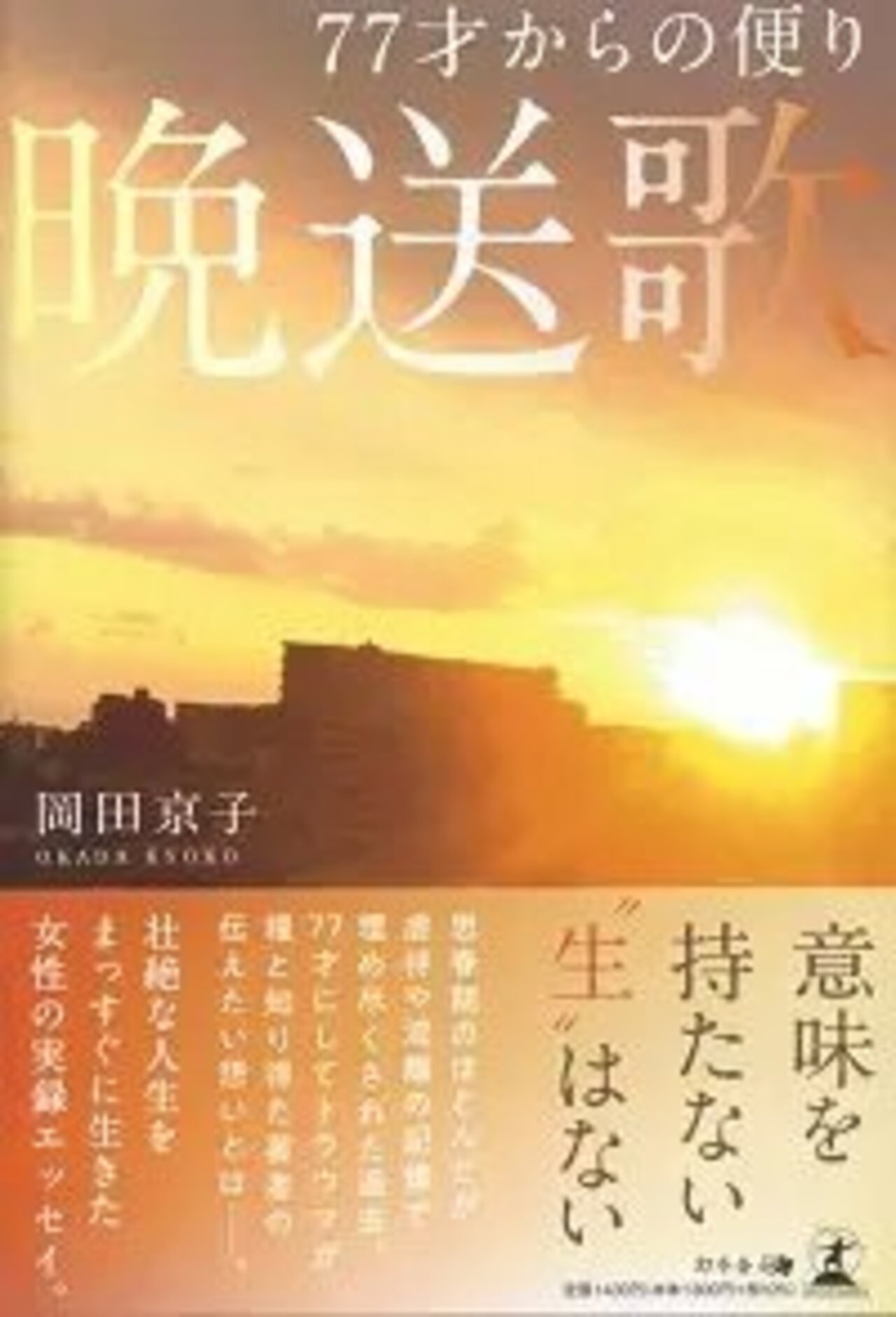第一章 父と信じて、母と信じて。
障子に映る二人の影、大柄な彼に小柄な彼女、とてもかなわぬ相手に金切り声で言葉にはなっていないあらん限りの罵声、口でかなわぬ彼は彼女を殴り倒す。私の記憶の中の初めての母の存在の形だった。
そのことから間もなく父、母、そして私、薄暗い部屋は隣の姉妹の奥座敷、ちゃぶ台の上に何だろう白い用紙。父は云う“美夜子は俺が育てる、心配せんでええからこれに判を押せ”と、母は只々泣き崩れ、姉妹は言葉もはさめず見守るしかない様子。私は訳も何も解らず辛く(お母ちゃんが泣いている、白い紙のせいで泣いている)とむやみに悔しく“お母ちゃん泣かしたらアカン”とその紙を手に取りビリビリに破り捨てた。
そのことが私の人生を、母の人生をどう変えたのか、それとも人の運命は変わり様も無く、形を変えて苦しみを与えるのか。先の見えないトンネルの始まりだった。そして私の人生で唯一抱きしめてくれた人との別れの日だった。
河辺のほとりで。
私に優しかった父は母には非情であった。夫婦の住居を売り払い、給料も全て有るもの全て持って消えた。母を選んだと思って、私への愛情までも捨て去ったのか。その日から二人は寄る辺もなく母は歩く道さえまっすぐ歩けたろうか、私は母の影を追うことしかできず私の存在は、何の、何の、意味も価値も無かったに違いない。
父の勤め先である神戸まで行く。社長と妻、“庄内さんは仕事を辞めると云って給料はきれいに清算していった”と、彼女の辛さと虚ろさが幼い私にも流れてくる。社長の顔は勿論定かでは無いが気の毒にの心は伝わる。それでも目の前に出された三角のケーキから目が離れない、母が食べないものを私が食べるわけにはいかない、躾が良い訳ではなく彼女の言葉の荒さが怖かったから。
帰り、社長がそのケーキを紙にくるんで“後で食べや”と持たせてくれる、味に憶えは無いが目から何かが落ちたのを憶えている。下を向いて小さな声で“ありがとう”と云えた。
その日から私達親子には今日、今から、何が食べれてどこで眠ることができるのか頭が働くよりも只必死で宛てもなく歩き回るだけだった。その上の母の辛さは煙草が吸えないことにもあり、私に煙草の箱を踏ませ、少し長い吸殻は拾わせ、吸える時は大きな息で吸い込み続けた。神戸は都会で吸殻もよく落ちている、私はチョロチョロとこまめに働いた。神戸、西ノ宮、踏切りの側、チンチンと鳴る音、光景が焼きついている。暫くは其処が彼女に安らぎをくれていたのか?