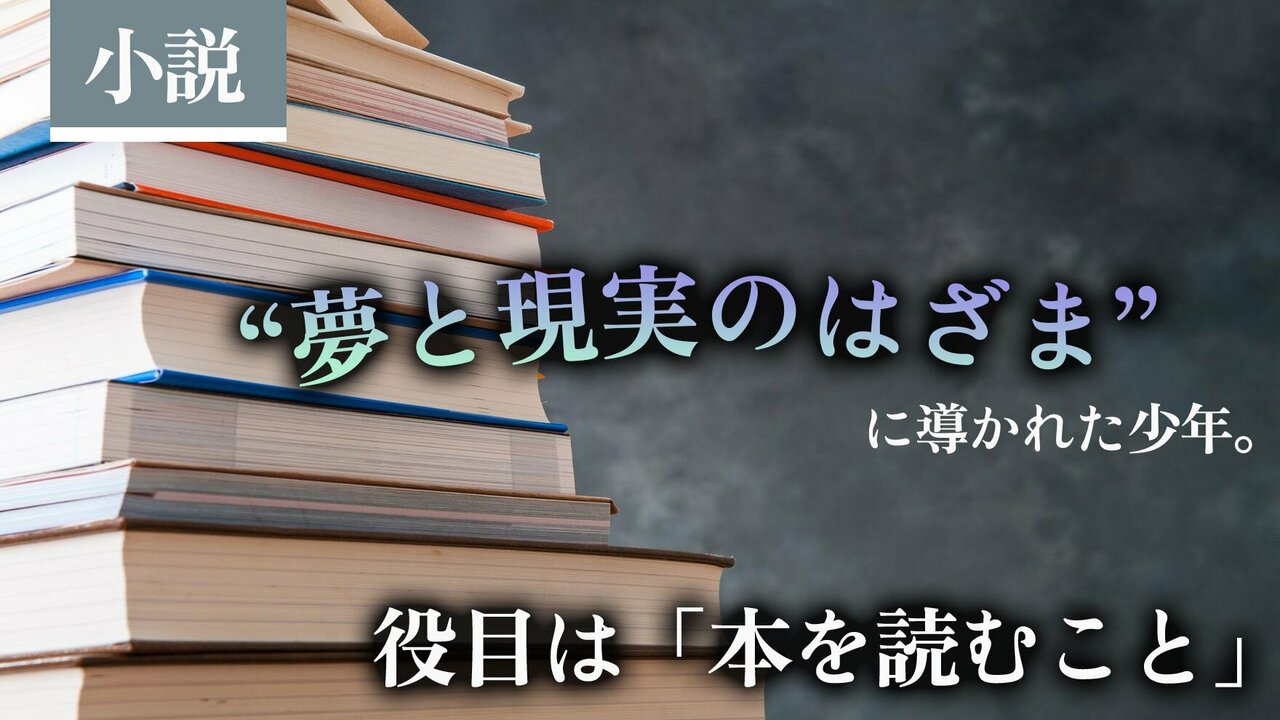気づくと、夕暮れ時の砂漠にいた。これは夢なのだろうか? それとも現実なのだろうか? さっき布団に入ったから夢だと思う。しかし、砂の感触がちゃんとしている。なんだか肌寒い。砂漠の夜はかなり冷え込むと、どこかで読んだ覚えがある。そして、傍らにはまたスケッチブックと鉛筆と消しゴムとあの黒猫。
前回と異なるのは、水彩色鉛筆と絵筆のセットが一緒に置いてあることだ。また描けというのか。いや、描かねばならないのだ。またあの衝動に駆られる。
衝動に導かれるままに、鉛筆を踊らせる。黒猫の視線がスケッチブックに注がれている。月も太陽も見えないが、オレンジ色と紫色のグラデーションが綺麗な空だ。たったひとつだけ瞬く星と砂の山。近くにオアシスもないようだ。
鉛筆でおおまかに描き終えると、今度は水彩色鉛筆の出番だ。自分なりに夕暮れ時の色をつけていく。まるで、混ぜる前のカシスオレンジのような空だ。あっという間に描き終えた。しかし、何か物足りない。
「なんだろう……?」
黒猫がスケッチブックに手を出して、「にゃあ」と鳴いた。そうだ、肝心の君がいなかった。
「君も入れないとね」
黒猫は、自分がモデルになったことに気づいたのか気づいていないのか、遠くの星を眺め出した。しっぽが揺らめいている。艶やかな黒。いつか読んだ雑誌によると、ほとんどの黒猫は茶色などの色が混ざっており、純粋な黒ではないらしい。ただ、今目の前にいる黒猫は、“漆黒”という言葉がぴったりな、本当に真っ黒な猫だ。
「君は、本当に綺麗な黒だねぇ」
思わず話しかけてしまった。すると、話がわかるのか背筋をピッと伸ばして、嬉しそうに(そう見えただけかもしれない)「ニャア」と鳴いた。そして、前足を前に出して、あくびをしながらヨガの猫のポーズのように背中を伸ばしたかと思うと、撫でてと言わんばかりにこちらに視線を向けてから、そばで丸くなった。
「猫団子……」そう言いながら、黒猫の頭を撫でる。
黒猫は心地がいいのか、ゴロゴロと喉を鳴らした。 改めて絵を見てみた。砂漠ゆえの殺風景な感じもあるが、猫と星で少しは絵が生きているように見えるのではないだろうか。決して絵が上手いわけではないが、昔から絵を描くのは好きだった。しかし、世の中は生き残ることのできる天才がゴロゴロしている。
「絵描きになりたかったこともあったなぁ……」
なんて一人こぼしながら、空を仰ぐ。肌寒さを感じながら、空のグラデーションに圧倒された。
「あぁ、綺麗だ……」
たったひとつ、どこか寂しげに瞬く星を眺めながら、黒猫を撫でる。至福の時とはこのことだ。しかし、終わりというものは突然やってくる。まばたきをした瞬間、私は自分の布団の中にいた。撫でた時に抜けてしまったのであろう。黒猫の毛が、指に絡んでいたのだった。
一体全体、どうしたらこうなるのか。わからない。どうしても。
「どうせなら、あのままもう少し撫でて、星空を見ていたかったなぁ……」
ぼやいて、そのまま目を閉じてみても何も変わらなかった。黒猫の毛もついたままである。