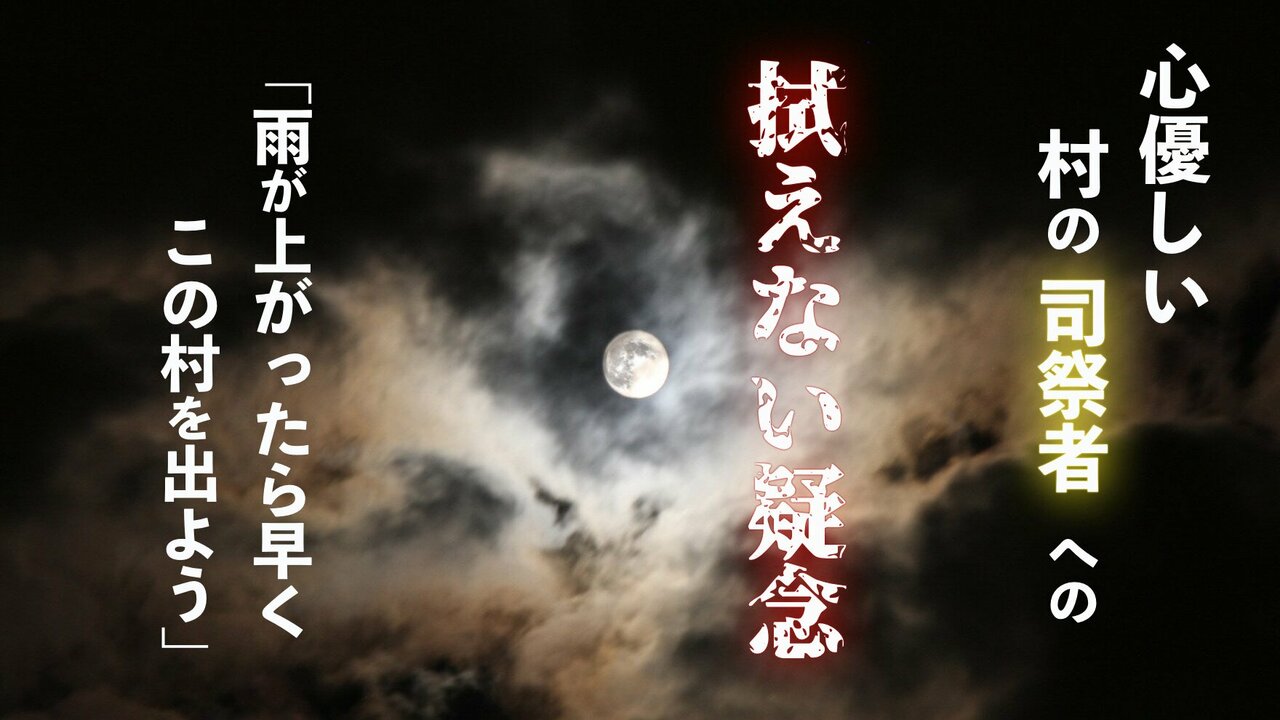「アオキ村はここに長いんですか」ゲイツが言った。
「八年になります」
「ほお、案外新しい」
「けれど、土地には二十年」
「どういうことです?」
「村の人々は大半が流浪民です」
「流浪民」
納得したように赤髪の頭が揺れる。流浪民とは、部族単位で世界各地を流れ暮らす漂泊民族。生活形態としては一定の土地に居つくことがない。
「だけどその言い方だと、単位は一つじゃない」
「複数の部族で成っています」
言われてみれば居流れる村人の顔や骨格の造りは根本的なところで微妙に違っている。なるほどあらゆる種族が混ざって結成した集団なのは得心がいく。新参者を手厚く保護するのはそういった成り立ちがあるからか。
しかしエリサ達を攻撃し追い払おうとしたことに説明がつかない。そもそも流浪民とは一個の血族から成るのが普通であり、しかも特性上、自決意識が強く複数が集合することはあり得ないのだ。ただ、超常事態さえ起きなければの話だが。
「隠れているんですね、奴らから」
ゲイツの問いをサヤが首肯する。アオキ村の人々はなにを遠ざけようとして部族の垣根を超え、集まり、深山の奥で隠れていたのか。人々を恐れさせる存在……その名をエリサは知っている。
「無機生命体、機械兵」
堂内から短い悲鳴がいくつも上がった。それは命を持たない殺戮者。人類が自らの手で生み出した滅びの兵器。世界の歯車を狂わせたのは紛れもなく奴らの存在だった。人類の絶滅を目指す機械の悪魔から逃れるべく人々の多くは息を潜めて暮らしている。
アオキ村のような排他的隠遁者もその一例に過ぎない。敢えて外の世界から自分達を閉ざしているのだ、見知らぬ者を警戒するのは当然の心理。それほどまで人々は機械に……いや、自分以外の存在に不信感を抱いていた。自分を守れるのは自分しかいないのだから。