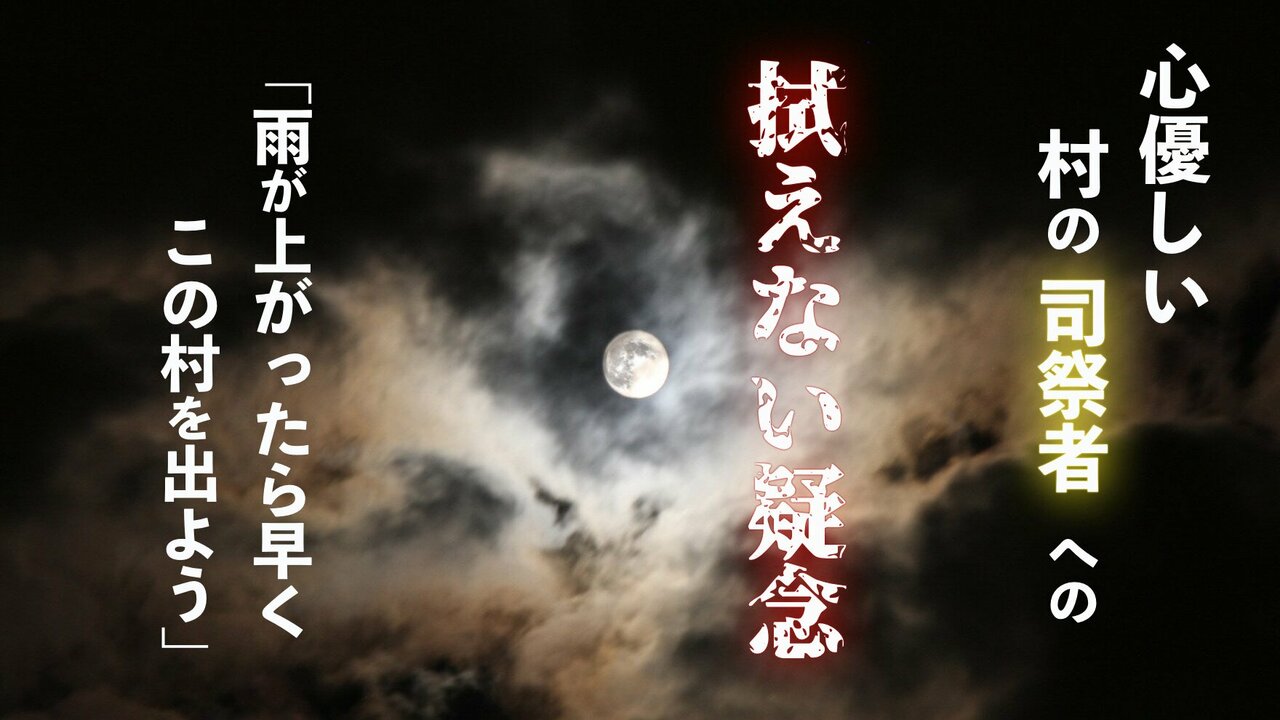第二章 赤い双眸
眠りから覚めた。冷えた空気が睡気を引き下げる。庵の中には闇が溜たまっていた。まだ夜か……。窓からは夜虫の声。ゲイツは壁にもたれ寝息を立てている。
エリサは掛け布を外し表に出た。まともな寝床が与えた休養は体をいささか軽く感じさせる。雨雲はすでにない。満天の星彩が黒こく洞々に散りばむばかり。方々には篝火の道みち標しるべ。火粉のはじける音が響く。アオキ村は死んだように眠っていた。
(夜明けは、まだ先だな)
しばらく歩き手ごろな切り株に腰を下ろした。風が木々を吹きさらい山を轟と唸らせた。夜霧の向こうに川が流れているらしい。そんな音さえ聞こえてしまうあたりこの土地がいかに文明に隔絶しているのかをエリサは再び実感した。エリサは懐から携行式電子記録端末〈プツロングラ〉を取り出し起動させた。
「目的地までの最短距離を教えて」
『カシコマリマシタ』
案内音声に伴って手元の端末から放出された光は空中で―エリサの目の前で固定された。ログラム・ヴィジョンである。〈プツロングラ〉は虚空に表示した電影画面に現在地からあらかじめ設定していた地点までの道のりを計算し、地図として表示してくれる。……はずなのだが……。
『現在地ノ情報ヲ取得デキマセンデシタ』
やはり電波は届いていない……か。旅の必須装備として幅を利かす機器ですらこの有り様ならば自分の求める情報を村人が持っていようか。いや、その望みは薄い。とにかく明日にでも発とう。手遅れとなる前に。
立ち上がって寝所に戻ろうとした時、総身がにわかに粟立った。エリサは闇を睨んだ。
―気配だ。周囲に何かいる。鬱蒼の森、建物の影、畑の畔溝……ありとあらゆる闇の中でエリサは確かに耳にした。隠すつもりのない、殺気じみた息遣いを。間近な気配に振り返る。息遣い、それは感情の高揚に伴う代謝熱を解消すべく行う生理現象。ただ「それ」が興奮しているのかといえば、否である。比喩にしては、寄り添いすぎだ。
硬質な部品がこすれ合う不愉快な金属音。原動機の排出する熱風。篝火に浮かび上がった影は機械がその身を構成し、エリサのよく知るところであった。