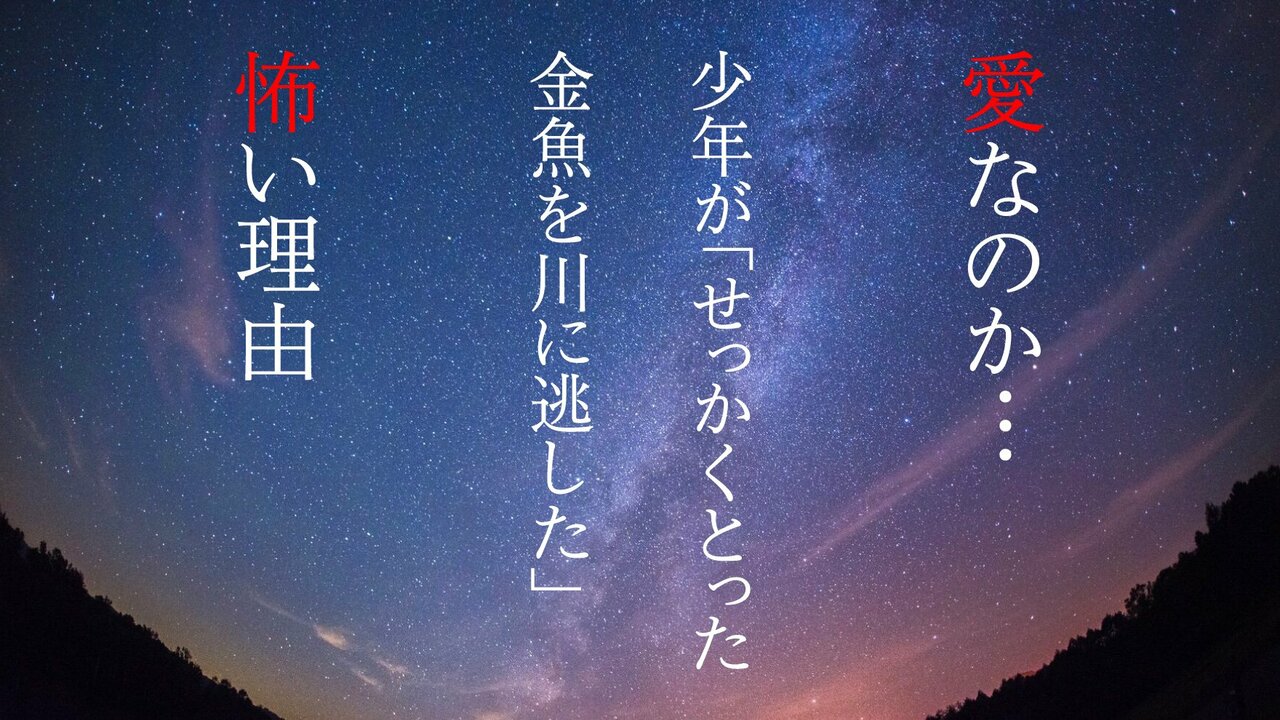少女に憑りつくもの
圭太は背丈と同じく、精神的にも早熟だった。だから、周りの期待に過剰に応えるクセについてクヨクヨ悩むこともなかった。人の目を気にしない人はいない。
今、そばにいる友人達だって、屈託なく笑ったりはしゃいだりしながらも、実は周りより自分が見下されないように虚勢をはったり、周りに合わせて心にもない返事をしたりしている。でも、別にそんな一面は誰にだってあることだ。おかしいことでも、悲しいことでもない。
変なのは、咲希だ。咲希は、周りに合わせない。周りと交わらない。同じ教室にクラスメイト達といながらも、一人だけ離れ小島に流されているみたいに、ポツンと孤立している。休み時間も、授業中も、いつもうつむくか、窓の外を見て、ぼんやりとしている。表情はいつも寂しげだ。
先生が授業中に時々発するジョークも、生徒達の笑い声も、咲希の耳には入らず、音が周りをすり抜けていっているみたいに見える。そこにいるのかいないのか、いっそ圭太の目には見えているのだけど、実は異次元空間にでもいるのではないかと思うくらい、いつでも咲希は周りの出来事に無反応だ。
咲希が教室で一人でいる時、圭太が話しかけてみると、話しかけられたことをとまどっているような顔をした。返事はそっけなくていつも会話は続かなかった。ごくまれに笑うこともあった。けれど、それは作り笑いみたいに見えた。たぶんそれは、笑っている時でさえ、どこか咲希の顔が悲しげに見えたからだ。
昨日、図書館で借りた本に、「憂い」という言葉が載っていた。辞書を引いてみて、咲希にぴったりな表現だと思った。咲希の顔には、いつも「憂い」が影のように暗がりをつくってみえた。そんな咲希は、祖母と二人で屋台を回っていた。圭太は、それをふと不思議に思った。