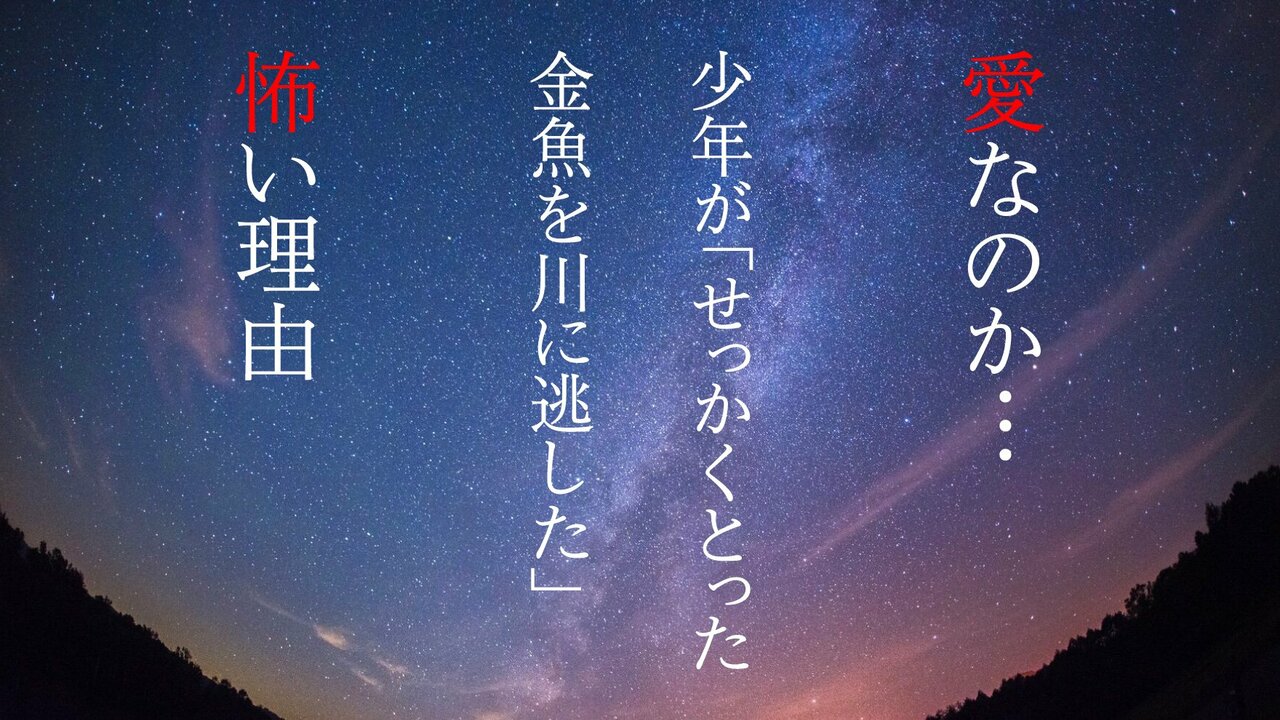少女に憑りつくもの
一人きりで、夏の夜道を歩いて行く。住宅街を横切り、帰りの道中にある公園を通り抜け、信号を渡って、また住宅街を抜けていく。
住宅の密集する辺りでは、風が少ない。夏の日差しの熱を残した生温かい空気が、夜でも辺りに満ちている。それでも、空を見上げれば、星たちが涼しげに輝いていた。夜も真っ暗にはならない街中から見上げる空だけど、白鳥座やこと座といった、夏の星座がうっすらと見えていた。
圭太は空を見ながらゆっくりと歩いた。手にぶらさげられた金魚の袋が、歩くたびにゆらゆら揺れていた。星空の下を抜けて歩いて行くと、圭太はたまたま家に帰る途中の咲希を見かけた。二人は途中まで帰り道が一緒なのだった。
咲希は、圭太が歩いていた道の先で立ち止まっている。下駄の鼻緒で足が擦れたのか、街灯の柱に手を当てて体を支えながら、下駄を脱いだ足をピョコンと上げて片足立ちになっていた。その時、祖母はそばにおらず、一人きりだった。圭太は心臓が高鳴るのを感じた。
つかの間圭太は何かをためらうような顔を見せたが、手にぶら下がっている金魚の袋の紐をギュッと握りしめると、腹をくくったような表情をして、「真島!」と、呼びかけた。
咲希が片足を下ろして振り返る。圭太は咲希に走り寄ると、息を弾ませながら、手にしていた金魚の袋を差し出した。
「これ、やるよ」
咲希は、戸惑った顔をした。それから、首を横に二、三度振ると、「いらない」と言った。
「どうして?」
圭太は、きっぱりと拒否されたことが自分でも驚くほどショックで、ついいら立った声が出た。
「だって、金魚を取り損ねて、残念そうな顔をしてたじゃないか」
咲希が目を丸くしたのが見えた。
「見てたの?」
圭太は、顔を赤らめて、咲希から目を逸らした。
「見てたんじゃない。たまたま目に入ったんだ」
咲希は、そんな圭太の様子をじっと見つめて、長い間黙っていた。どのくらいの間があっただろう。気まずく思っていた圭太の耳に、ふと、柔らかな声が聞こえた。
「ありがとう」
圭太が咲希の顔を見ると、彼女は微笑していた。教室では見たことがない表情だった。街灯の明かりに照らされながら微笑する姿は、咲希自身がうっすらと光を放っているみたいに輝かしく見えた。そんな彼女は穏やかな声で、優しいね、と圭太に言った。
「でも、やっぱりその金魚はいらない。自分ですくったとしても、帰りに川に逃がしてあげようと思ってたの」
「なんで? せっかくとったのに」
「小さい生き物は大抵長く生きられないでしょう? 死んじゃうのが怖いから」
急に顔を暗くして、咲希は言った。死ぬのが「悲しい」でも、「寂しい」でもなく、「怖い」と、そう言った。咲希のその言葉が圭太の耳に強い印象をもって残った。じゃあ、さようなら。咲希はそう言って、圭太に背を向けた。その背中は寂しげに見えて、圭太は胸の奥をキュッとつかまれたみたいな痛みを感じた。
「ねえ!」
圭太は咲希を呼び止めた。
「真島にお願いがあるんだ。急に変なこと言うけどさ……」
もう一度振り返った咲希に、圭太は言った。
「今から一緒に川に行ってほしいんだ」