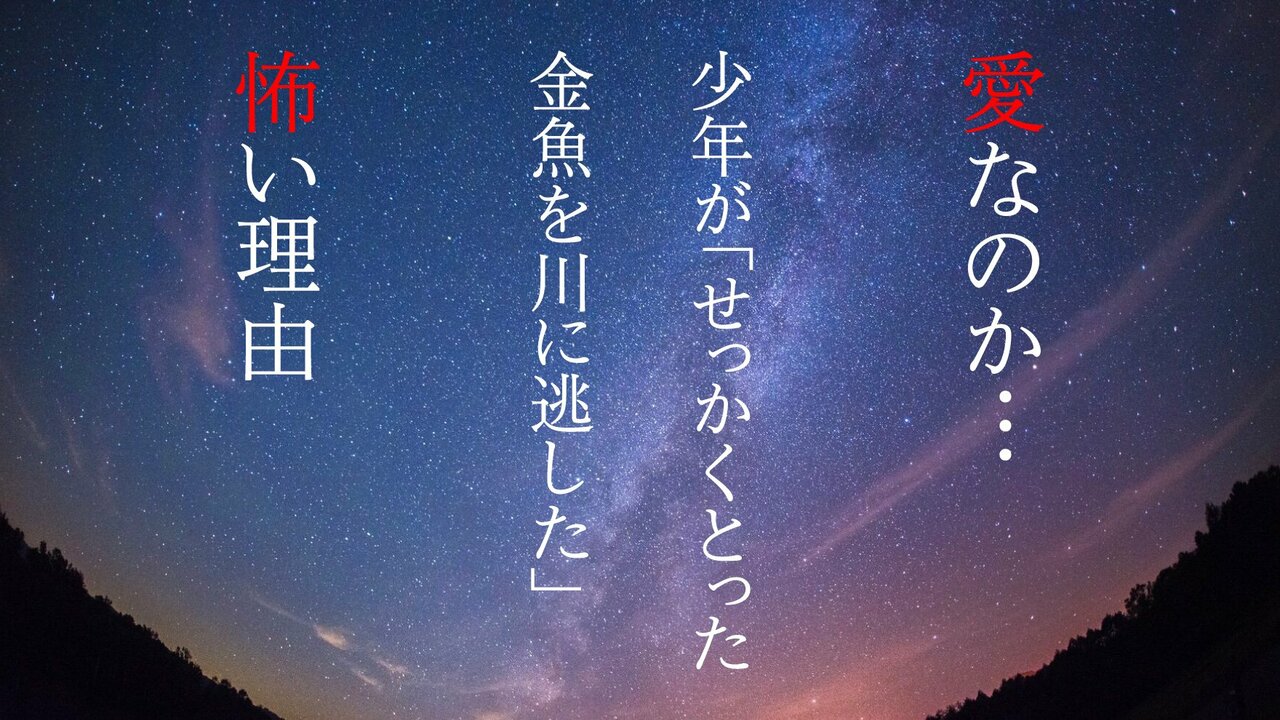少女に憑りつくもの
咲希が金魚を目で追いながら、ポイを水面にそっと入れた。すると、途端に水がはねた。咲希が飛沫を避けようと顔に手をやる。金魚には逃げられたようだった。人形のように白くて滑らかな肌をした整った顔に、残念そうな表情が浮かぶ。
「でもさ、話は変わるけど」
さっき、咲希が母子家庭だと教えてくれた友人が言った。
「真島って、暗いけど美人だよね」
圭太はその言葉に心臓の鼓動が跳ね上がった。咲希から慌てて視線を逸らすと、自分の顔に手を当てた。自分の顔が熱を持って赤らんでいないか気になったからだ。
「ど、どうして急にそんなこと言い出すんだよ」
友人は笑った。
「何、あせってんの。変なの」
そこで、その話はおしまいになってしまった。友人達は、もう違う話をしている。しかし、圭太はどうして友人がそんなことを自分に言ってきたのか、気になって仕方なかった。自分がさっきから咲希ばかり盗み見していたのを、気づかれていたのかもしれないと思ったからだ。自分の胸の内を、友人に見透かされてしまった気がした。
圭太は、意識して、自分の視線を咲希がいる方から遠ざけた。もう咲希を気にするのはやめよう。しかし、そう思えば思うほど、今同じ運動場にいる咲希のことが意識された。圭太は、そんな自分を変だと思った。
「ねえ、圭太、次、何する?」
友人に尋ねられ、圭太は「うーん」と言って屋台を見回した。金魚すくいの屋台から離れていく咲希の姿が目に入る。咲希の手に金魚の入った袋はない。どうやら、一匹もとれなかったようだ。圭太は、それを見ながらアイスクリームのコーンの最後の一口を口に放り込むと、友人に、
「金魚すくいやろうよ」
と言った。友人の一人が「えー?」と不興気な声を出した。
「あんなの手にブラブラぶら下げてたら、遊びにくいじゃん」
「いいだろ、やろうよ」
珍しく自分の意見を押し通した圭太は、金魚すくいの屋台を目指して歩き出した。もし、金魚がとれたら―、と圭太は考えた。金魚がとれたら、咲希に渡してやりたい。でも、何と言って渡そうか。親しくもないのに、驚かせてしまうだろうか。でも、もし喜んでくれたなら、とても良いのに―。
そんなことを思う圭太の頬ほほを夏のにおいがする風がなでていった。