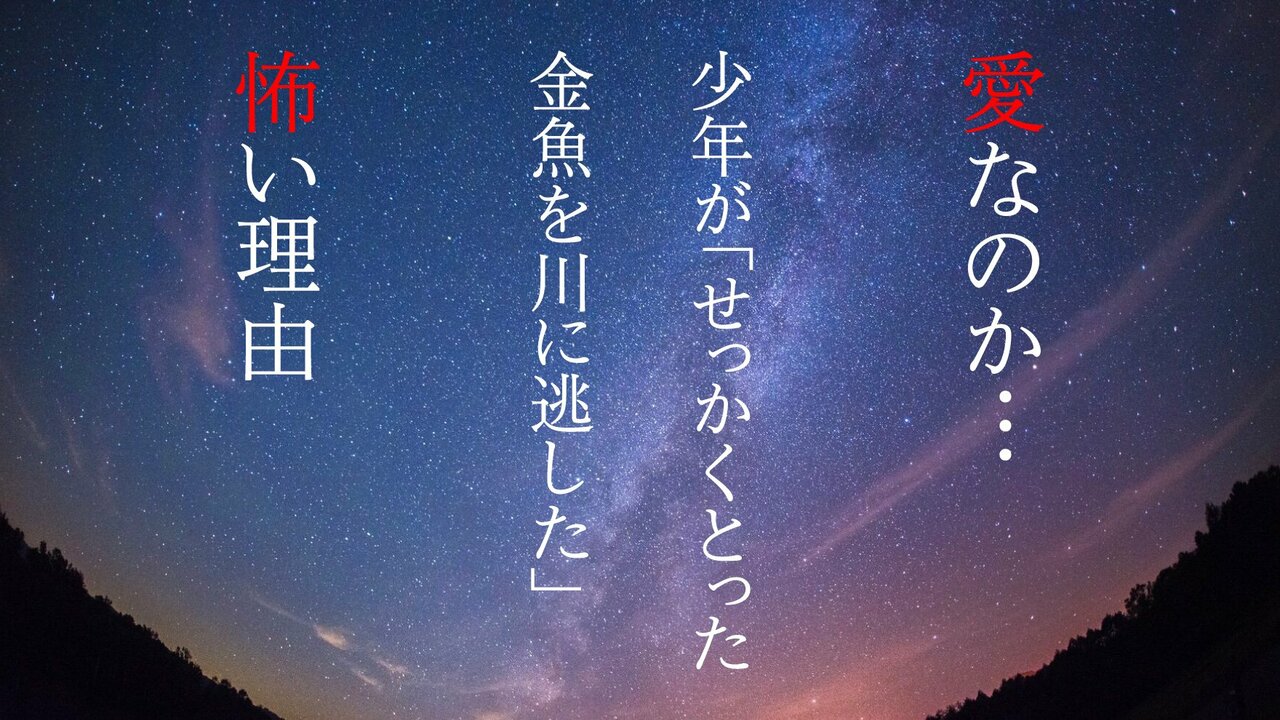少女に憑りつくもの
圭太の周りはいつもにぎやかだ。一年生の時から、ずっとそうだった。
圭太は勉強ができる。スポーツも大体得意だし、背が高いので、活躍しているとよく目立つ。おまけに温和で面倒みがいいので、いつでもクラスの人気者だった。そういうふうに目立つ者には、やっかみを言う人も現れるものだが、圭太はそういう人間を特に相手にしない。言わせておけばいいと、大人びた対応のできる人だった。
そういう感情的にならずにいつも落ち着いているような所も含めて、圭太はいつもクラスで憧れの的だった。学期初めのクラス会では、いつも学級委員に推薦されていた。そんな大人びた圭太だったから、友人達は、圭太の胸の内側に、夏の夕空を見上げてワクワクとするような、ロマンチックで子どもっぽい一面が隠されているとは思いもしなかった。
しかし、それは圭太の計算通りのことだった。
圭太は、友人達が心の底から好きだったけれど、彼らに自分の心の内をすべてさらけ出すことはできないでいた。圭太の周囲には常に人がにぎやかに取り囲んでいたけれど、圭太から見ると、周りと自分の間には見えない何かがあるように感じていた。壁とは言わないまでも、ガラスのようなもの―それは透明で見通しがよいけれど、しっかりとした厚みがあってちょっとやそっとの衝撃では割れないもの―があるようだった。
射的は圭太の圧勝だった。ビリだった友人が、約束通り何かおごると言ったが、圭太は笑って「いいよ」と言った。それから、みんなでヨーヨー釣りをした。アイスクリームを買って、それぞれの手に色とりどりのアイスを持ってブラブラ歩きながら食べたりもした。
次は何をしようか。友人の一人がそう言った時、そうだな、と言って屋台を見回した圭太の目に、真島咲希の姿が映った。