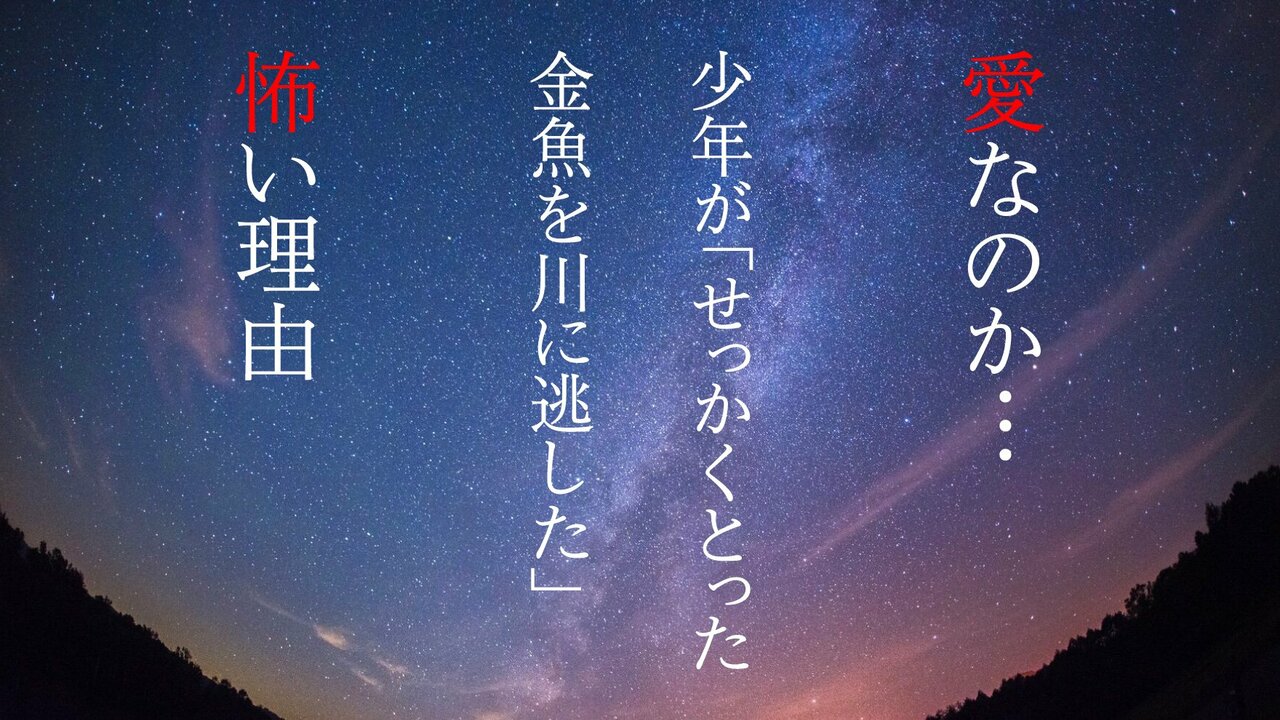少女に憑りつくもの
咲希は小学五年生になった。七月――。彼女は、今、教室の窓際の席で、もらったばかりの通信簿を手にしていた。そして、中をチラリとのぞいて、すぐに閉じてしまった。
深いため息が漏れる。毎年代わり映えのしない、ひどい評価のオンパレードだ。じっくり眺める必要もなかった。コメントの欄に書かれている先生からの言葉も、毎年似たようなものだ。遠回しに、咲希は周りの生徒達とは違うと書いてある。
咲希は、自分が周囲と違うということに強い劣等感を抱いていた。どうして、自分は普通にできないのだろう。他と違うと感じるたびに、そのことばかり考えていた。そして、母に申し訳なく思っていた。
母は、父が失踪してから、女手一つで自分を育ててきてくれた。母は気持ちが強く、がんばり屋で、風邪をひいたって家事も仕事もさぼったことがない。そんな母の娘なのに、なぜ自分は学校に通ったり、友達をつくったり、勉強したり、そんな普通のことさえちゃんとできないのだろう。咲希は、しばらく通信簿を手に持ったまま、ランドセルにしまえずにいた。
窓の外は明るい。真っ白い入道雲と、真っ青な空は、美しいコントラストを描いている。教室にいる同級生達は、明日から始まる夏休みに心を踊らせ、夏の日差しのような明るい顔をしてにぎやかに騒いでいる。教室の中の喧騒と、窓の外の蝉の声がにぎやかにこだましていた。
うきうきとした様子の生徒達に向かって、担任の先生が、「じゃあ、休みの間事故のないように、気をつけて過ごしてくださいね」と言うのが聞こえた。はーい、と答える同級生達の声の後に、たくさんの椅子が引かれる音がして、にぎやかな声と足音が教室の出入口に向かって一斉に動きだした。
やがて、先生も足音を残して、教室を去って行った。教室には、咲希一人がポツンと取り残された。咲希は机から立ち上がれずにいた。またもや、胸の内に巣食う何かが怪物のようにむくむくと膨らみ始める。体の中いっぱいに膨らんだら、咲希の皮膚を食い破って外に出てきてしまいそうだ。
誰か助けて。
咲希は、心の中でそうつぶやくのだけれど、やっぱりその声は誰にも届かないのだった。