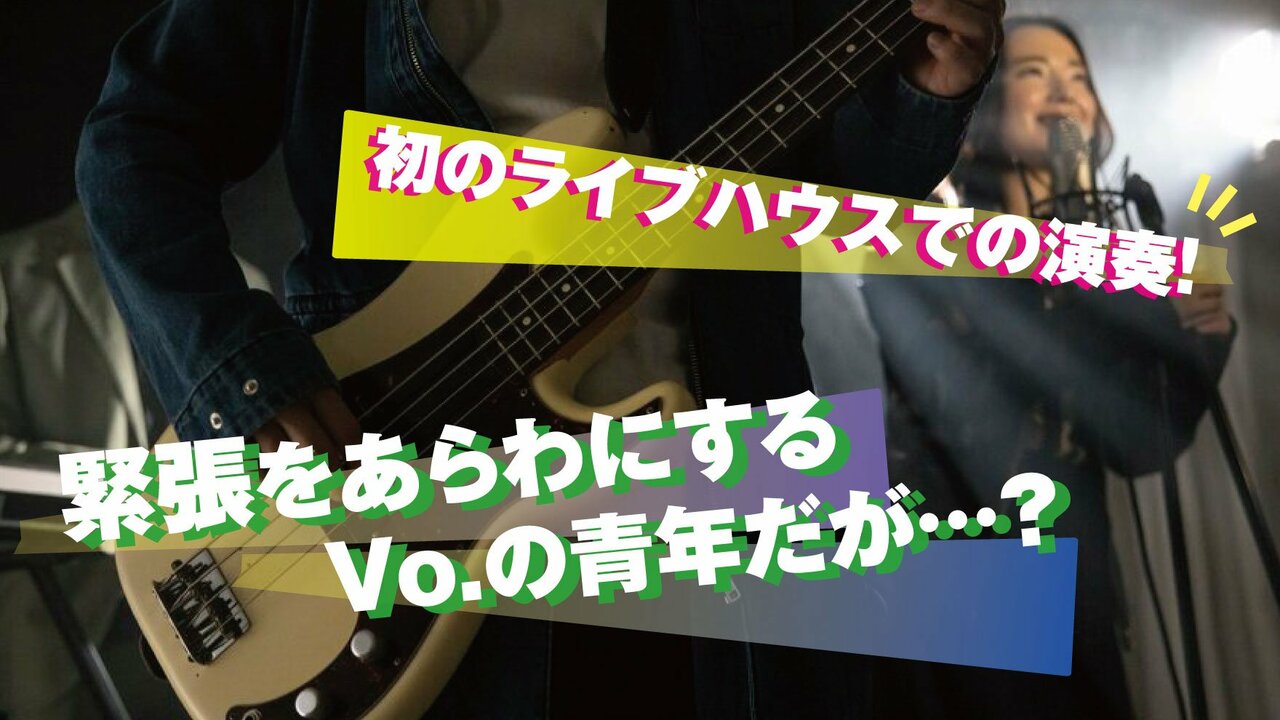7 故郷
人はどこかに向かっているようでいて、どこかに帰っているのではないだろうか。
例えば、会社に向かうということは、社会貢献したい自分に帰っているということ。歩くということは、もしかしたならば、敬虔なまでに、命の故郷のような場所へ、帰っている姿なのかもしれない。黒いスーツ姿に身を包むサラリーマンの群れを見て、青年は思った。それぞれが家庭を持ち、様々な家族事情があるなかで、家に帰るということは、平安を憩う温かなよろこび、思う存分素面で彷徨えてしまう、消えてしまいそうな本来の自分に帰っているのであろうと、思えてしまった。
青年は、こんなことを思いながら、最寄り駅から今日も緩やかな丘を、時々、ぼんやり霞んでいる月を見上げながら歩いていく。
この月も、どこかに帰っているのかもしれない。現象宇宙は、もはや、仮の姿でしかないのでは。この地球にもいつか寿命が来て、太陽が凍るときに、人は、その真価を輝かせるだろう。そのときに、大宇宙に骨だけになって漂うはずがない。元々、人は、心は、大宇宙をはみ出した存在なのだから。
目には見えない世界が、目に見える世界にやさしくアプローチし続けているけれども、いつか人類は、愛というものがあるのにもかかわらず、さらにその愛がどうのこうのと、残酷なまでに、突き付けられることだろう。ああ、魔的なプルトニウムさえ吉に転ずる業を! 無限と有限にある障壁や狭間、空間や距離を芸術的手法によって接近させ、バラバラになって機能しなくなったエレメントを統合する。
さらに言うならば、低俗だと見なされ人々が軽視してしまっているものに、その必要性や可能性、尊厳や高次なる神性さえ見いだし、聖なる息を吹きかけていくこと。既知のものには、未知なるものを、未知なるものには、手にとるように感じられる身近さや汎用性を、これこそ真のロマンだ!
このようなことに胸を馳せて、今日も青年は、五臓六腑の奥にある、燃えるような沈黙の車輪を回転させて、瞳を光らせ、まだ命を永らえさせようと、そう思った。