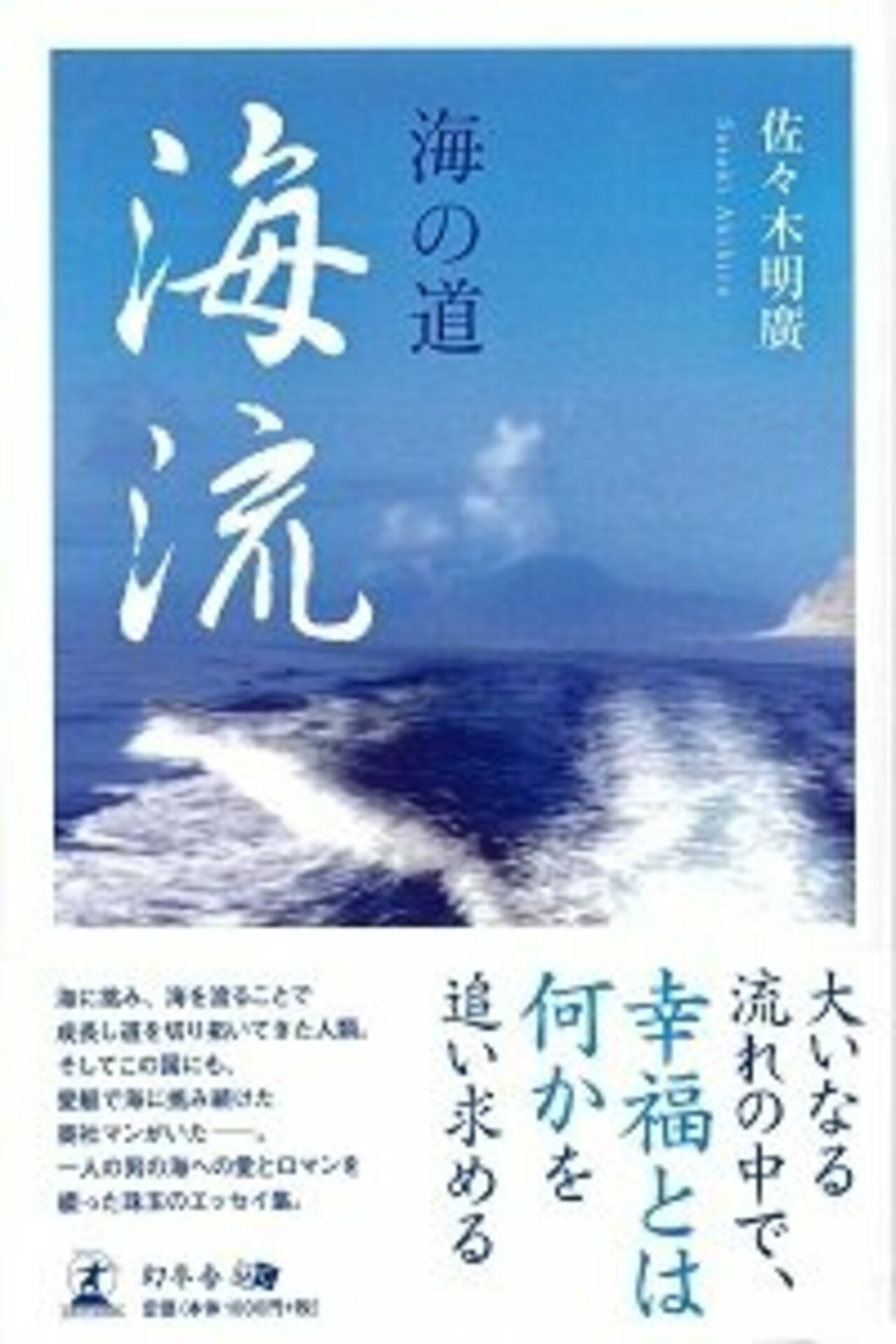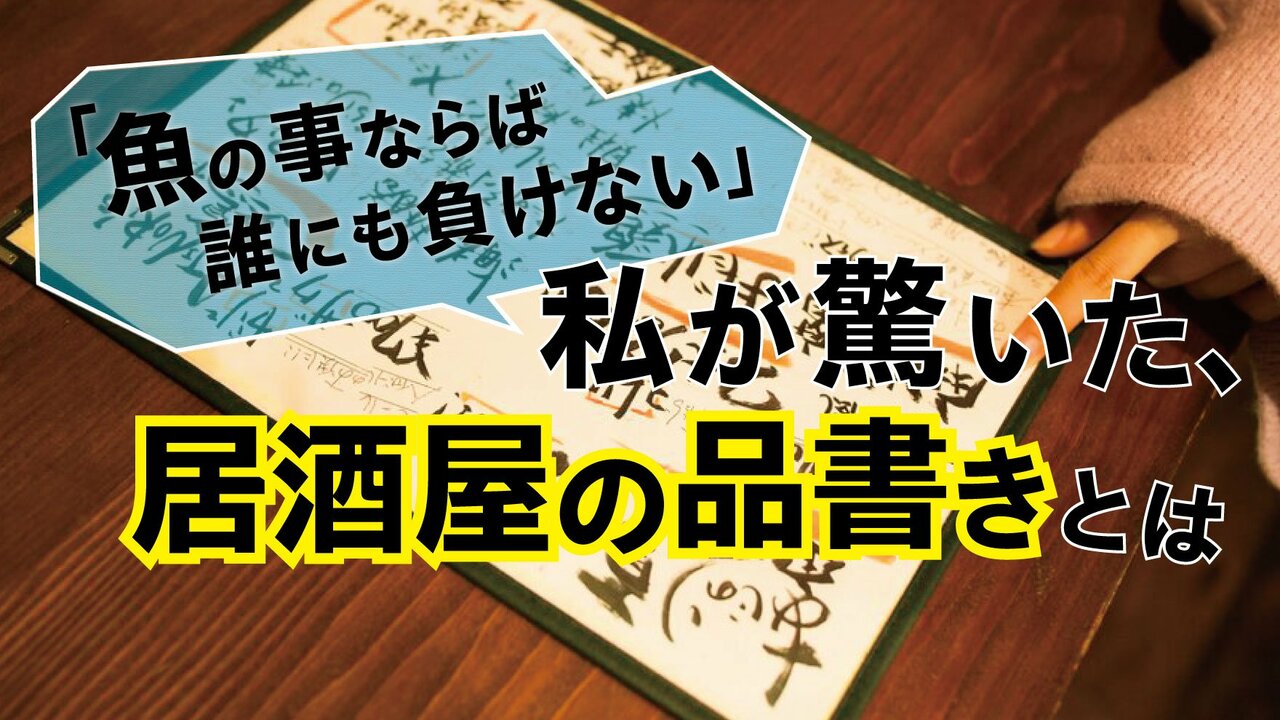第二章 西日本
一 大阪
一九六五年、関西系総合商社に入社した私の赴任地は大阪であった。北海道の田舎に育った私にとって、当時世界中に店を構え輸出入・国内販売に活躍し急成長を遂げていた商社はまさに第二の新世界であった。
配属された部署の課長はデュッセルドルフから戻って来たばかりの仕事には厳しい商社マンであったがすぐにわかったことは無類の酒好きだったことである。また、課員は酒よりはむしろ麻雀が好きな人たちであり、退社時間が来ると課長の酒の誘いをかい潜って梅田駅前右手にあった終戦後に建てたと思われるボロビルの二階の雀荘に逃げ込むことに苦心していた。
そのような課に私が飛び込んだものだから、課長から声が掛かるのは早かった。入社二日目に、帰り道が同じ北の方向(梅田)だからと理由をつけて梅田駅ガード下に居並ぶ屋台のおでん屋に連れて行かれたのである。道産子は足が短いが力が強い否、酒が強いのはいかほどのものかと揶揄されながら誘われたが、酒は北の地で鍛え上げた私である。敵うわけがない。
魚をこよなく好む私にとっておでんは余り歓迎されなかったが、ただ酒だからまずは我慢した。ふと見るとおでん鍋の中に小さなタコが入っていたのでそれを入れてくれと頼み、出されたタコを見てびっくりした。何とそのタコは子供なのに卵をはらんでいるではないか。食べてみると不思議な歯ごたえと味がして意外と旨い。
「課長、内地のタコは子供なのに卵をはらんでいて旨いですね」
と言うと課長は面白いことを言う奴だと言い、聞き耳を立てていた関西の止まり木族の叔父さん方と一緒に大笑いされてしまった。
数ある商社の中で神戸、尼鉄、中山、鹿島などミルメーカーに膨大な売り上げ実績を持っていた部署の課長である。接待費はごまんとあると豪語されてそのあとは北新地の高級クラブのはしご酒となったのは自然のなりゆきであった。
一緒に飲んでくれる相手ができたと喜んだ課長であったが、それを聞いた実家から間もなく会社宛てに大きな段ボール箱が届いた。私の席の横に置かれた箱から通常、会社には無い生臭いにおいを発している。私には中身はシシャモであることがすぐにわかったが課長は君、それは何かねと不快気に聞く。
どうせ関西の人にはシシャモなどわからないであろうと思いながらも、「酒にどんぴしゃりの旨い干物が入っている」と答えると、今宵は誰を道づれにしようかと物色していた課長は急に相好を崩して「千賀ちゃん、今晩今橋寮空いているか、酒置いてあるか」と矢継ぎ早に指示が飛びその夜は急遽課の宴会となってしまった。
ちなみに千賀ちゃんとは、どぎつい河内弁で時たま電話を掛けてくる取引先の社長の怖い電話を優しく代わってくれる課のお姉様であった。私には英語や関西弁に慣れる前に怖い言葉があったのだ。同じ日本人でありながら相手の言葉がわからない恐怖を初めて知った。