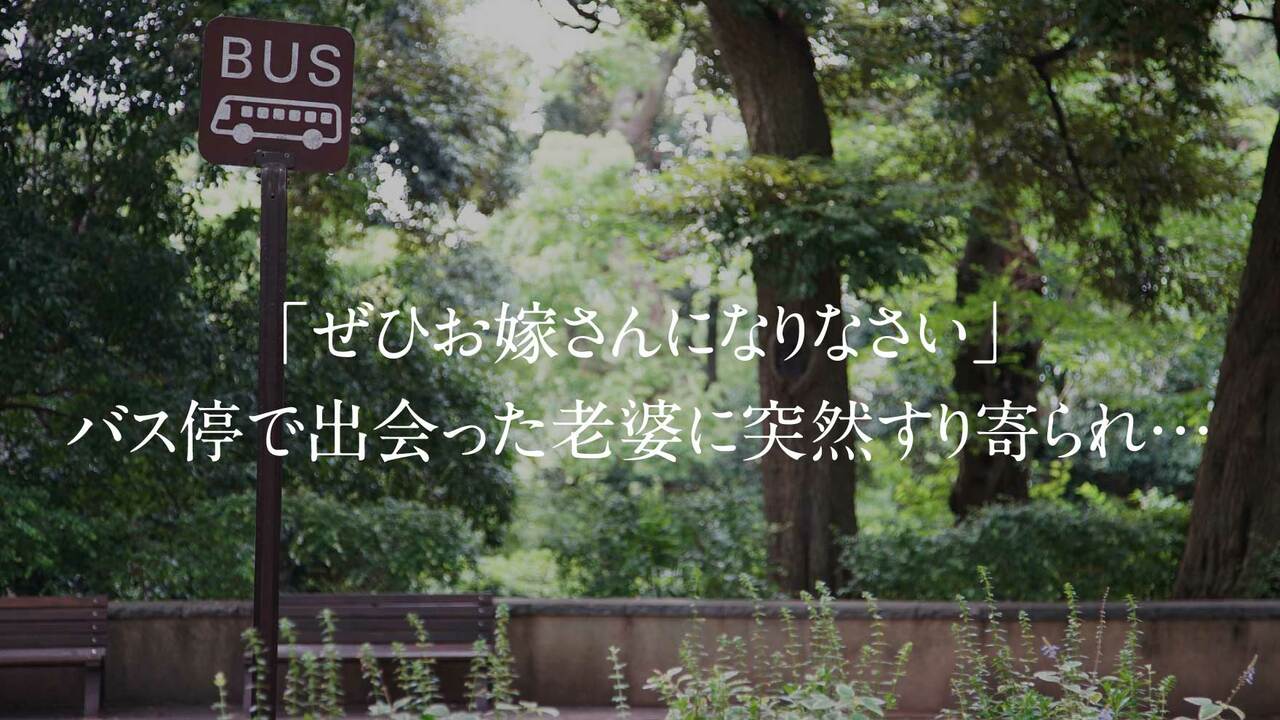第四章 運命に導かれ
小さな宗教
大谷大学には宗教を勉強するために入学したはずだったのに、和辻哲郎の『古寺巡礼』を片手に、京都・奈良の寺々の仏像を見歩いたり、焼き物や絵を観ることに夢中になったりしていた。
『古寺巡礼』は、若い私にいにしえの都にどれほど美しいものが存在するかを教えてくれた。授業もよくさぼった。
朝起きて唐招提寺に行きたいと思えば、私の足は大学ではなく唐招提寺に向かっていた。雲一つない青空の中で眺めた、金堂と太い柱の列はかけがえのない思い出であり、秋篠寺で出会った伎芸天の目を見張る美しさも忘れられない。なぜか親鸞には心が向かなかった。
でも思い出は二つある。一つ目は、大学の階段の所で、『歎異抄』で有名な金子大栄先生とすれ違ったことがあった。
着物に袴姿で杖をつかれていたが、偉大な仏教学者が放たれる独特のオーラに目を見張ったことがあった。
二つ目は、京都市伏見区日野にある法界寺に阿弥陀如来坐像を見に行ったことがあった。
歴史家の研究によると、親鸞は藤原家の末流の日野有範の子どもとなっている。本尊は薬師如来(秘仏)である。秋の午後の時間、私は一人で庭の風情を楽しんだり、阿弥陀堂で過ごしたことがあった。
平安時代の定朝作の、宇治の平等院の阿弥陀如来も荘厳で、魅力にあふれた仏様でよく通ったが、さっぱりとした清楚な感じのする建物にも親しみを感じ、私は長い時間、のんびりと阿弥陀堂での時間を楽しんだ。
当時の日野は、『方丈記』の著者、鴨長明が日野山の草庵に住んでいたのを彷彿させるような心寂しい所で、京都市内に戻るには、一時間に一回程度のバスを利用するしかなかった。
夕暮れ近く、バス停のベンチに座っていると、一人の老婆がやって来て、「こんな所で何しているの」と尋ねられたことがあった。法界寺に阿弥陀如来坐像を見に来たことを告げると、
「貴女のような若い娘が仏像に関心を持つことは珍しい。ここの住職は今、お嫁さんを探しているからぜひ貴女がなりなさい」
などと言って、私にピタリと体をすり寄せてきたのである。身元不明の小娘に向かって、変なことを言う老婆だと気味が悪かったが、本気で説得しているようにも思えた。
弱々しい夕陽は落ち、辺りに闇が漂い始めた頃だった。私が体を離すと、またすり寄って来て、
「ぜひお嫁さんになりなさい」
と繰り返すのである。ベンチはそう長くはない。時間にしてどのくらいだったのだろうか。バスがやって来た時は、得体の知れない不思議な呪縛から解放されたような気分を味わった。後に、『芸術新潮』の編集長だった山崎省三氏の書かれた文章を拝読して、私のこの日の出来事となぜか重なった。
「青はヨーロッパ中世のマリアが着ていた衣の青、ジョットやピエロ・ディラ・フランチェスカの空、十七世紀フェルメールの青い空気、ゴッホが描く夜空や教会のガラス窓に映える空の青に通じ、背後に何か人間を超えるものが潜んでいる青なんですね。単なる空の青じゃない青。日本でも東大寺のお水取りで読み上げられる過去帳に、ずーっと実名が並んでいる中にたった一つ『青衣の女人』という無明の名前があります。きっと霊なんでしょう」
確かに私は青に魅せられてきたし、これらの画家たちも皆好きである。そして「青衣の女人」と老婆が重なるのである。
あの日の出来事は、不思議な老婆に出会っただけでは片づけることのできない、そんな思いを私の心に残した。ただそれだけのことであるが、霊的記憶というものが存在するようにも思えた。