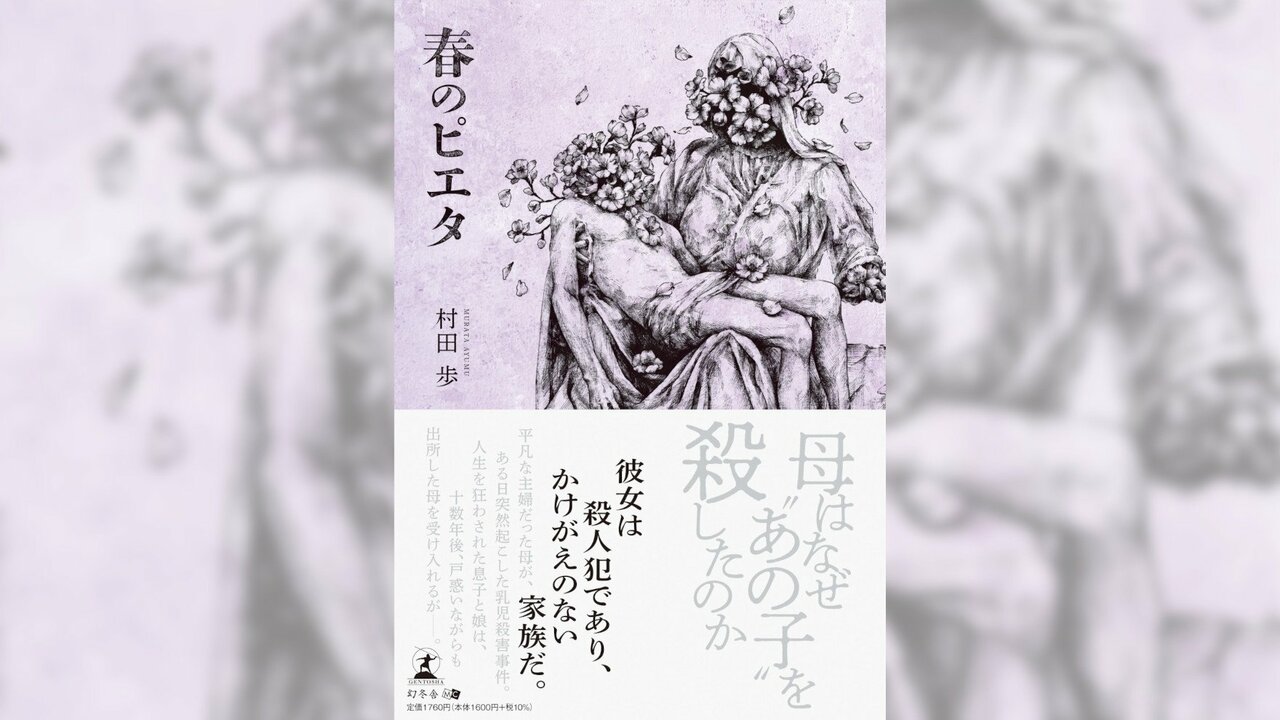優子 ―夏―
「早い時間ならお客さんはいないと思ってたのに、本当にすみません」
「ああ、いいのよ。若旦那は特別なの。昼の三時には仕事終わっちゃう人だから。それにわたしのお客じゃないしね」
意外に屈託のない話し方であたしに座るように促すと、自分も隣に座り、長い手を伸ばした。
「ちょっと、あそこの神林さんのバランタインで一杯作って」バーテンの男性に命令する。こういうお店は経営者の次に偉いのはホステスさんなのだろうか。佳香さんの身体からは意外なことに香水の匂いがまったくしなかった。正面から見たのより横顔の方がずっといい。これもまた意外なことだが、こんなに色っぽいのに、なんだか男の人といるみたいな感じがした。
「あの、あたし保育所に子供を預けていて、あんまり時間がないので単刀直入にお願いするのですが……」
「何時に迎えに行くって言ってあるの?」
「え?」
「何時にお迎え?」
「ええっと、遅くとも八時半までには必ず迎えに行くって言ってあります」
「お住まいは劉生の実家の近く?」
「ええ、歩ける距離です」
「だったらそんなに急ぐことないじゃないの」
長い脚を組み替えて、佳香さんはロックグラスを手に取った。「ミックスナッツも頂戴、若旦那の付けでいいから」
「はい」
ああ、なんと気持ちいいまでに主従のはっきりした世界! あたしも一度でいいからこんなふうに低い声で男の人に命令してみたい。佳香さんは貧乏ゆすりをしながら黙っている。貧乏ゆすりがこんなにかっこよく見えるなんて。