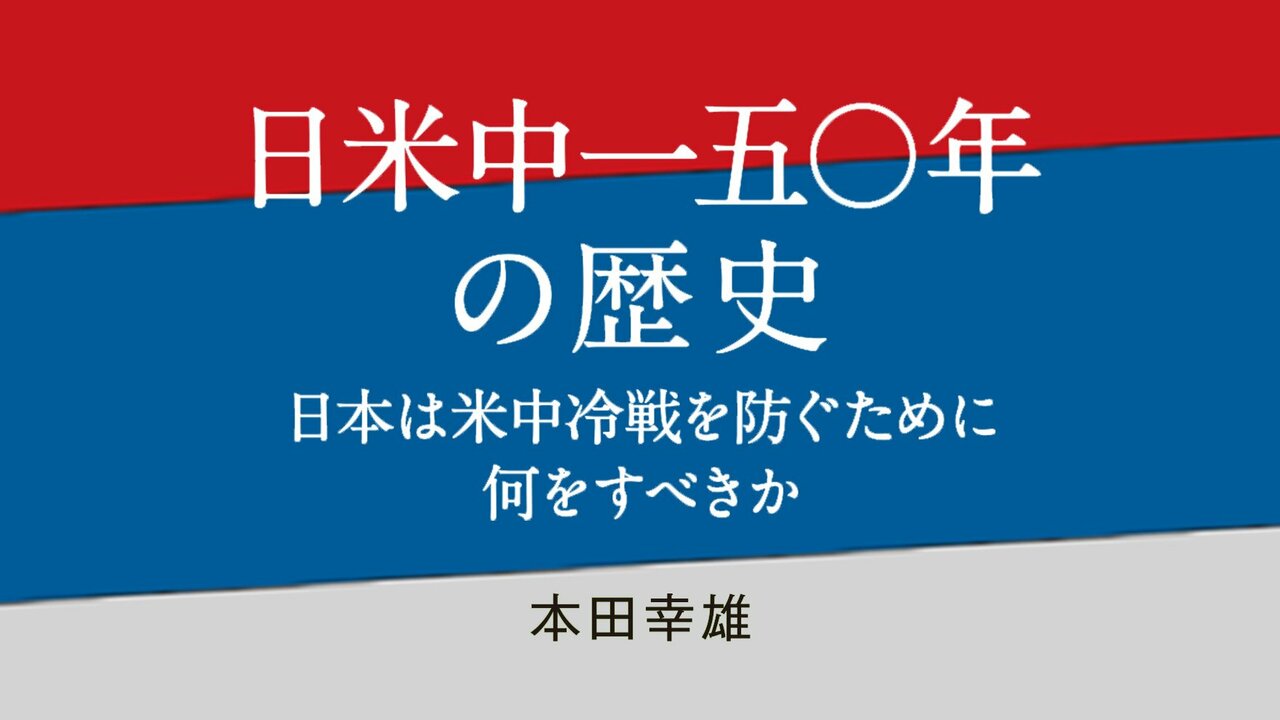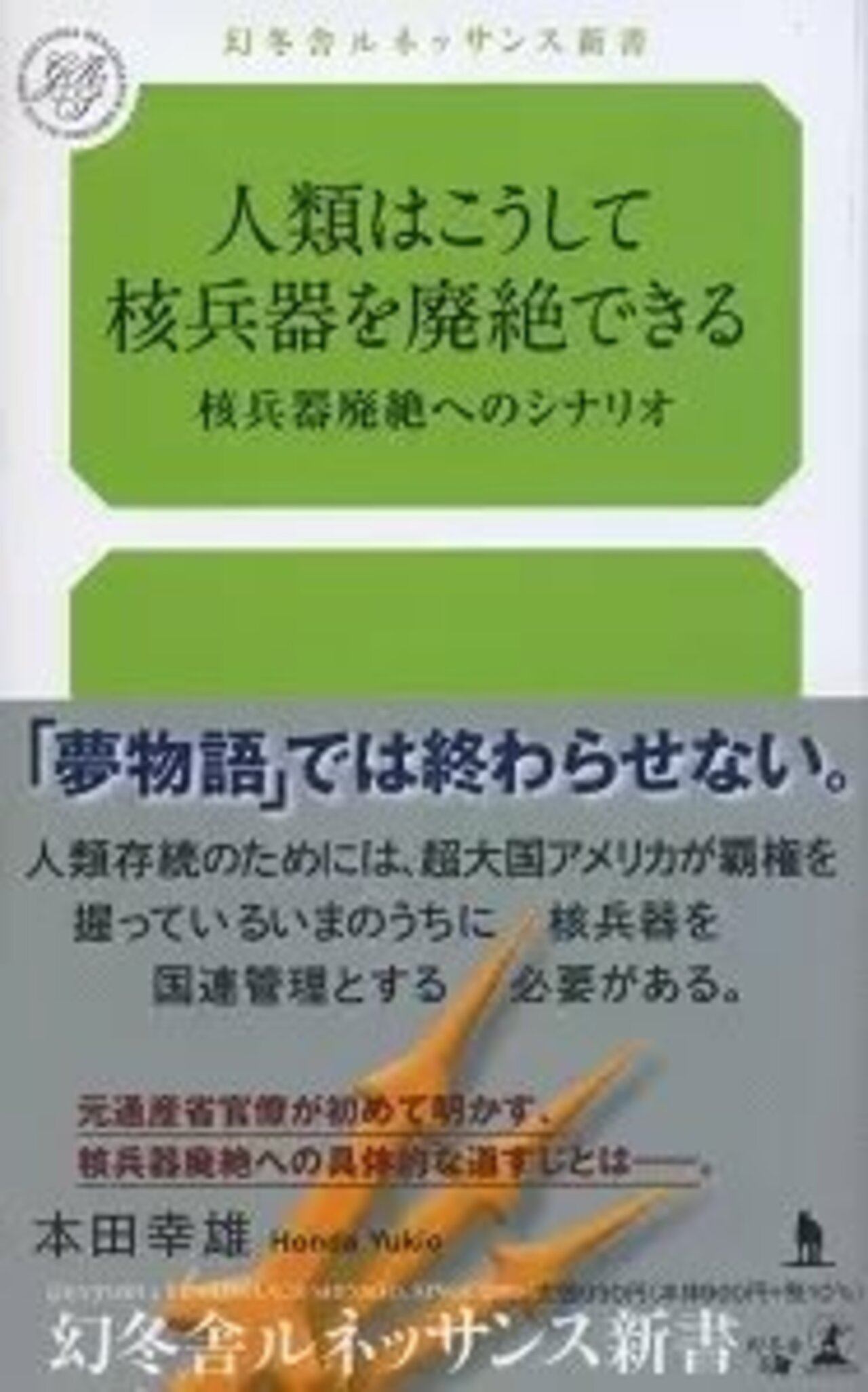【前回の記事を読む】第二次アヘン戦争でイギリス政府が「武力行使」に至ったワケ
第一章 第一次世界大戦までの日米中
清国の改革・洋務運動
清国においても、ヨーロッパ近代文明の科学技術を導入することで改革を進め、中国の富国強兵をはかろうとしました。これを洋務運動と言いました。
清朝の高級官僚であった曽国藩・李鴻章・左宗棠・劉銘伝・張之洞らがこの運動の推進者となり、一八六〇年代より西洋技術、とりわけ軍事技術を導入した近代化が推進され、清朝の国力増強がはかられました。ヨーロッパの近代軍備を自前でまかなうために、武器製造廠や造船廠が各地に設置されました。
他にも、電報局・製紙廠・製鉄廠・輪船局や、陸海軍学校・西洋書籍翻訳局などが新設されました。次いで、運輸・通信・鉱業や繊維工業の発展など富国策がとられました。これらの諸事業の経営は官営のものが多く、民間における資本主義的な発展はあまりみられませんでした(日本の富国強兵・殖産興業も初期は官営でしたが、のちに民間に払い下げられ民営中心に転換されました)。
このように中国の洋務派の改革は、時期の早さでも規模の大きさでも日本の明治維新に勝っていましたが、日本の場合と異なって、成果が上がりませんでした。
その一つは、生産管理方式は清国の官僚主義に基づく旧式の管理方法で、加えて生産された品は政府だけが使用するため採算は度外視されていたことなどが上げられています。こうした軍事工場から利潤はほとんど得られず、施設を維持・拡大し生産を継続するための資本を蓄積することができませんでした。つまり、経済・経営がわかる人材・官僚がいなかったのです。
また、西太后を中心とする清国政府の洋務派官僚と日本の明治維新政府の官僚とでは、モラルの点でも大きな差があったと指摘されています。近代化されたはずの清国の軍隊でしたが、清仏戦争(一八八四~八五年)と日清戦争(一八九四~九五年)に敗れて、その弱体ぶりを暴露し、洋務運動の失敗が証明されました。この結果、欧米列強の中国進出が再び活発化していきました。
ロシアの南下政策
清国が第二次アヘン戦争や太平天国の乱に苦しんでいる状況を見てロシアは東アジアでも南下政策を推進し始めました。一八五八年五月に中国北東部、アムール川中流のアイグン(現黒竜江省黒河市)において清朝と愛琿条約を結びました。
この条約によって、ネルチンスク条約(一六八九年。これは対等な条約で、満洲での国境を黒竜江・外興安嶺の線に定めました)以来の国境(外興安嶺)は南へ大きく下げられ、アムール川が国境とされました。つまり、ロシアはアムール川以北の広大な土地を圧力によって獲得しました。
次いで、ロシアは、一八六〇年の北京条約で、愛琿条約では両国の共同管理地とされていたウスリー江以東の土地を清国から獲得し沿海州とし、ウラジオストック軍港という念願だった不凍港の建設に着手しました。