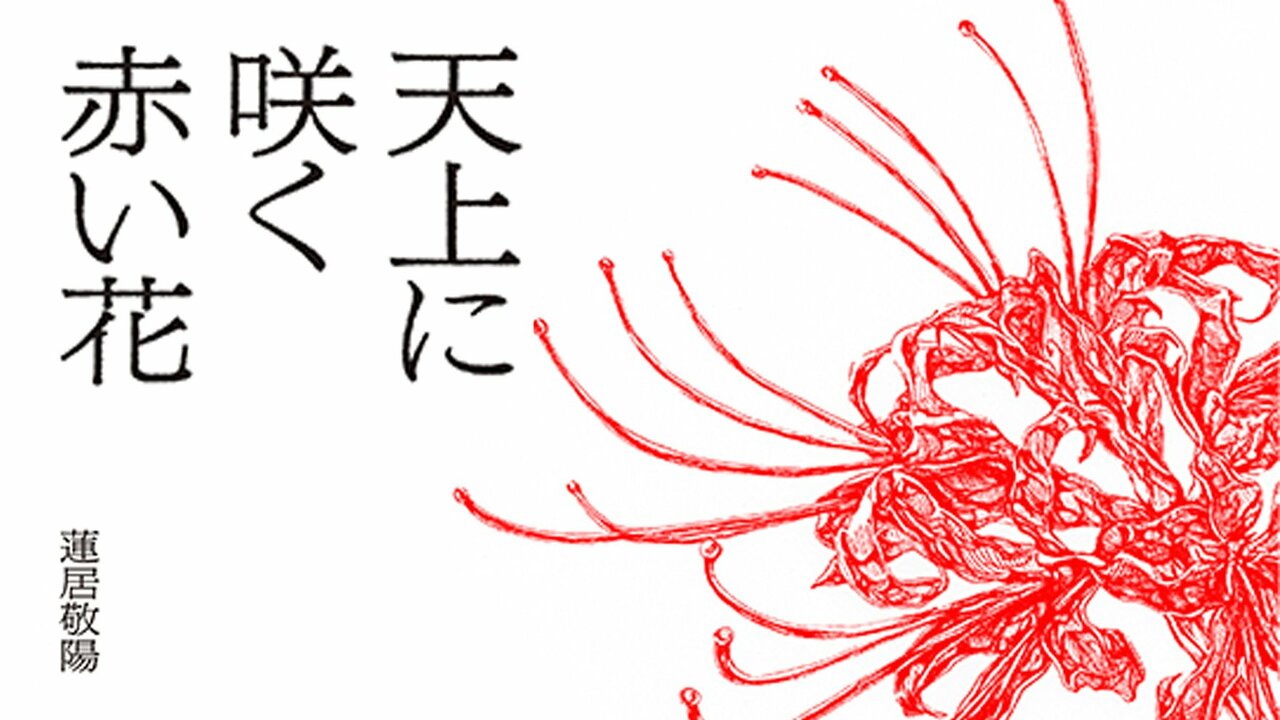【前回の記事を読む】【小説】夫からの暴力に涙する娘…「仲直り」を勧めた母の愛情
一部 事件発生と、幼なじみの刑事とお巡りさん
二〇〇五年九月
被害者の氏名は中原純子さん(五三)。彼女が居間でうつ伏せになって倒れているのを発見したのは、夫の悠矢さん。紐状のものを使って首を絞められたと考えられる。女性は十九日午後九時前に救急車で市民病院に運び込まれたが、意識不明の重体である。以上が、事件が起きた日から二日後の、九月二十一日の朝刊の西播版に載った記事である。
その同じ日(九月二十一日)の夜に、北村大輔は高倉豊と会っていた。いつもは数年置きに、決まって八月だった。二人共警察官だったし、北村大輔の母親の弟は中原悠矢だったので、話題は当然彼の叔父の妻である、中原純子の事件のことになった。
北村大輔は、純子叔母さんのことが好きではなかった。具体的に何か嫌なことをされたり言われたりしたということはなかったのだが、彼女の大輔を見る目は冷たく、人間的な温かさを感じ取ることが出来なかった。それは彼が幼少の頃から現在に至るまで、ずっと続いていた。
それでいて北村大輔の両親の居る前では、中原純子は無理に作った笑顔をこちらに向けて、優しそうな叔母を演じている。だがそんなときの彼女には、一段と心の冷たさを感じてしまう。そのような態度をそのときどきで上手に使い分ける中原純子を、北村大輔はくだらない人間だと思っていた。そんな彼女をどうして好きになれるだろう。
「お気の毒というより他ない」と言う高倉豊に対して、北村大輔は「あまり好きではなかったので、辛くはないです」と率直に話した。
「辛辣やな」
「もちろん死ななくてよかったとは思ってますけど」
「正直な奴やな。私もそれに倣って言わせてもらうなら、親類縁者の中に犯人が居ると捜査本部は考えているようや。家の中に上がらせて煎茶を出していることから、或る程度親しい人間だったことは間違いない」
「新聞で読みました」
「彼岸花が居間のテーブルに置かれていたことは知らんやろ」
「彼岸花? 何故そんなものが」
「さあ、それはこれからや。彼岸花の球根にはアルカロイドとかいう毒物が含まれとって、有毒植物ということになるようや」
「いや、知らんかったな、それは」
「俺もや。この事件で初めて知ったんや」
「豊君も、僕の親戚を疑っているんですか」
「いや、少し気になるだけや。それにトラブルということでなら、中原夫妻の娘と現在離婚調停中の夫、村上功太が居るし、彼の母親の家に中原純子が怒鳴り込んでいる」
「は?怒鳴り込むって……」
「何ヶ月後かに生まれてくる子供の争奪戦や。どちらも親権を主張している」
「大変なことになってたんですね」
「問題なのは、暴力を振るうような男に子供は渡さないと、中原純子が村上功太の母親を罵倒したことや」
「功太君がひとみちゃんを殴ったってことですか。そりゃあ駄目だ」
「しかし、娘の結婚相手に言うんじゃなく、母親に言うのは筋違いってもんやろう」
「父親は居ないんですか。その、ひとみちゃんの夫の父親は。済みません。従姉妹の結婚相手なのに何も知らなくて」
「亡くなっている」
「そうだったんですね。じゃあ功太君だったり、母親が……」
「もちろん捜査の枠の中には居る。ただし、本格的な捜査はこれからや。明日ようやく捜査本部設置や。市職員の夫が保健センター勤務の妻を殺害して逮捕した事件から、一ヶ月後に起きた事件だからか、県警の動きは鈍いな。でももちろんやる気がない訳ではないんや。その証拠に、先に私を赤穂署に送り込んでいる訳やから。ただ大輔には悪いんやが、十数年振りに赤穂に捜査本部が出来た殺しで犯人を逮捕して、捜査本部が解散してから一ヶ月しか経っていないというのがなあ」