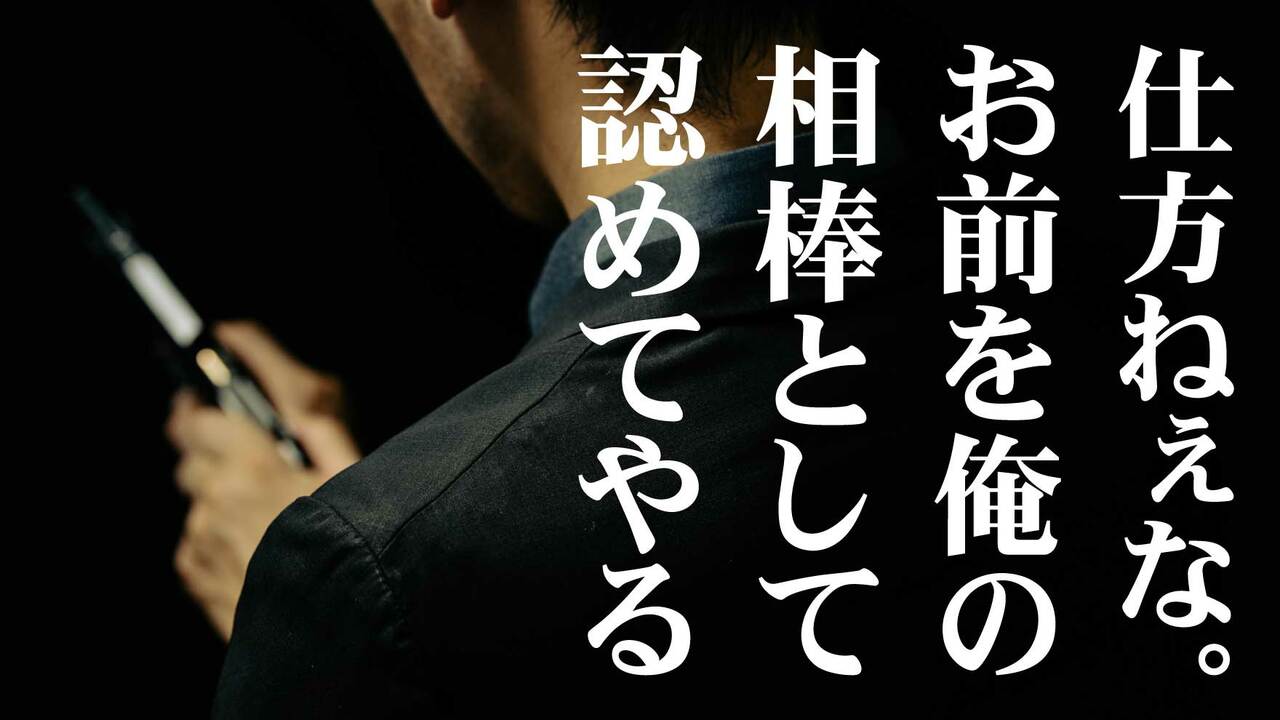恭子は戸惑った。このままでは、永遠にラットの生命を奪い続ける事になるかもしれない。
「待って。私、どうしたら良いか解らないの!」
恭子は女性に訴えた。女性は、少し困ったような顔をして言った。
「……すみません。答えは自分で見つけるしかありません……」
女性の口調は優しいが、発した言葉は冷たい。しかし、女性の言う事は正論だった。自分の能力のコントロール方法がどうして他人に解るだろう。自分自身でさえ判らないのに。
それにさっきのラットの場合、命までは奪っていないと思う。ラットに異変が起きた瞬間に接触を止めたから、死ぬまでは至っていないはずだ。何より、身体から魂を引き剥がす、あの感触を感じていない。そう、殺さなければいいんだ。
思案の末、両手を机の上に差し出す。その瞬間、机から金属の塊が出現し、恭子の指と手首を拘束された。
「え?」
恭子は掌を上に向けた状態で、上体を拘束された。女性がラットを乗せてきた。
「え、ちょっと待って。……い、嫌!」
掌にラットが乗せられる。ラットから熱の流入が始まった。
「嫌ああああ!!」
部屋に、恭子の悲鳴が木霊した。
その夜、恭子はベッドの中で泣いた。
一体、何匹のラットの命を奪ったのだろう。勿論努力はした。目を閉じ、心を落ち着かせよう、感情を殺そう、と努力した。しかし、ラットが息絶える度に悲しみが溢れ、涙がこぼれ落ちた。もう、能力のコントロール方法などどうでもいいから、逃げ出したかった。それを拘束具が邪魔した。
解放されたのは、涙が涸れ果てた頃だった。
帰りの車中、魂が抜け落ちたような恭子に恵比寿顔は言った。
「手荒な事をして申し訳ありませんでした。――しかし普通のやり方をしては訓練になりませんので……」
恭子は答えなかった。
車中の他の人間は、疲労で何も考えられなくなったのだと思っただろう。恭子は悲しみと共に、常人と異なる能力を持つ自分を呪っていた。車中でも、何時もの場所で車を降りて夜道を歩いているときも、それから家に帰ってからも、この能力をどうすべきかを考えていた。
自分の部屋のベッドに俯せになり、手に残る冷たいラットの感触を思い出すと涙が溢れ出てきた。訓練を止める。能力をコントロールする事は諦め、一生生物に触れない人生を送る。その選択肢が自分にはある。明日、あの場所に行かなければいい。
恭子の涙は涸れる事無く、夜は更けていった。