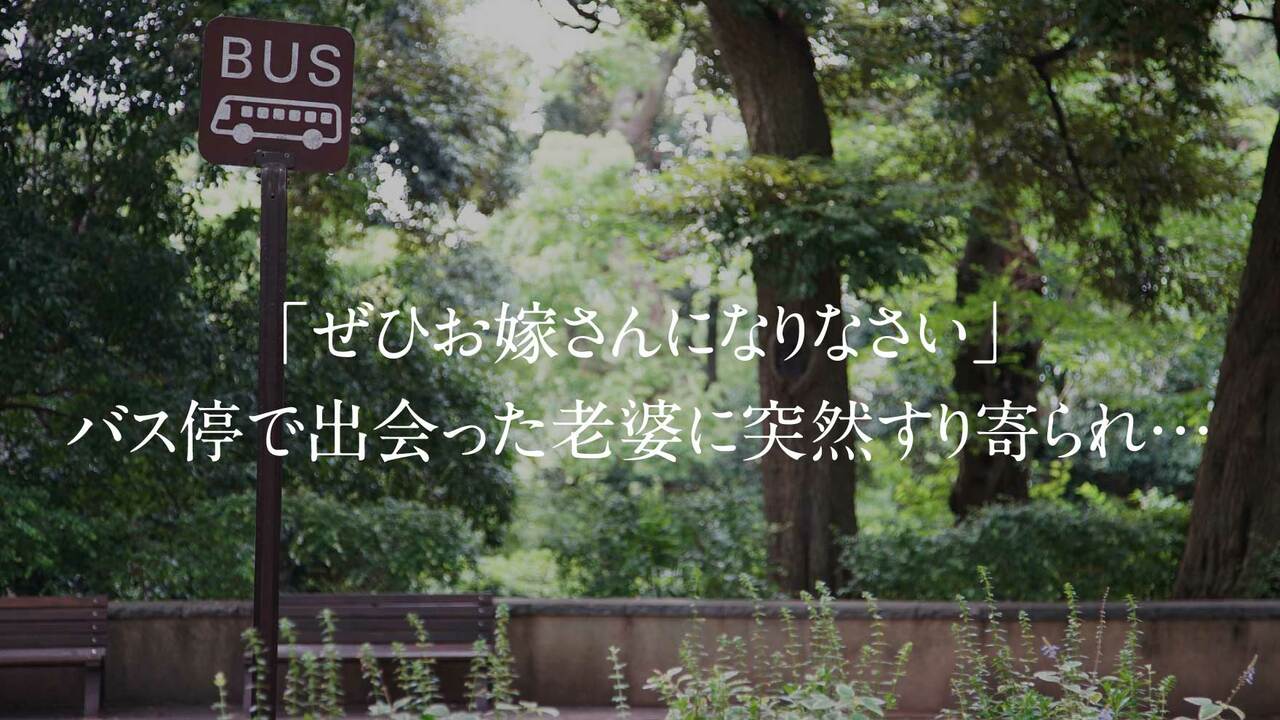森有正――星と月と悲しみ
私の朝は早い。大抵午前三時には起きている。今年は暑い夏だと思っていたのに、過ぎてしまえば一夏はあっという間で、中秋の名月も終わり会津地方はもうすっかり秋の気配である。つい最近、聴きたいCDが車の中にあることに気づき、外に出た時驚いた。空にこんなにたくさんの星が輝いていたなんてと。こんな時、目が潤むのは、今年は大切な友だちを三人も亡くしたせいなのだろうか。会いたいと思った。
その日から星と月を眺めるのが大切な日課になり、亡き友だちと語り合う時間になった。死者たちは、有り難いことに、それぞれ私にかけがえのない思い出と言葉を残してくれた。
今日は、少し早く起きてしまった。午前二時半。きっと快晴になるのだろう。白い楕円のような形をした雲がたくさん浮かんでいて、その中を月が結構な速さで移行している。月が光を放つ所だけ、まるでフェルメールの「手紙を読む青衣の女」のようなブルーの色が現れ、素晴しく神秘的で、あの女性が出現したような錯覚を起こしそうだった。
つい最近、一冊の本に出会い、私の中で小さな事件が起きている。
片山恭一著『どこへ向かって死ぬか――森有正と生きまどう私たち』
森有正は、大好きな辻邦生の本の中に登場する程度の人だったのに、冒頭からこんな文章が飛び込んできて、私を狼狽させている。
「孤独、絶望、死、これらは決して悲壮がかった脅し文句ではないのだ。人間の魂のカリテ(質)なのだ。どうしても、そこに行かなければ、先に向かってひらけないものがあるのだ」
「僕たちは、人間が幾億人いようとも、自分であって、絶対他の人とは、置き換えられない人間にならなければならない。僕はこの人間存在の極限に追い詰められたことを喜び、また悲しむ。この人生においては、こういう自覚は必ず不幸と苦しみとを招きよせるからだ。人間とは、まず悲しみなのだ」『バビロンの流れのほとりにて』
なぜだろう。ページはその先には進まない。