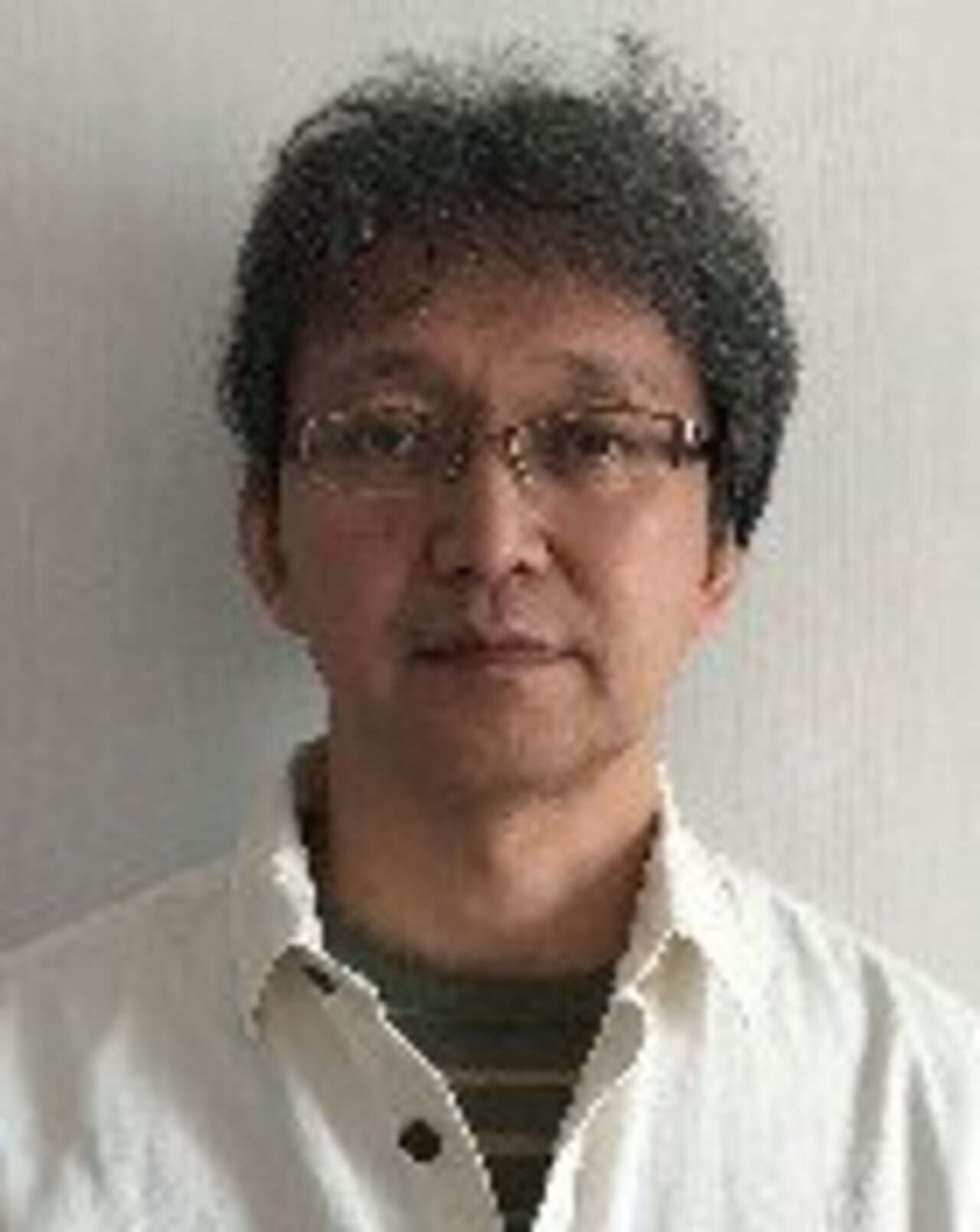廉は病院スタッフの懇切な応対と、何より和枝自身のしっかりした動きに「これは必ずうまくいく」と感じていた。病室に戻った和枝が、朝、遥から渡された紙袋をベッドの上で開けた。尻尾に「K」のイニシャルが付いた折り鶴、布や毛糸で手作りしたお人形、遥が幼い頃から夜は肌身離さず抱いていた安眠グッズ。そして「ママ、ファイト!」と書かれた手紙が出てきた。和枝は手紙の文字を追い、その安眠グッズであるくしゃくしゃの毛布カバーの切れ端を抱きしめながら、振り絞るように泣いた。
夕方、和枝と廉は本館一階の喫茶室に寄った。一杯のコーヒーとオレンジケーキを二人で分け合った。
「じゃ、よろしくお願いします、廉」
「和枝に負けないように、遥と暮らしていかないと」
「そうよー、ちゃんと暮らすのよ」。
和枝の笑顔が眩しかった。
病院からの帰路は圏央道、下道とも大渋滞に引っかかり、通常四十五分のところをたっぷり二時間かかった。家では和枝の姉の真咲と、その娘で大学生の綾が掃除やキッチンの片付けまでやってくれ、遥と一緒に晩ご飯も済ませてくれていた。気が付くと和枝からメールが入っていた。
「きょうはありがとう。あのあと高井先生が来て、今日の検査はすべて結果良好ですって。じゃあ店じまいします。おやすみね~」
廉は翌日から特別に休暇をもらうことになっていた。一週間前、平林家に持ち上がった一連の出来事を、廉が所属長の時村編集長に報告したところ、「仕事のことはおいおい考えましょう。とにかくすぐに全力で奥さんのサポートに入ってください」と即答されたのだった。管理職としてはどこまで許可を出せるか、部内の要員状況を勘案する時間が必要なはずだ。でも時村さんはとにかく即答してくれた。しかも真っ先に妻の病状を案じて。廉には、人の言葉としてそのありがたさが心に沁みた。