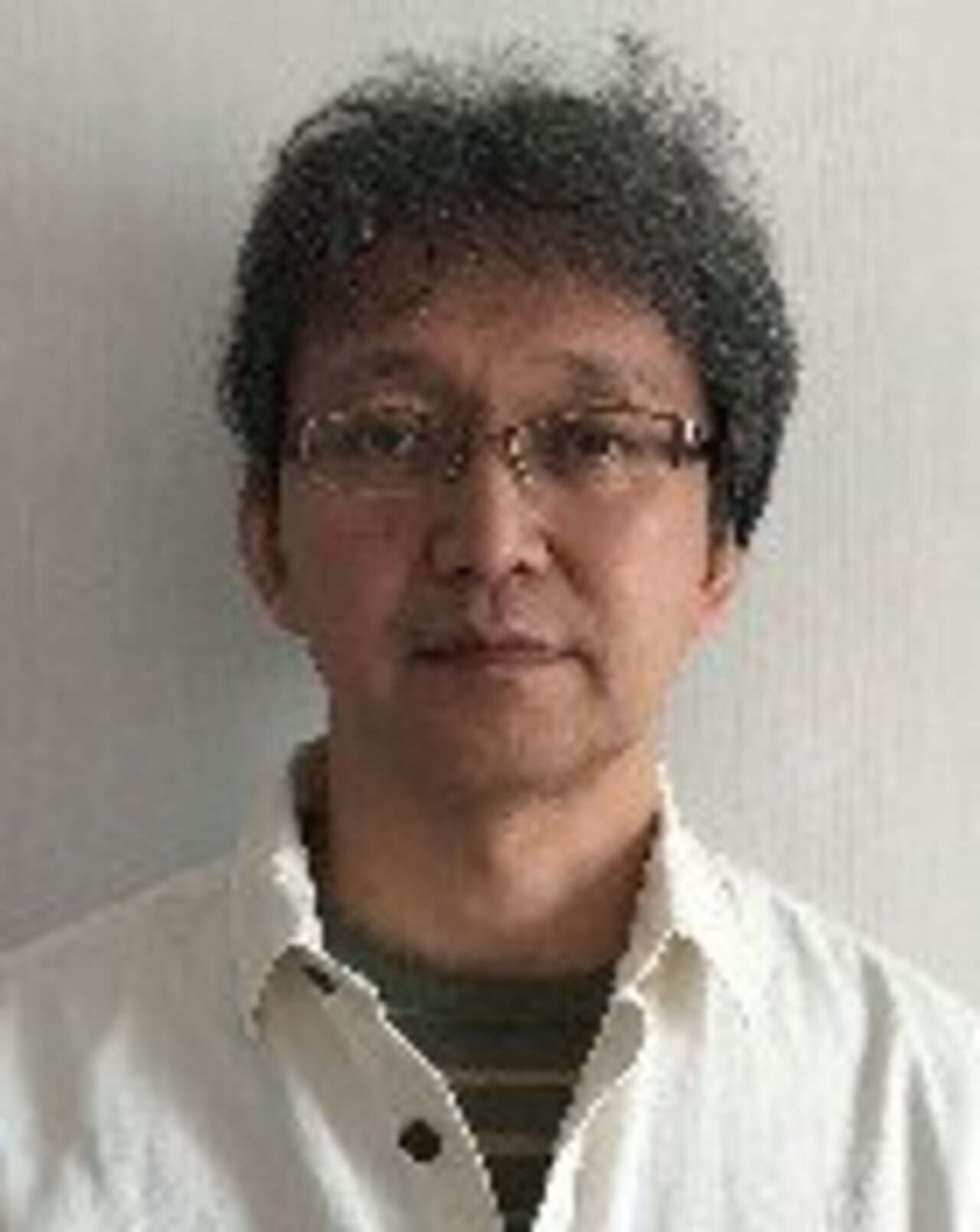【前回の記事を読む】「余命はあまり長くはないかと」医師からの突然の宣告に絶望
突然の医師からの電話に出ると…
和枝にはもうひとつ、入院の前にやらなければならないことがあった。
ピアノの生徒さんを手放すのだ。治療が長期にわたるかもしれないのでやむを得なかった。
「毎週通ってきてくれて、みんなここまで弾けるようになったんだよ」
廉にぶつけるしかない心の叫びだった。
未就学児から八十歳まで十五人。
身を切られる思いだったろう。生徒さんやその親御さんもどんな気持ちで和枝の決断を受け止めたことだろう。
八十歳の女性は「和枝先生のお宅まで、歩いて行き帰りできるかどうかが私の健康の物差しです」と言いつつ、毎週、杖をつきながら善行駅からの坂を上り下りしていた。
今後もピアノを続けたいという生徒さんがほとんどで、和枝自身が次の先生を紹介し、きちんと申し送りをしていた。
お別れのレッスンは三日間に及んだ。
最終日は、四国に接近した台風の余波で荒れ模様の天気になった。
いつもだったら和枝が玄関ドアを開けると「ヤッホー」「先生、いまアイス食べながら来たの」「お暑うございます」と生徒、親御さんそれぞれの挨拶に始まり、がやがや談笑しながら二階のレッスン室に入っていくのだが、この日は来る人来る人、皆やや緊張した面持ちで無言のまま階段を上がっていった。
最後はショパンのワルツに取り組んでいた小学四年の女の子だった。音が鳴りやみ、女の子は母親と階段を下りてきた。和枝と玄関でしんみり別れの挨拶を交わし、目を泣きはらした二人が、うつむいて私道を歩いていくのが見えた。がっくり肩を落とし和枝がリビングに入ってきた。
「今のは夏帆ちゃんだよね。いくつの時から教えていたんだっけ」
廉が聞いた。
「年少さんからよ。そうねえ、小さい子のレッスンは特に楽しかったな。『♪シラシミレーミーシラシミレーミー』なんて一緒に歌いながら弾くこと、もうしばらくないのね」
遥については、親子の間のレッスンがだんだん難しくなり、小学四年の時から、和枝の音大の先輩に当たる白銀彩先生に教えていただいていたので、ピアノに関しては状況が変わることはなかった。