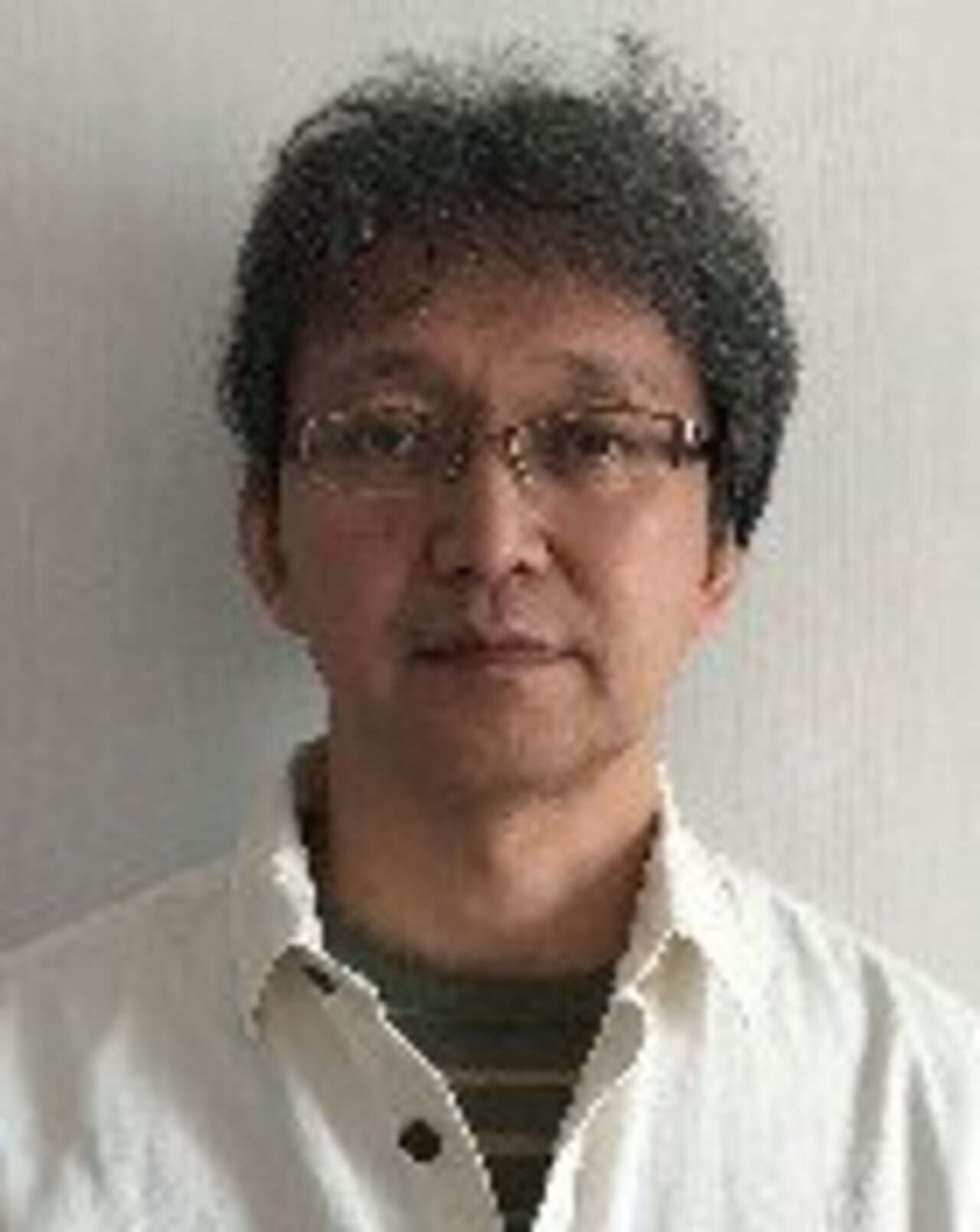重たい質問
七月二十四日、和枝がK大学病院に入院する。
フローリングの床にシャンプー、リンス、石鹼のボトルがまとめて置かれ、新しい歯磨きセットは半透明のケースに朝の陽を吸い込んでいた。あとは浴用タオルが三枚にバスタオル二枚、肌着、靴下、替えのスウェット、ドライヤー。
さっきからダイニングテーブルに頰杖をついたまま、廉は床に広がるそれらを、ただぼんやり見ていた。支度が進んでいく光景に刻一刻ダメージを深めていき、眼球を動かす気力さえ失われていた。
和枝は長い脚でひょいと品々をひと跨ぎし、廉の左肩に手を添え、支えにしながらタオルの前にきちんと座り直す。そして廉の顔をちらっと見てから、丁寧にたたみ始めた。
和枝の表情や身のこなしには病気を感じさせる不穏な陰は微塵も見えず、それが却って廉の顔を曇らせた。
「心配するなよ」。和枝が少しむっとしながらもおどけた調子で長い静寂を破った。和枝の膝の前の品々にはすべて「ひらばやしかずえ」とマジックで書かれていた。
「私の貴重品、廉のバッグに預けま~す」
和枝からK大病院の診察券と入院のしおりが手渡された。
「これを家族旅行の朝の準備と思って乗り切ろう」
という、先刻からの廉のむなしいあがきもここでぷっつり断ち切られた。病院へは二人のドライブとなった。遥は幼なじみで中学同窓の愛絵ちゃん、静那ちゃんと、気晴らしに湘南テラスモールのシネコンに出かけるというので、それを見送ってから家を出た。
遥は「ママ、じゃあまたね」と笑顔だったが、「ママ」と「入院」を結びつけ、現実として受け入れることがどうしてもうまく出来ないでいた。
この時は、和枝が好きな「ゆず」のCDをかけなかったので、エアコンの送風音だけが車内を満たす。湘南藤沢バイパスはスムーズに流れ、雲一つない碧空には蒼い富士山がくっきり浮かんでいた。
「何もかも順調に運ばなくたっていい。急ぎたくもないんだから」
言わなくてもいい廉の呟きを、和枝のため息が飲み込む。
圏央道・茅ケ崎中央ICのETCゲートが跳ね上がった瞬間、何かのスタートを暗示されたみたいに感じた廉は、いちいちうるさい自分の感情のざわつきに、とことんうんざりしていた。
左車線で八十キロをキープしながら、入院する日というのはこんな感じだったと、廉は自分の少年時代を思い出していた。