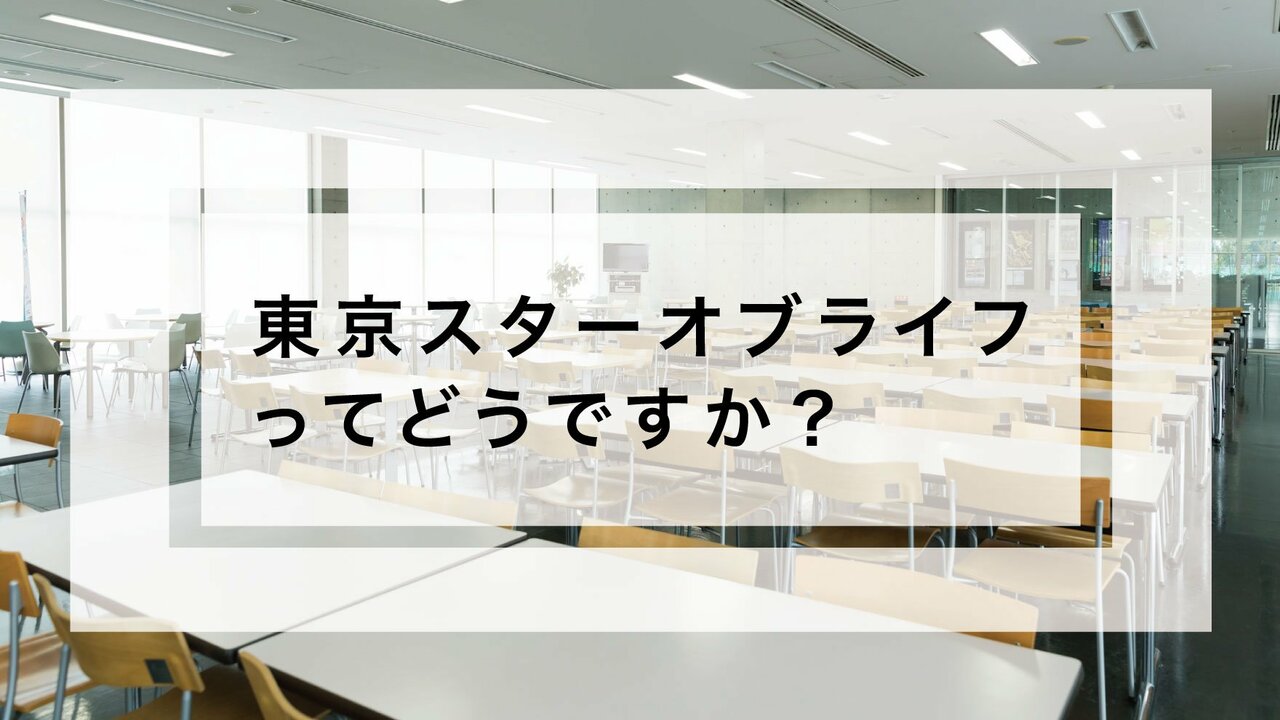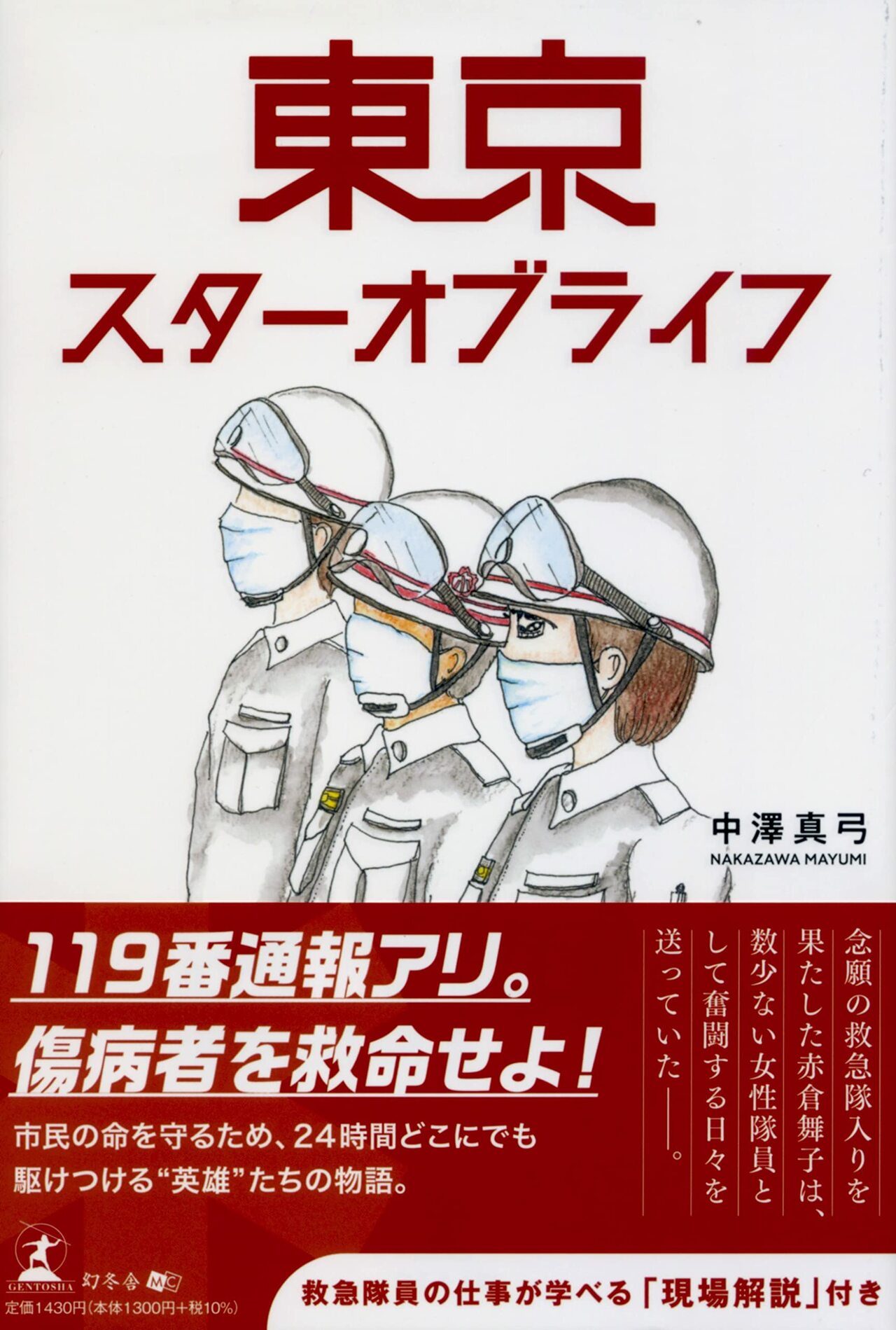【前回の記事を読む】全国で女性はわずか2%…舞子が救急隊員を志した理由とは
紅一点
「あれ? 今日、水上くん補欠?」
総務課の女性事務員、玉原が署長室の来客の湯呑を片付けに食堂に入ってきた。災害現場に出場する消防吏員とは違い、事務職員は主事といわれ、署員の福利厚生や経理などの仕事をしている。
「玉原さん、お久しぶりです」
容姿端麗な水上が笑顔で挨拶をすると、玉原も嬉しさを隠し切れない。
「お会いできて嬉しいわ」
水上は見るからに「好青年」オーラが漂っている。四十代の玉原主事は、すっかり水上青年のファンになっていた。玉原だけでなく、年に一回開催される消防署対抗の剣道大会では、水上は女性職員や出入りの保険屋の黄色い声援を浴びている。出張所では食事当番の腕前も評判がいいらしく、出張所員から「料理男子」と呼ばれて重宝されているという噂だった。舞子は、玉原主事とにこやかに話している水上を見て、自分に対する態度の冷たさを感じていた。
「では、取材はこれで終わりにしましょう、来月号の『救急女子』特集、楽しみだな」
記者が広報課に取材完了の電話を入れ、引き揚げていった。「料理男子」に「救急女子」……。それだけではない。女医・女性警察官・女弁護士……男とは、女とは、こういうものであるという認識に反する職業に就いているだけで、好奇な目で見られる。舞子は食事当番用のエプロンを外した。
女性だから、特別扱いをされているわけではないと信じている。水上より先に正隊員になったのは、厚生労働大臣が認めた「救急救命士」の免許を持っているからだ。
「あのー、水上さんて、私のこと嫌ってません?」
食事当番の後片付けを終えて事務室に戻ってきた舞子は、救急係のデスクで入力作業を行っていた菅平と岩原に尋ねてみた。当の水上は、体力錬成室で若手の隊員たちと筋トレをやっているらしい。
「何を言い出すかと思ったら……」
「お、さては、あのイケメン料理男子を狙ってんの?」
「いや、そんなことは、まーったくないですけど。なんか、とげとげしいというか……私に対して」
「やっぱり、ライバルなんだろうね」
菅平が救急活動記録票をファイルに挟みながら言った。現在、夜八時。今日の分だけで、もう八件分の活動記録票が束になっている。
「彼はね、小さいころにご両親を交通事故で亡くしたとかで……その時の救急隊員の姿を見て、消防官になったんだったかな。でも、やっと救急隊員の研修を終えて念願の救急隊員になれるかと思ったら、救急救命士の免許持ちの君が配属されてきた」
「しかも、数少ない女性救急隊員として、チヤホヤされている」
「岩原さん、私、チヤホヤなんてされてないですよ……。むしろ、チヤホヤされているのは、水上さんの方だと思いますよ。イケメンとか、料理男子とか言われて」
「いや、周りにはそう見えるってことだよ。水上だって、若いとはいえ、もう何年も救急隊員になりたくて、この前の人事異動を待っていたんだ。面白くないんじゃないの? それに、水上も、ルックスじゃなくて実力でお前に勝ちたいと思っているはずだ」