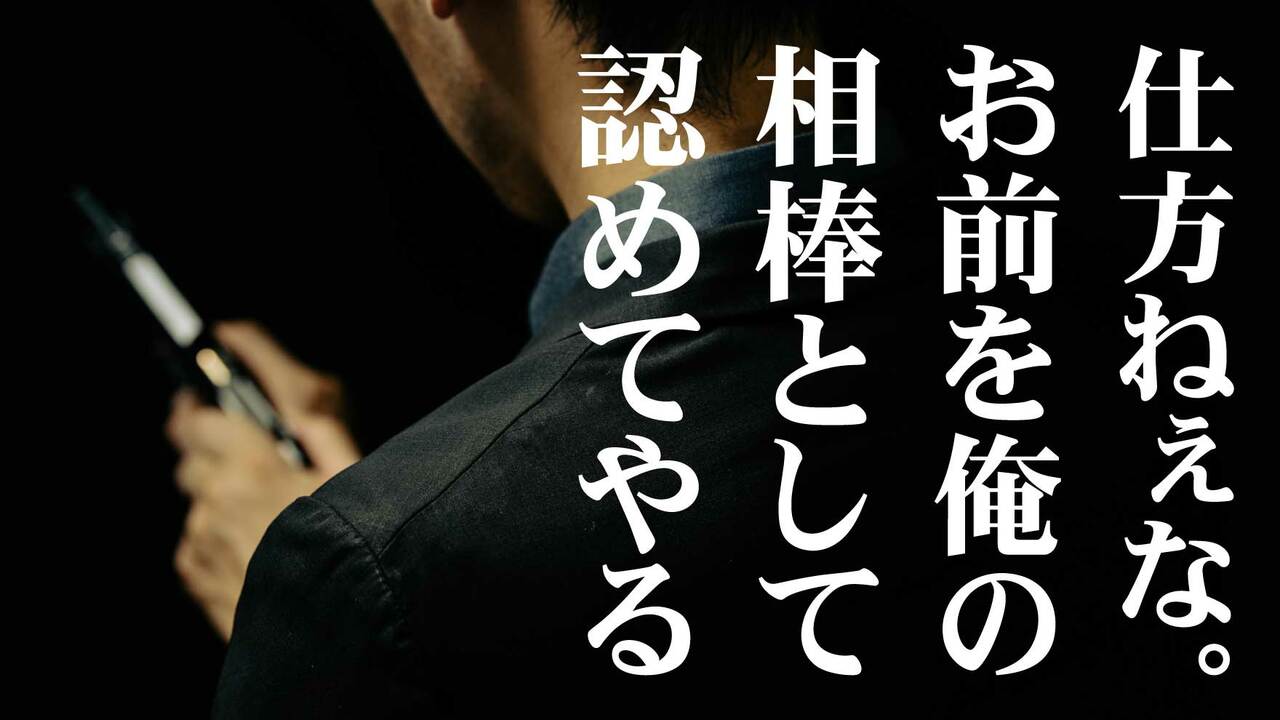【前回の記事を読む】【小説】呆然とする少女。祖母の命を奪った人物は紛れもなく…
第二章 恭子
祖母の葬儀が終わり、恭子は自分の部屋の机の前に座っていた。
通夜の席でも、葬儀の間も、火葬場でも。恭子は泣きもせず、一言も発せず、ずっと放心状態だった。
祖母の命を奪ったのは自分だ、などとは誰にも話せない。
後悔の念だけが、恭子を包んでいた。
それは、決して晴れる事の無い、トラウマとなった。
自分には命を奪う力があるのか。それも掌から。
祖母はそれを知っていたのか。
そうでなければ、恭子の手袋を自ら外し、手を握る事などしないはずだ。
もしかすると、祖母も同じ能力を持っていたのではないのか。だから恭子に手袋を与え、幼い頃から生命の大事さや怒りの抑制を教えていたのでは?
幼い頃……?
あの昆虫達も、実は私が命を奪っていた?
しかし祖母は、私に普通に触れていた。何かこの力をコントロールする方法があるはずだ。死の間際、祖母は「感情をコントロールしろ」と言った。あれはどういう事なのだろう。
恭子は机に飾ってある花瓶から、一輪の花を抜き取った。
花を見つめながらふと、病室での祖母の顔が思い出された。
そして手から流れ込んできた祖母の光と熱。
あの流れ込んできた「何か」が祖母の生命だったのだ。
改めて後悔の念が沸き立つと共に鼓動が激しくなり、目頭が熱くなる。
すると――。
恭子は目を瞠った。掴んだ花に変化が生じていた。
花がみるみる恭子の手の中で萎れていく。
恭子はその萎びていく様を凝視した。
あれは、現実だった。
自分には生物の生命を奪う能力がある。
祖母の命を吸い取った忌むべき能力。
恐ろしいその力の存在と犯した罪の事実に、恭子は机に俯せ泣き崩れた。
何故、私にこんな力があるの?
おばあちゃんはそれを知っていながら、何故あの時まで黙っていたの?もっと早く教えてくれていれば、その対処法も教えてもらえたかもしれないのに。
だが、祖母はもうこの世にはいない。この秘密を隠して、これから自分は生きていかねばならないのだ。
絶望と不安で、涙は止まる事がなかった。
翌日、恭子は学校へ登校した。
嫌だったが、休む理由が無い。
手袋を決して外さない事を心に誓い、学校へと向かった。
幸い、素手が直接相手の素肌に触れなければ、力が発動する事は無いようだ。祖母が伝えた唯一の対策方法。それを恭子は昨夜寝ずに確認を行ってみた。
しかし、不安が消えたわけでは無かった。この恐ろしい能力を隠し続けて生活を送る事が出来るのか。そんな不安を抱きつつ、恭子は校門をくぐった。出来るだけ、いや、絶対に誰にも触れないようにしよう。