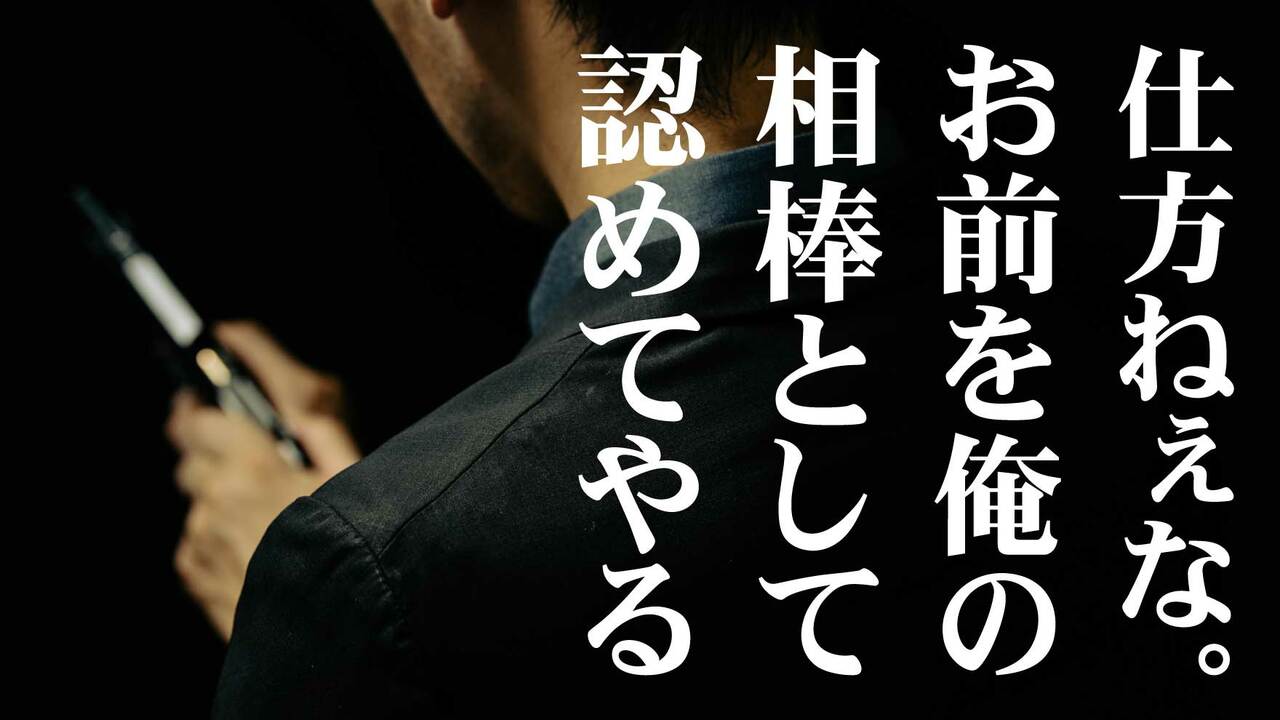【前回の記事を読む】「楽にしておくれ」往生際の祖母の願いに恭子がとった行動は…
第二章 恭子
その時だった。
祖母は恭子の手袋をゆっくりと剥ぎ取り、手を握り直した。
恭子はそれをじっと見つめていた。
握りしめた祖母の冷たい手が、次第に暖かみを増す。
恭子は最初、祖母の手が自分の体温を奪って温かくなったのだと思った。しかし、その熱の広がりは収まらず、手首から肘へと広がった。
皮膚の表面ではない。
筋肉が。
骨が。
それ自体が熱を帯びているのだ。
そして握った掌から、二人が何かの光源を掴んでいるかのように、掌を透かす程の眩さの光が溢れ出してきた。と、同時に「何か」が恭子に流れ込んできた。
恭子の掌の細胞の隙間に、粘度を持った光が、ざわざわと這うように侵入して来る。
しかしそれは、何か祖母の大事なモノを奪うような気がして、思わず握りしめた掌を離そうとした。
が、次の瞬間、祖母は病人とは思えない力で、恭子の掌を握り返してきた。思わず恭子が目を向けると、祖母は優しく見つめていた。
「いいんだよ、恭子。全身の痛みが消えていく……。こんな幸せな事は無い……」
祖母の掌から流れ込んで来る「何か」は、次第に暖かさを増してきた。
「恭子……、お前にはある力がある……。ハア……ハア……早く言うべきじゃった。恭子、感情をコントロールするんじゃ……」
恭子は頭が混乱し、祖母の言っている事が理解出来なかった。
「力を、世の人のために使うんじゃぞ……。それがお前の使命じゃ……」
掌の光度が増してゆき、恭子の腕までが光を帯びる。
流れ込んで来る「何か」は、恭子の身体に溶け込み、一体化していく。
「おばあちゃん!?」
祖母は幸せそうな顔をして、瞳を閉じた。光が、ゆっくりと消えていく。
祖母の身体から、全ての力が抜け落ち、握っていた手が恭子の手から滑り落ちた。
もう、荒い呼吸もしていない。
「おばあちゃん……?」
祖母は幸せそうな顔を浮かべ、ベッドに横たわっている。胸に耳を当ててみるが、鼓動が聞こえない。呼吸する胸の上下動も無い。
祖母を呆然と見つめた。
祖母は死んでいる。
只の心肺停止ではない。恭子だけは判った。