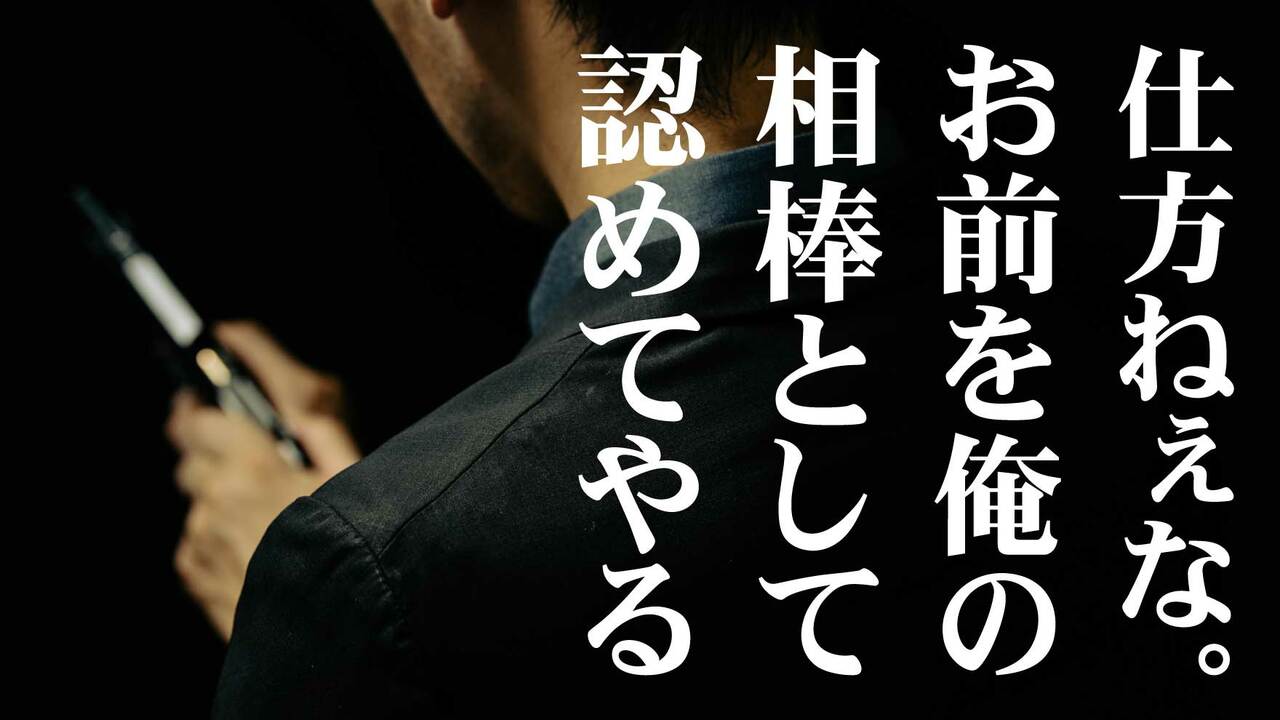生命が消えて無くなった事が確信出来ていた。祖母の生命は尽きたのだ。それが判るのでナースコールも押さなかった。そして、祖母の死は寿命などではない。私に、祖母の命は奪われた。そんな事をしたのが自分だという事も、時間が経過するにつれ実感できた。祖母が私に受け渡したのでは無く、私が、祖母の命を「吸い取った」のだ。
今、祖母の命を、私は奪った。
昔おばあちゃんが言った「それ」ってもしかして……。
恭子は、恐ろしい一つの回答を導き出した。
もしかして私には、他人の生命を吸い取る能力がある?
おばあちゃんは私の能力を知っていた?
幼い頃私に禁じたその力を、祖母は己の苦しみから逃れるために使わせた?
何故?
どうして!?
何故そんな酷い事をさせたの? おばあちゃん!?
恭子は祖母が死んだ悲しみと同時に、自分の能力に恐怖を覚え、祖母が何故、自分の死を恭子に背負わせるという惨い行為に及んだのかという思いで胸が苦しくなった。
それは自然と涙となって現れた。
「おばあちゃん!」
まだ温かさの残る祖母の身体を、慟哭しながら激しく揺さぶった。
この力は何?
何故、この能力を使わせたの?
その答えをまだ貰っていなかった。祖母には恭子の疑問に答える義務があるはずだ。
心肺停止をアラームで知った医師や看護師達が病室に入ってきた。
おばあちゃん! と連呼する恭子を、一人の看護師が引き剥がし、医師が祖母の傍らに立つ。すぐに医師は祖母の状態を確認し、看護師に指示を与える。
生き返って欲しい。
この恐ろしい力の事を説明して欲しい。
祖母が全てを知っているはずだ。
それが無理な事は恭子が一番よく知っていた。祖母の生命を奪ったのは自分だからだ。それでも看護師に制止されながら、病室の中でおばあちゃん! と連呼していた。
蘇生処置が始まり、電気ショックの衝撃で祖母の身体が跳ね上がる。
病室には、恭子の叫ぶ声が繰り返し響いていた。