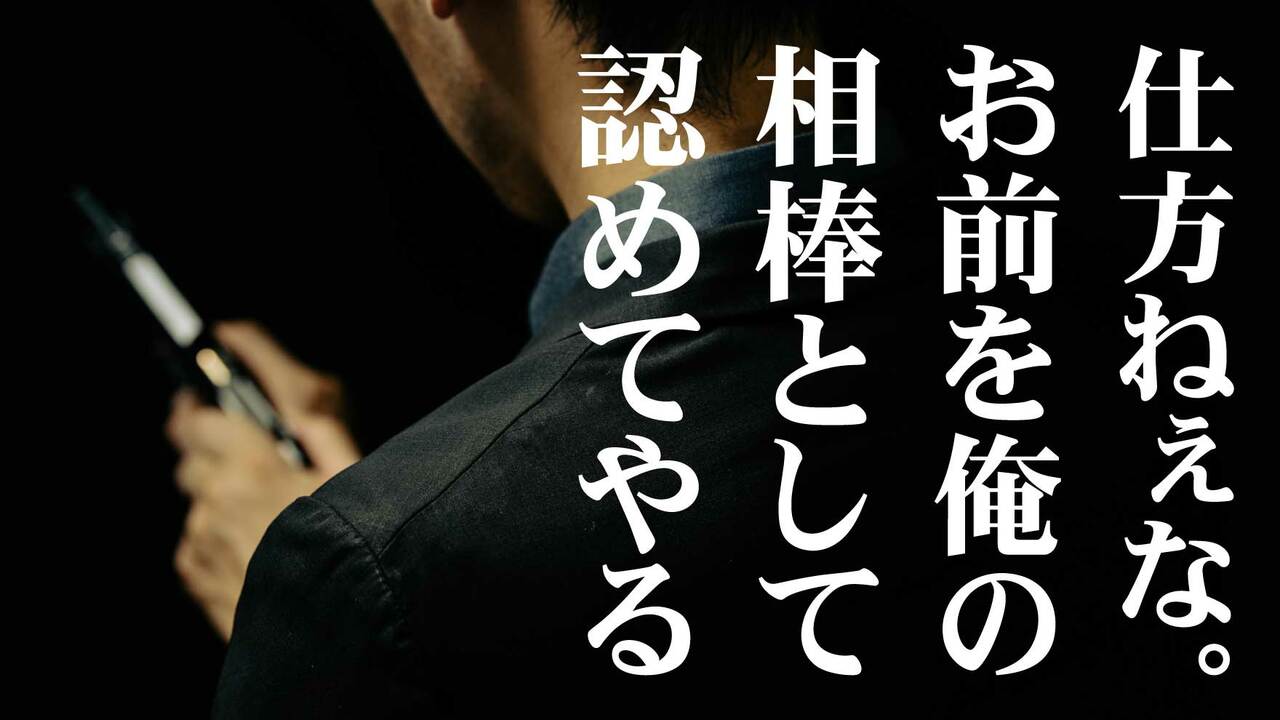そう心に誓い、校舎へと近づいた。
「おはよー、恭子!」
声と共に、自分の肩を叩く者がいた。恭子は身を竦めた。そこには友人の風花が立っていた。
「どうしたのよ、そんな驚いた顔して……」
風花は恭子の顔を覗き込んだ。恭子に触れた風花には何の異変も無い。掌でなければ、さらには布越しなら、他者が触れても大丈夫なようだ。
「いや、別に……」
「へーんなの」
風花は笑顔を浮かべ、並んで歩き始めた。
「恭子、何時も手袋してるのね。暑くない?」
風花は、恭子がしている手袋に話題を変えた。以前から疑問に思っていたようだ。恭子は言い訳を考えて無かった。
「こ、これは、手が荒れてるっていうか……」
「そう、手袋までしなくちゃいけないなんて、酷いのね。大丈夫?」
「だい……じょうぶ……」
恭子は作り笑顔を浮かべた。
「よかった。そうそう、宏美が昨日ねぇ……」
風花とは下駄箱から教室まで、会話しながら歩いた。
もしかすると風花は、祖母を亡くした恭子を元気づけようとしてくれているのかもしれない。休んでいた間の学校の様子を、明るく話してくれた。恭子は緊張が解れていくのが分かった。
今まで通りの生活が出来るかもしれない。手袋を外さなければ、外れても人の皮膚に直接触れなければいいんだ。恭子は少し落ち着いてきた。
風花と二人で教室のドアをくぐる。
「お、伊弉弥恭子」
声の方を見ると、高杉という男子が、教室の入り口で友人の男の子と話をしていた。そして恭子に気付くと、近づいてきた。
そして彼は、恭子の右手の手袋をいきなり剥ぎ取った。
恭子は全く不意を突かれた気分だった。こんなに簡単に手袋を外されるとは思っていなかった。
動悸が激しくなる。
「何だ?お前。何時も手袋なんかしてよ」
高杉君は手袋を目の前にかざした。
「か、返して!」
恭子が伸ばした手を高杉君はひらりとかわし、手袋を頭上へと上げた。
「伊弉弥、お前お嬢様にでもなったつもりかよ」
「返して!」
高杉君は背が高かった。恭子がジャンプしても、手袋には届かなかった。
しかし、手首には届いた。
何度かジャンプした時、恭子の右手の指先が、高杉君の手首に触れた。
バチッ!
静電気が大気を裂くような音がして、高杉君の手から手袋が離れた。
恭子は空中で手袋を受け止め、右手にはめた。
高杉君の方を見ると、彼は白目を剥いていた。
暫く硬直した様に立っていた彼だったが、不意に膝が崩れ、ゆっくりと沈んでいった。そして膝を付き、背後から崩れ落ちた。後頭部が容赦なく床を叩く。
高杉君は昏倒した。
「キャー!」
風花が叫んだ。クラス全員の視線が教室の入り口に集まる。さっきまで高杉君と会話していた男子達が駆け寄った。高杉君は泡を吹いていた。
「おい!保健室だ、保健室!」
数名の男子が駆けつけ、高杉君を保健室に担いでいった。
恭子はそれを、震えながら見送っていた。