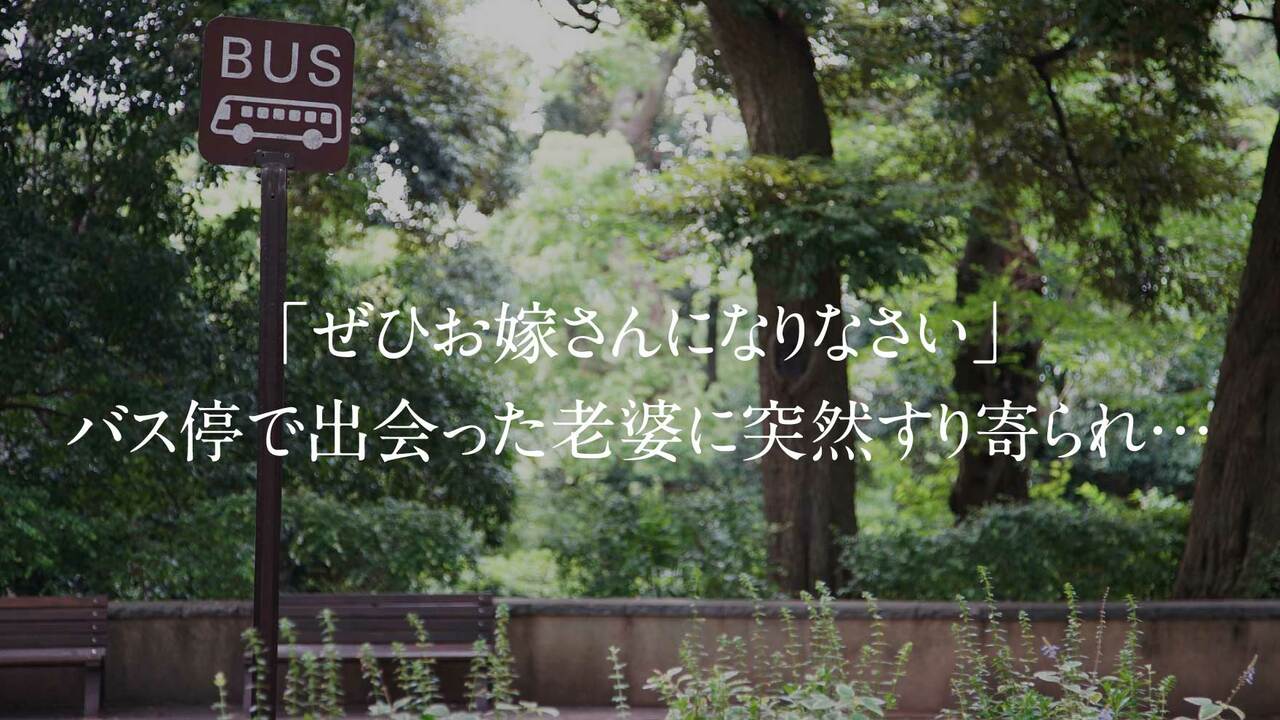この作家は、ヨーロッパの生活を経験され、長い間書く根拠を求めて、かなり苦闘された作家でもある。どこかで、永遠を感じたとも書かれている。『廻廊にて』の最後は、苦難を強いられたマーシャの人生に対してこう綴られている。
「マーシャ、あなたは少なくとも〈あなた〉という見事な作品としてそこにいる。そうなのだ。あなたのような死だけが憐憫を必要としない。死がその宿命を成就するものであるとするなら、私はためらいなく言う、マーシャよ、それはあなたのような死なのだ」と。
この小説は、私に生きることの勇気を与えてくれ、人生を支えた一冊と言っても過言でない出会いになった。辻邦生の処女長編小説であり、第四回近代文学賞を受賞した作品である。
瞬間の中に永遠が開示される世界。『廻廊にて』は芸術が基調となっているが、後に『西行花伝』という、まるで交響曲を奏でるように空観の世界へ、辻文学は大きく結晶していったように思われる。ショートショートに『アネモネ』と題した作品がある。
リルケの『マルテの手記』の一節。「愛する女は、愛される男を、常に凌駕する。なぜなら人生は運命より偉大だからである」を具現化した作品のように思われた。
さだまさしの歌う『舞姫』のような世界。甘美な追憶も人生を美しくすると、私は思った。『夏の砦』も好きな作品で、主人公支倉冬子の幼年期はどこか私に似ているような気がした。
私も案外孤独で、空想好きで、自分勝手で、学校の授業より興味があることが多すぎた。共感できる部分が多く、「二重の性格」「農耕生活や市民生活を信仰にもみちた敬虔なものとして受け取っていた」等や「自分が透明になって、ただ善意なり個性なりが現出するという意味において、私はやはり冬子がアニノム(無名)な存在を目ざしていたのではないかと想う」等の文章が響いてきて、赤い線がたくさん引いてある。
また創作ノートを拝読して、作家と呼ばれる人たちの生き様の凄さを教えられたようにも思えた。後に、師であった森有正の、『廻廊にて』『夏の砦』の書評を拝読し、深い思索にまた感激させられた。
「生きることには、意味がある。死ぬことにも、意味がある。宗教はそれを教える。しかしそれだけでは終わらない。『美』が何かを奏でる。我々の奥の何かが、それに不思議なかたちで呼応する。人間精神の奥があらわとなる」、これはアランの『生きること信じること』の編訳をされた哲学者、神谷幹夫先生の解説の文章である。
私の貧しい理解を許してもらえるなら、辻邦生はこの意味をよく理解していた人だと思う。そして森有正もアランが好きな人だった。こうして、辻邦生は、私にとっていつでも帰っていける作家になった。