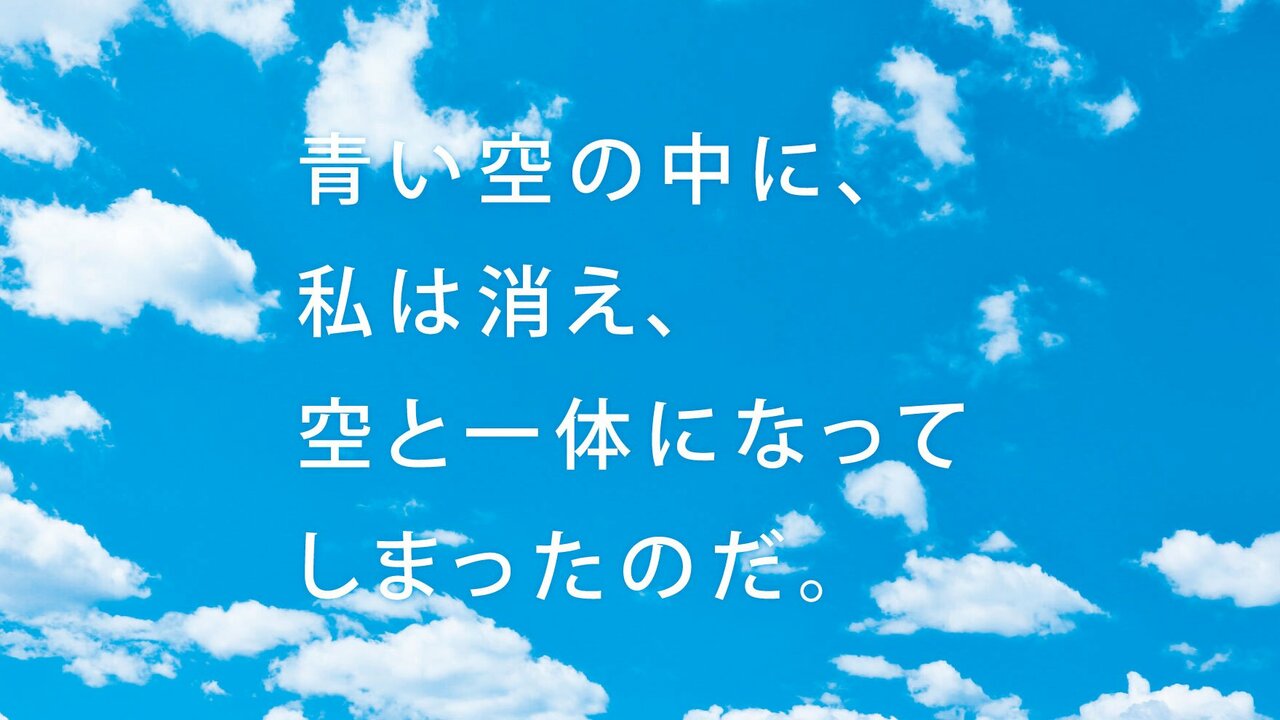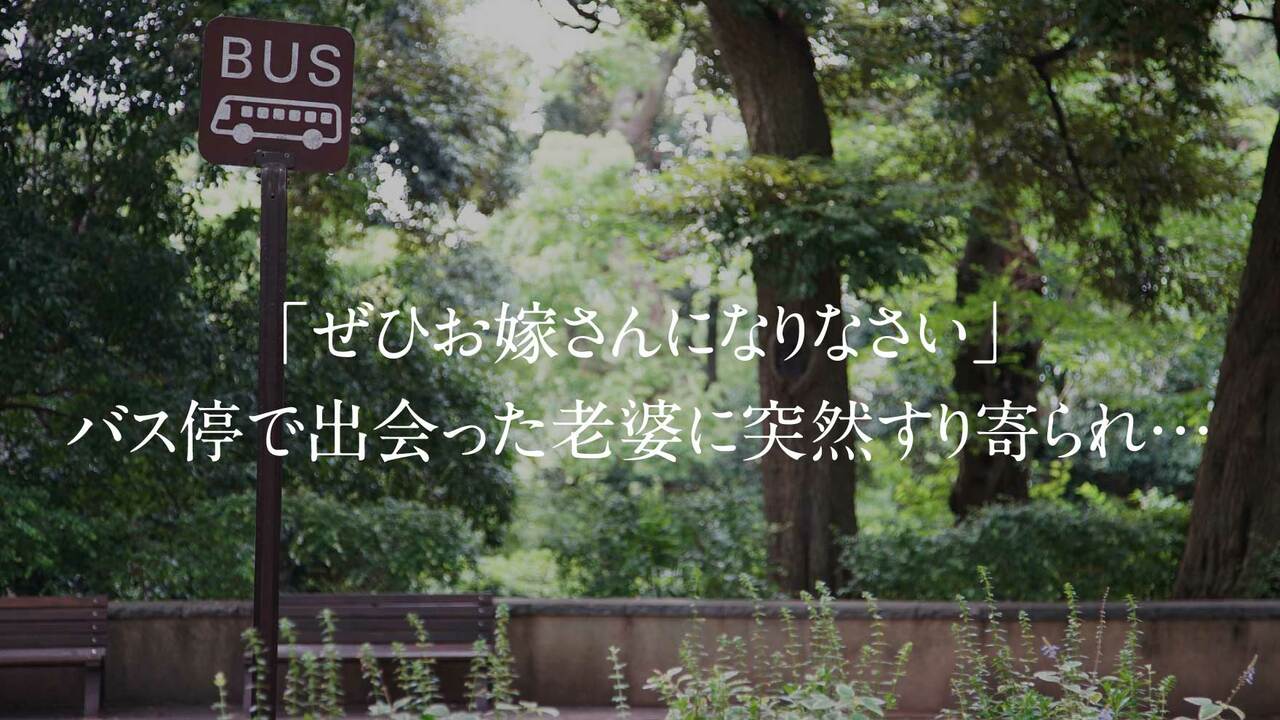【前回の記事を読む】「もう一人産もう」病に悩む女性が命がけの出産を決意したワケ
辻邦生(廻廊にて・他)
私は時々、辻邦生の小説『廻廊にて』を手に取る。この作家は、たとえ苦難を持っていても優しい眼差しで「貴女も憐憫を必要としない、運命にうち勝つ強い意志を持つのですよ」と語りかけてくださる。その心に触れると、また一歩歩いて行こうと思う。
それは、今から二十年近く前の暑い夏の日の出来事だった。当時私は、市内のギャラリーで働いていた。人の流れが途絶えた遅い午後の時間、入り口の日陰になった場所にしゃがみ込んで草むしりを始めたことがあった。しばらくすると腰が痛くなってきて、立ち上がりぼんやりと空を眺めた。汗をぬぐいながら。その時だった。いつも見慣れているはずの青い空の中に、私は消え、空と一体になってしまったのだ。
不思議な経験だった。私が身に付けているものをすべて捨てたとしても、余りある宇宙の慈悲の中に包み込まれたとでも言ったらいいのだろうか。一種の恍惚状態に陥り、神秘体験の時とは違う言葉にできない浄福感を味わった。
ギャラリーの入り口には、井戸水がチョロチョロと流れていた。川のすぐ畔で育ったので、水音が私を誘い込んだのだろうか。それとも草の思い出だったのだろうか。
育った村は山奥にあったので、自然に囲まれた暮らしがすべてだった。裏山に咲く山百合・桔梗・女郎花・野あざみの花々。峻烈な雪の思い出。飛び交う鳥の群れ。白つめ草がたくさん咲いていて、そこにはいつも空があった。
流れる雲を追いかけたり、天空にはきっと特別な世界があるような気がして、私は空を眺めると胸キュンになってしまう、ちょっと(いや、かなり)変わった子どもだった。空は、刻々と変わる不思議なキャンバスだとも思っていた。周囲は山に囲まれ、寝ころんでいると、私は空の世界にいた。
ボードレールが「なんとそなたが輝くことだ、雲間を漏れる日に映えて」(『悪の華』より・堀口大学訳)とうたったように、私も空はそなたであり、輝く空に吸い込まれたりときめいたりしていた。
草むらから眺める鰯雲・入道雲・マリンブルーの空・赤く燃えた夕焼け雲・ひこうき雲・荘厳な落日……。遠い昔の思い出だったとしても、誰にも侵されない、私が充実して生きてきたという感覚は大人になっても続いていて、私はいつも幸せな記憶を持っていた。でも、私だけが特別ではなく、子どもの日の懐かしい記憶は誰の心の中にもあるのだと思う。
それにしても、あんなに満たされた瞬間はなかった。奇蹟のような一瞬。たった一人、言葉にはできそうもない浄福な一瞬を味わったのだから。でも、あの日の出来事は、どんなに空を眺めても二度と味わうことのできない一瞬であった。