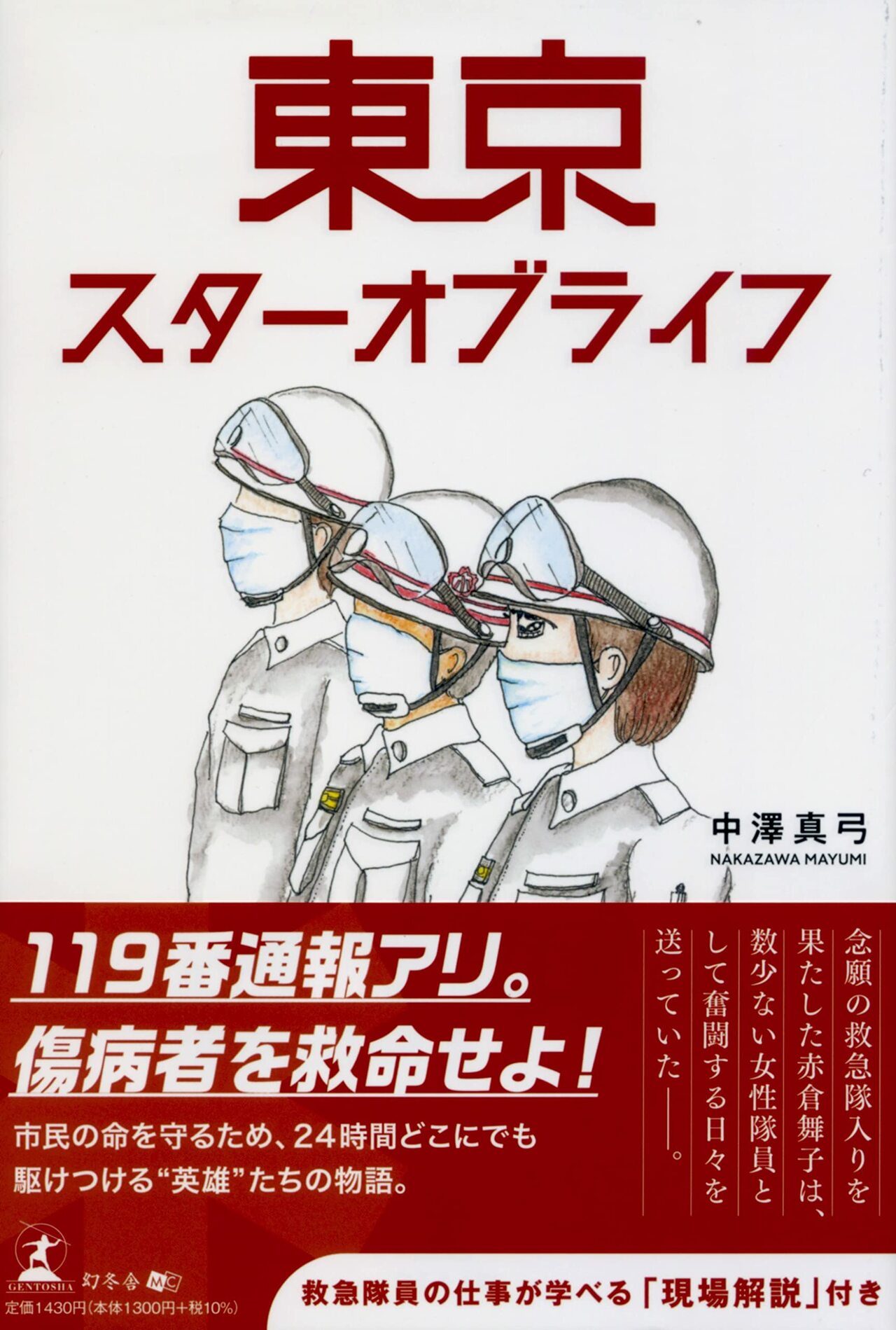「ご苦労さん」
病院の駐車場で心電図モニターの記録紙を補充していた舞子に、医師引継ぎを終えた菅平が声を掛け、感染防止衣のポケットから缶コーヒーを取り出した。舞子が救急隊員になって約一ヶ月。重症事案や、長時間の救急活動になった時、菅平はどこからか缶コーヒーをポケットにしのばせて戻ってくる。それは、「糖分のとり過ぎにならないように」という菅平の方針で、苦いブラックコーヒーと決まっていた。
「死亡確認、立ち会ったのは初めてだったっけ?」
「はい……」
舞子はさっきの光景を思い出していた。
舞子たちが搬送してきた高齢男性の傷病者は、病院の初療室に入ったところで医師から心肺蘇生の中止が指示された。引継ぎ医師が、心電図のフラットなラインなど死の徴候を確認し、死亡確認の宣言をする。
「十五時三十分、ご臨終です」
付き添いとして救急車に同乗してきたヘルパーと、救急隊三人はそっと手を合わせた。
「隊長、所轄の警察が到着したみたいなんで、時系列を申し送ってきます」
岩原が時間経過の書かれたメモを持って、警察のライトバンに向かっていった。この傷病者は、どうして亡くなったのかわからないから、警察に引き継いで死体検案を受けることになってしまうのだ。
「隊長は……。悔しくないんですか」
「悔しいって、何が」
「さっき、指示要請したとき、指導医から特定行為はしなくていいって言われましたけど……。現場では、心電図も完全な心静止ではなかったし、アドレナリン投与したら助かったかもって、思ったんです。家族がいないからとか、高齢だからとかで、特定行為するとかしないとか、なんか納得いかないんです」
菅平は困ったように首を傾けて、ますますパグ犬のような顔になった。