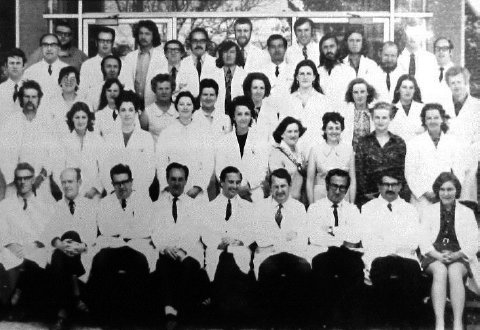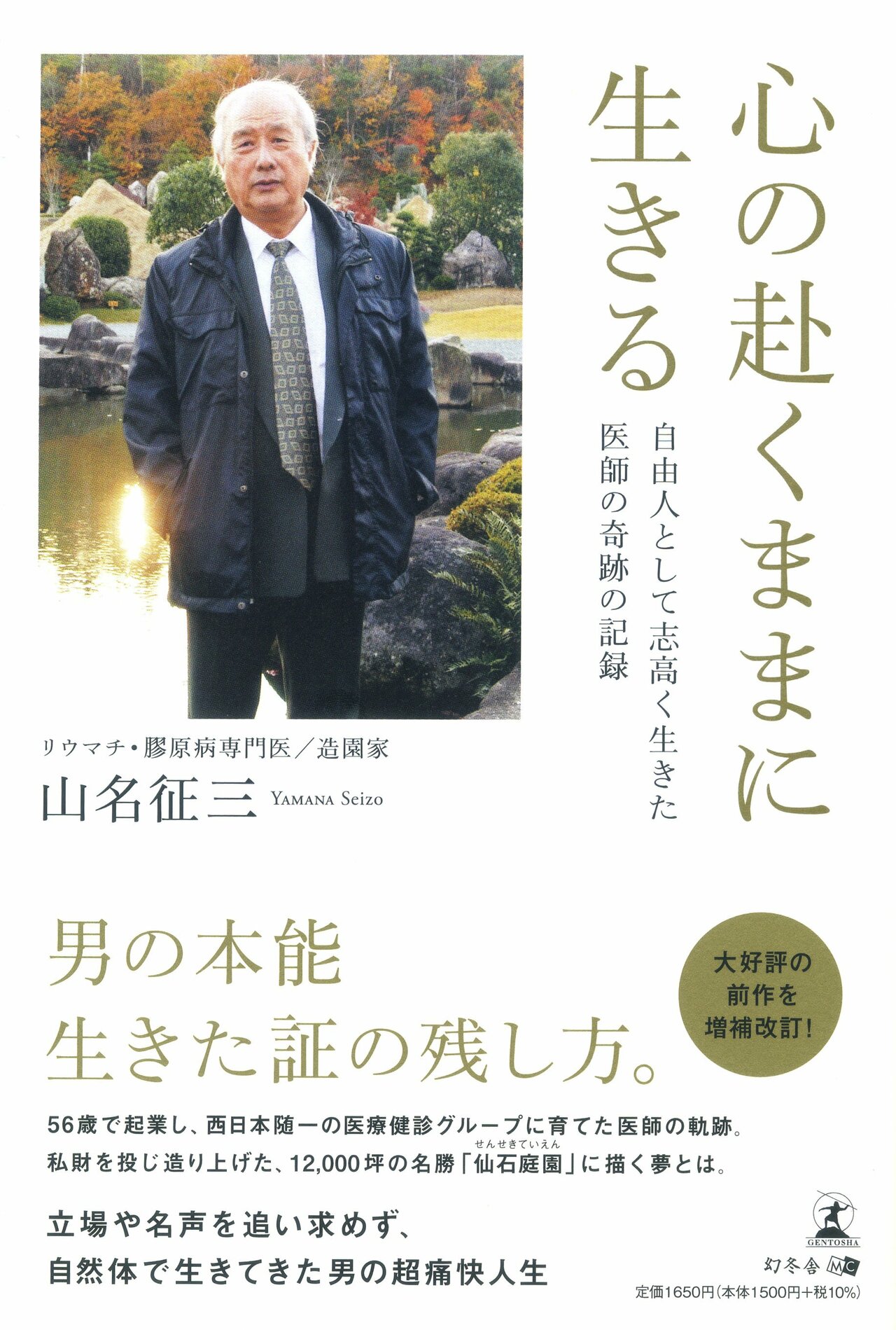【前回の記事を読む】世界的評価まであと一歩…医師がかつての免疫研究で「猛省」
Monash州立大学免疫病理学教室でPh.D.コースへ
メルボルンのタラマリン空港に降り立った。離日前、送りに来た父親から、「征三、お前は地の果てに行くのか」の言葉をかけられていたが、日本から13時間を要する遠い国であった。空港には若い美しい女性がDr. Seizo Yamanaと書いたプラカードを掲げて私を迎えてくれた。これから3年間一緒に仕事をすることになるジェニファー・ローランドとの出会いであった。メルボルンの第一印象は大変素晴らしいものとなった。約1時間の車中の会話もはずみ、私の英語も捨てたものではないと感じたものである。
これからの仕事場であるモナシュ大学の附属病院アルフレッド病院に着き、早速ネイルン教授の教授室で初顔合わせの機会を頂いた。ネイルン教授は私より少し背が高い程度の小柄であったが、雰囲気は英国の紳士はかくありなんと思わせる風貌の持ち主であった。到着後、数日のうちに私の当面の住居が準備されていること、所属研究室の事を知らされた。その中で大変うれしかったことは、ジェニファーと同じラボで机も隣であったということである。以来、研究室内におけるすべての事は彼女が細かく気遣いをしてくれた。
到着後しばらくしてネイルン教授から私の仕事のテーマは腫瘍免疫であること、上司はデイビス講師であることが矢継ぎ早に告げられた。私のテーマが腫瘍免疫であることは寝耳に水でネイルン教授とデイビス講師と私との3人でかなり激しい議論となった。私の言い分は抗胸腺細胞血清の仕事をするためにメルボルンに来た。未解決の宿題も多く残している。これを解決して腫瘍免疫に行くのならOKだと言い張った。
デイビス講師はセイゾウはsticky manだとティータイムの時に皆の前でいったので、私はsticky manの意味がとっさに理解できず、なんという意味かと周囲に問い返すと周囲の者は気まずそうな顔をしていたのを今でも思い出す。通常は“やねこいやつ”だという意味だろう。善意にとればこだわりの強い人間だという意味にもとれるが、デイビス講師の物言いと、周囲の雰囲気からは前者の意味だったのであろう。