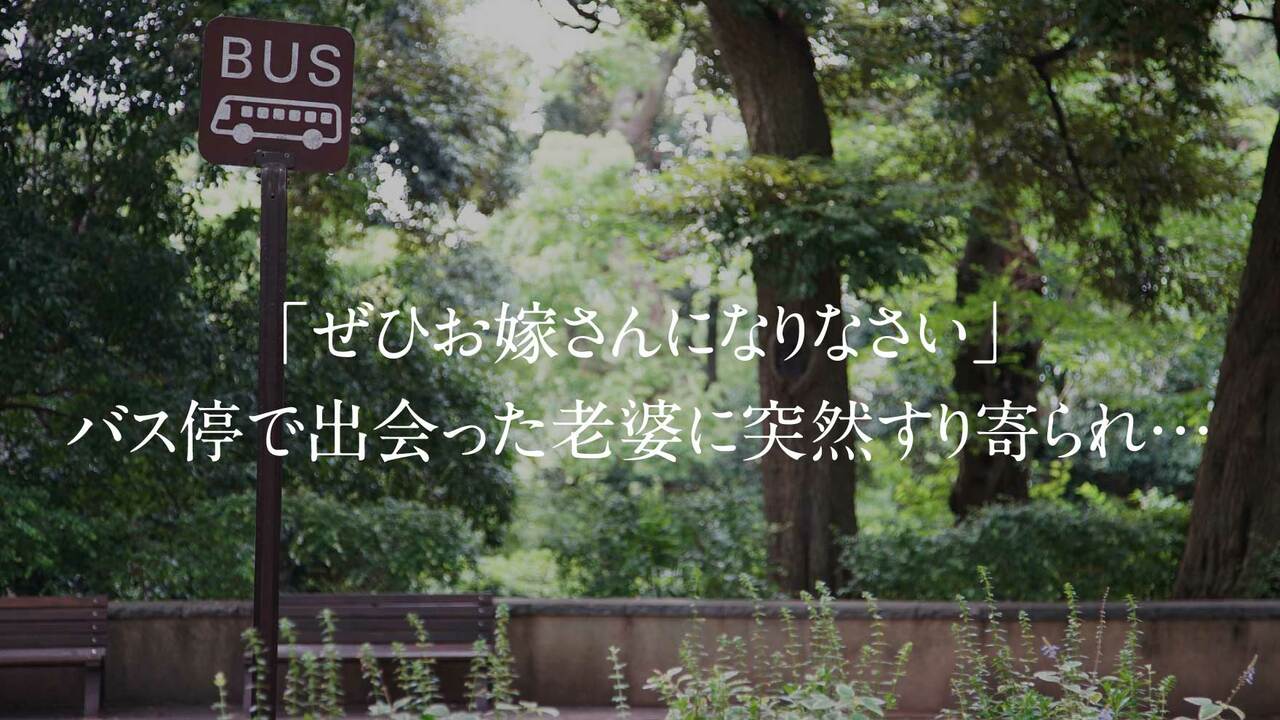【前回の記事を読む】書店でサインをくれた川端康成の自死に「驚かなかった」理由
井上靖
それから小説や、後に『美しきものとの出会い』を読むようになった。
『美しきものとの出会い』の中で一番好きなのは「私の法隆寺ノート」である。
特に日本画家・荒井寛方との交流のエピソードは胸を打つものがある。
「ある時、私は荒井寛方と氏の宿舎であった小さな寺の一室で会った。爆撃の烈しい頃で、氏は老体にも関わらず、はたで見ても判る不自由な自炊生活をしながら、毎日のように火の気のない金堂に通っては、模写のために作ったやぐらの上に坐り込んで、労多くて報いられることのまったくない模写という仕事に、無報酬で没入した。
『形あるものは亡びますよ。爆撃で亡びるかも判らないし、爆撃で亡びなくても歳月で亡びますよ』
荒井寛方はその時そんなことを言った。
『描き上げられますか』
『さあ』
『描き上げたものを保存できますか』
『さあ』
私の質問には一つも答えなかった。答えることのできない時代であった。併し、明日の日は判らなくても、やはり模写しなければならない。本物も模写も共に消滅するにしても模写の努力だけはしたという人物がなかったら、金堂の壁画は泣きますよ。と彼はそんなことをほそぼそとした口調で言った。私は荒井寛方と最後に会ったその日の心も体も引きしまるような感動を、今でもはっきりと思い出すことができる」と綴られている。
このような人物が、日本の美術を支えてきたのだと思った。
追悼号を読むと、井上靖の眼差しに感銘を受けた日が甦る。
古い友人は、当時私がこの作家を熱く語っていたことを覚えてくれていて、面白かったと笑った。おまけに小説『氷壁』に感動し、大胆にも女の子一人で山岳部にまで入部したのだから、このリリシズム溢れる作家との出会いは大きかったように思う。
後に、亀井勝一郎や太宰治と親しかった文芸評論家、三枝康高の『井上靖――ロマネスクと孤独』を拝読し、「瞳」が『北国』の詩集の中で最も優れたものというだけでなく、現代詩の秀作の一つであること。そして『北国』が戦争の悲しみを、自分の魂を記録した、すなわち死と受難の心情を歌った詩であったことに驚かされた。
『北国』に出会った時、三枝先生の解説のように、人は確かに理由もない孤独に佇まなければいけない時があり、幼い心でえりちゃんの死、命の悲しみを懸命に受け止めようとした私と重なったような気がしたのだが、戦争体験が原型になっていることを知った。
詩「比良のシャクナゲ」の中に、「幸とか不幸とかに無縁なひたすらなる悲しみ」という言葉が出て来るのだが、ふいにこの言葉が浮かんでくることがあり、今もどこかで支えてもらっている気がする。
時を重ねた今、小説『星と祭り』『化石』は、特に共感できるものが多い。遺作となった長編小説「孔子」を再読すると、(まだ間にあう)といった、私を軌道修正する何かが漂っている気持ちにおそわれる。読書は、忘れかけていた大切なものを取り戻してくれる力を持っている。
ページを開けば、その人の精神に再会できるし、それが誤読や稚拙な理解であったとしても、私の人生に役立つものなら大切な存在であると思うようになった。
また、時代を超えて世界の様々な人に出会える唯一の手段であり、自分を生きるために教え導く存在だと思っている。