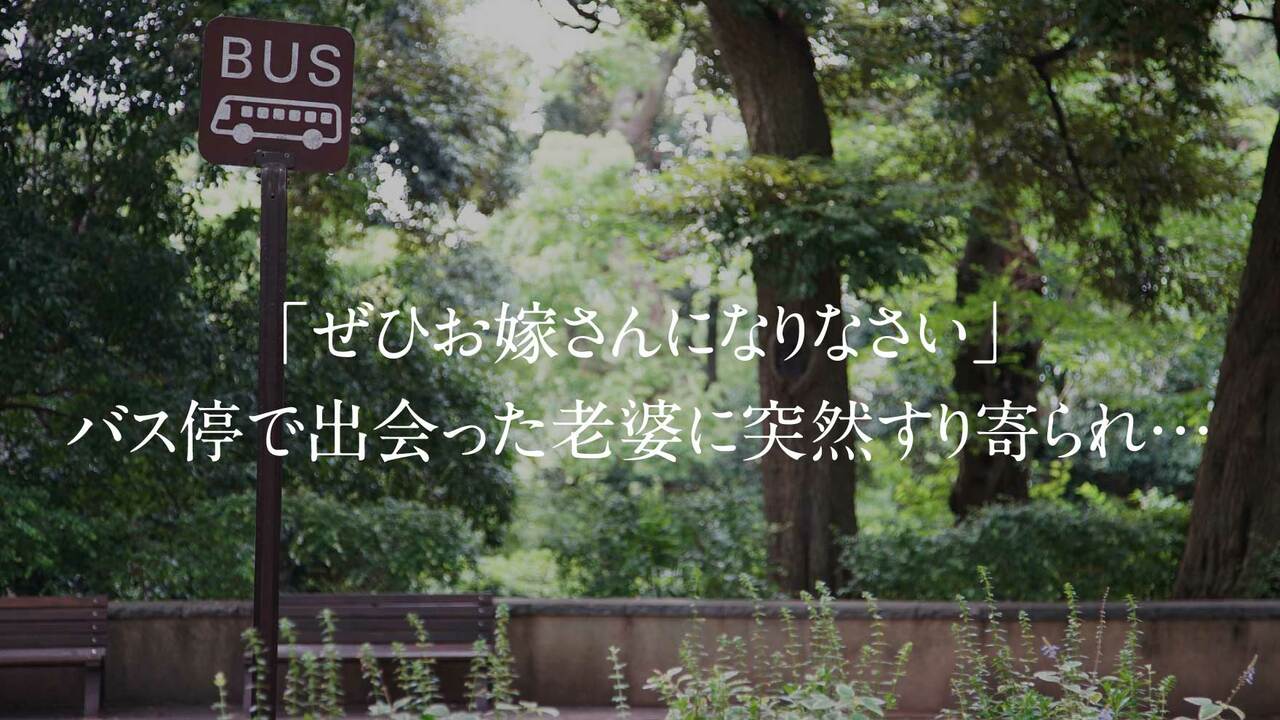【前回の記事を読む】書店バイトで川端康成に遭遇!何故かひどく寂し気な後ろ姿…
川端康成の眼
レジにいた私は、歩き始めた川端康成に向かって「サインをして頂けますか」と日記帳を差し出したのだ。この恐るべき勇気。
怖いもの知らずというべきなのか、小娘の図々しい恥知らずな言動であった。それを咎めもせず、川端康成は少し眼を細め、じっと私を見つめた。まばたき一つしない眼は、思いがけず優しかった。そして、一言も言葉を発せずサインに応じてくださった。しかし、顔を上げたその後の眼は、どこか虚空を彷徨っているような不思議な眼だった。とても印象に残った眼だった。私はその眼をみながら、なんて憐れな人なのだろうとか、私のほうが労ってあげなくてはいけないような想いに駆られたことを記憶している。
自死を知ったのは、四月に入ってからで衝撃を受けた反面、あまり驚かなかった。今にして思うと、きっとあの眼から漂っていたもののせいかもしれない。
当時、自死の真相について様々な憶測がとんだ。調べてみたら、そのような運命を予感させる文章に出会い驚かされた。作品『故園』の幼年期の回想も、胸を打つものがある。顔を近づけて見た祖父の顔に、死の寂しさを感じ、死に顔と違わない寝顔を眺めた少年の孤独意識は私に想像すらつかない。
また、リルケはロダンを書いた文章で、「ロダンは名声を得る前孤独だった。だがやがておとずれた名声は、彼をおそらくいっそう孤独にした。名声とは結局、一つの新しい名のまわりに集まるすべての誤解の総称にすぎないのだから」と述べている。
川端康成は、(私は世界が認めたすごい文学者なのです)などという雰囲気を微塵も感じさせず、むしろひどく寂しげだった。人生の途上で、あんな悲しい眼をした人に出会ったのは、この作家が最初で最後であった。
あの頃は三島由紀夫が自決したり、学生運動の名残が続いていて、ある種の激動の時代だったような気がする。
幼い頃から闇を見つめてきた人は、俗事に疲れ、彼岸を見る眼が色濃くなっていったのだろうか。感傷的ではあるが、日本のヘルダーリン(ドイツの詩人・思想家)のような人だったのかもしれないと思ったりした。ヘルダーリンの詩『帰郷』は私も好きな詩で、三島由紀夫も若い時影響を受けている。私などには計りしれない二人の巨匠の間には、独特の共有できる何かがあったのだろうか。三島文学は読んでいないが、二人の間の(往復書簡)には、両者ともに切実なものが漂っているような気がする。
「小生が恐れるのは死ではなく、死後の家族の名誉です」と、三島由紀夫は死後の自分を託すのである。文学者とは、書くことでしか生きられなかった人たち。俗事とは次元が違う、抜き差しならない魂を背負った人たちの心に宿るものなのかもしれないと思うようになった。
川端康成が去った後、店長は「ハッチは勇気があるなぁ」と肝を潰したような声を出したけど、私の大馬鹿ぶりは、大切な宝物になった。
立花隆は、著書『臨死体験』上の中で、三島由紀夫は、『仮面の告白』の冒頭で、自分は生まれたときのことを覚えていると書いておられる。また夏目漱石も臨死体験をしており、心理学者のユングは自分も臨死体験をしており、青い地球を見たと自伝の中で書いているのだという。「臨死体験」と「神秘体験」は、かなり類似性があり、立花隆の知的好奇心には圧倒される。私は息子に「脳みそのない立花隆」と揶揄される時がある。