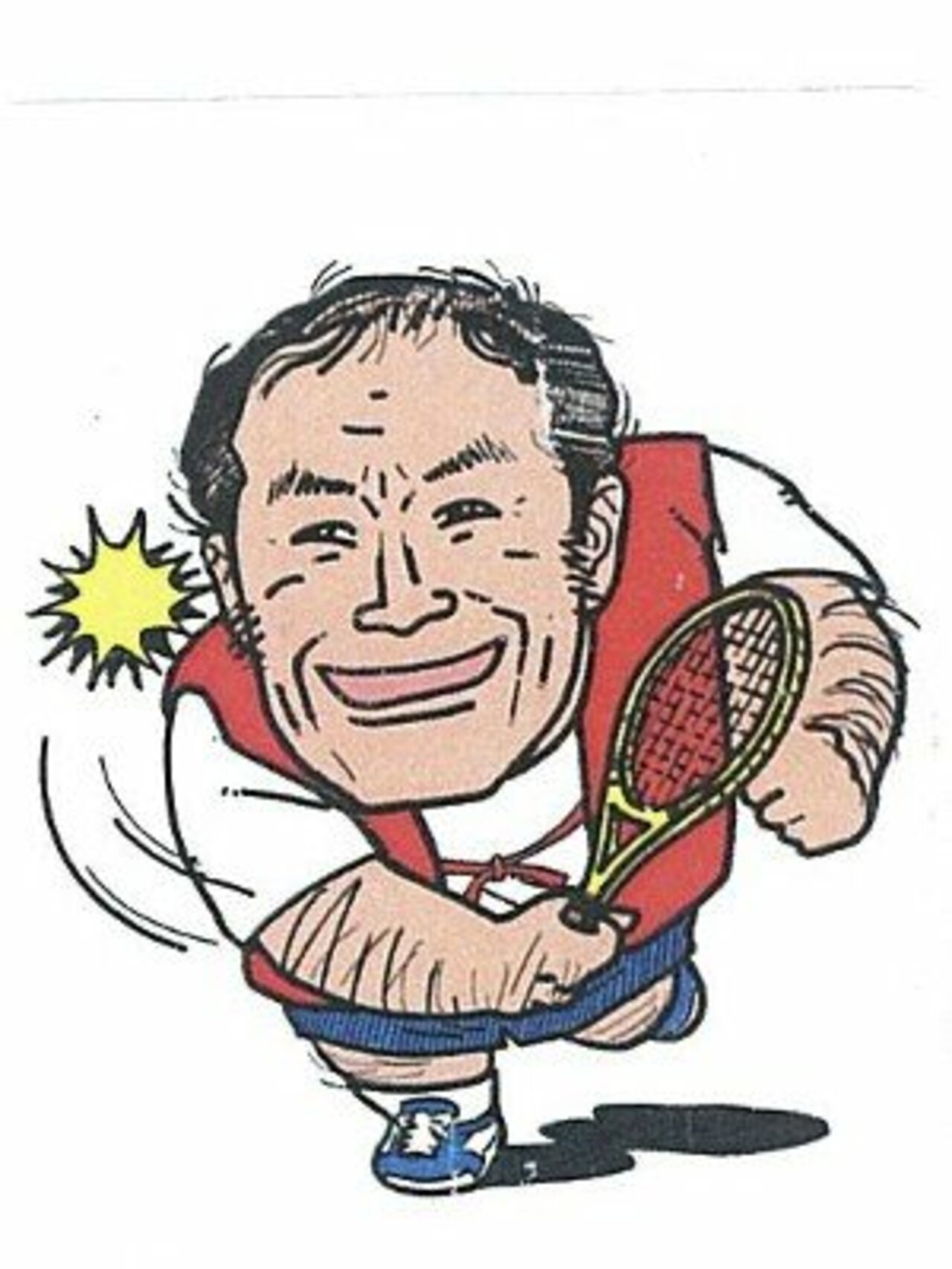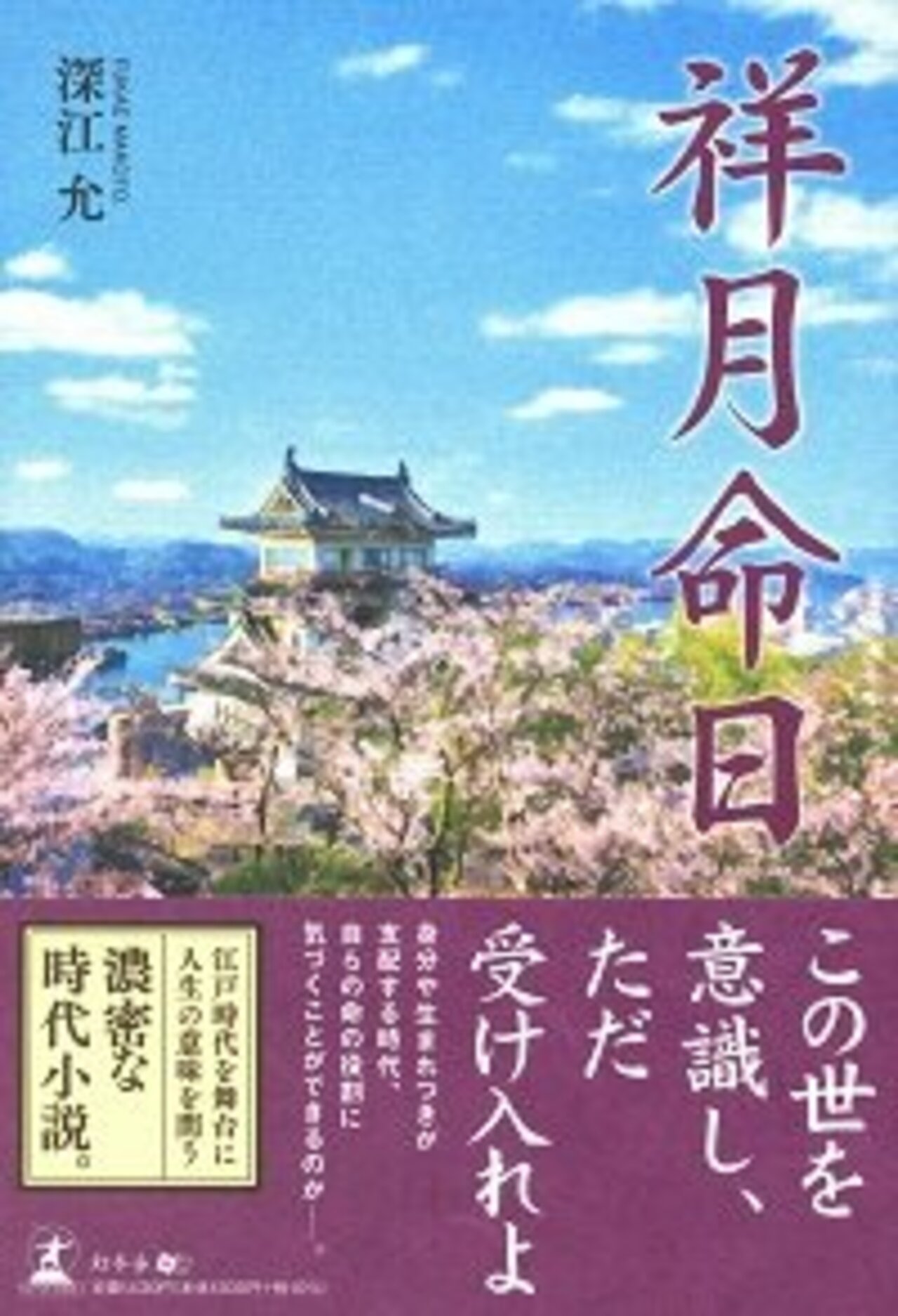【前回の記事を読む】「やっとうはできなさるんで」…“やっとう”とは何か?
坊の入り江
二
吉三と重太郎は、藩内で二番目に大きな川である一の目川を渡り、さらに海岸線を南に向かった。
「重太郎さん。こちらのほうは初めてで、来たことがないでしょう」
吉三は親しげに話しかける。それまでも、金崎港を調べた話や坊の入り江の様子などを一方的に話しかけていた。
「あっしや、加持様のことを加持家に婿養子に入る前から良く知っていましてね。加持様は剣の修行のため、山ごもりをしたことがあるんですよ。そのとき、諸星様と会われて、それが縁でしてね」
十年前、加持家皆殺し事件が起こり、たまたま居合わせた新宮寺司が賊の一人を斬って、唯一生き残りとなった美月を助けた。しかしながら、司は不可抗力とはいえ、人の命を奪ったことで心に葛藤を抱えることになり、それを曹洞宗法円寺の住職の学然和尚の叱咤で、剣で生きる者の宿命として、一生背負っていくと覚悟を決めた経緯がある。
その後、加持家襲撃事件の首謀者が、時の筆頭家老・都野瀬軒祥の惣領の祥之介であるとわかると、美月に助太刀をして敵をとらせた。この敵討は重太郎が十二歳のときのことで、竹矢来の外から見ていたから良く覚えていた。
吉三は和木重太郎に初めて会ったとき、彼の憮然たる風貌を見て、この世に生まれての不条理に対する反骨があると感じた。しかしながら、一言では表せないが、その不条理を自分では変えられないことも知っていて、不条理の本質の、この世に生まれた不可解さに対する無力感というか、疎外感というようなものに、それに対する焦いらだち燥と悲哀の混ざったものを感じた。
一方でそういう負の意識ばかりでなく、重太郎が十四歳のときに親元を離れ江戸に出たと聞いて、その不条理を跳ね返そうとする意思を感じるのである。とりあえずかどうかはわからないが、その後、剣の道を選んだということは、心の葛藤が世の中を変えてやろうという外に向かわずに、自分を鍛えようと内に向かったということだ。
「いろいろござんしょうが、生きているということは、いいもんでござんすよ」