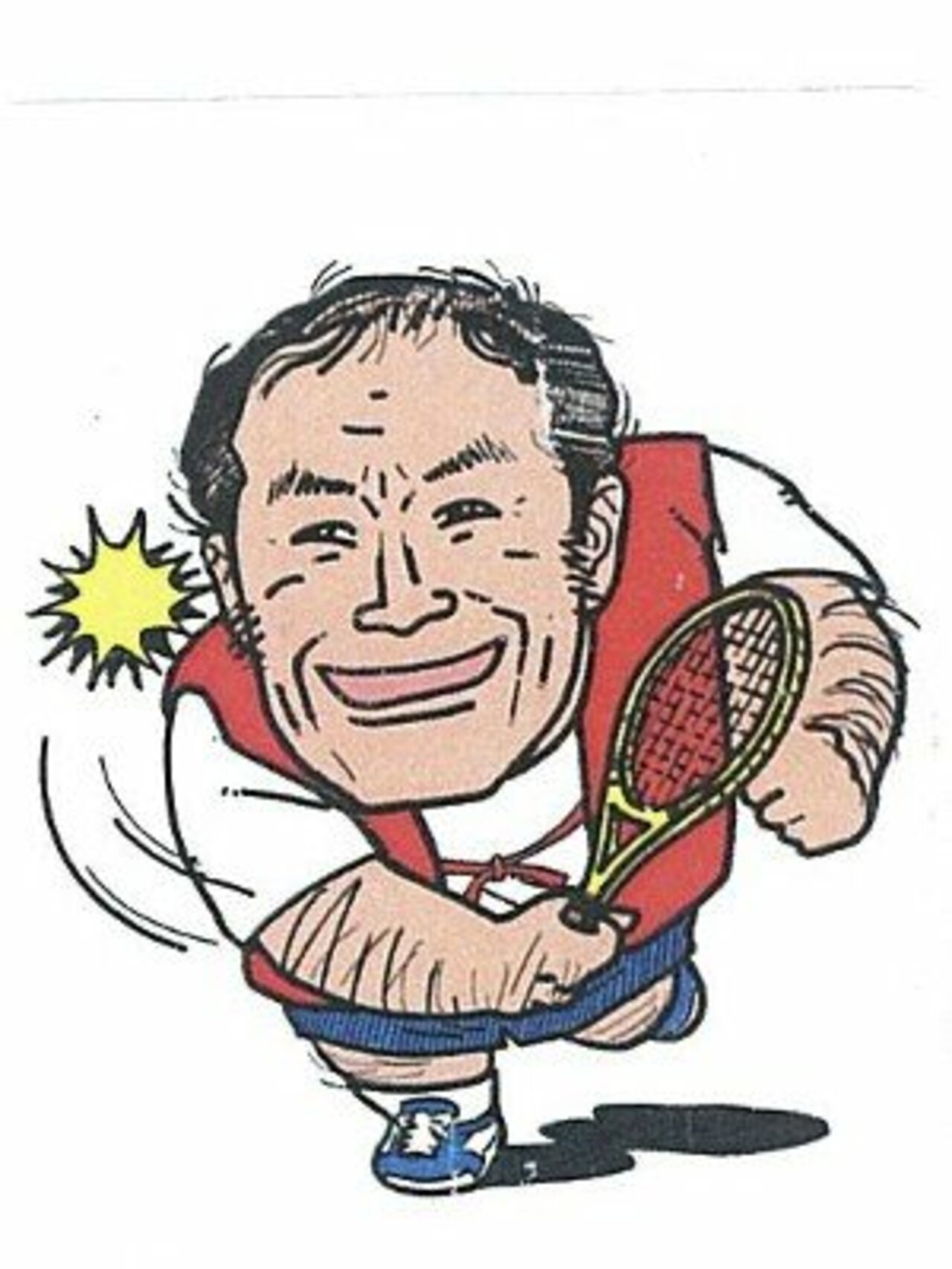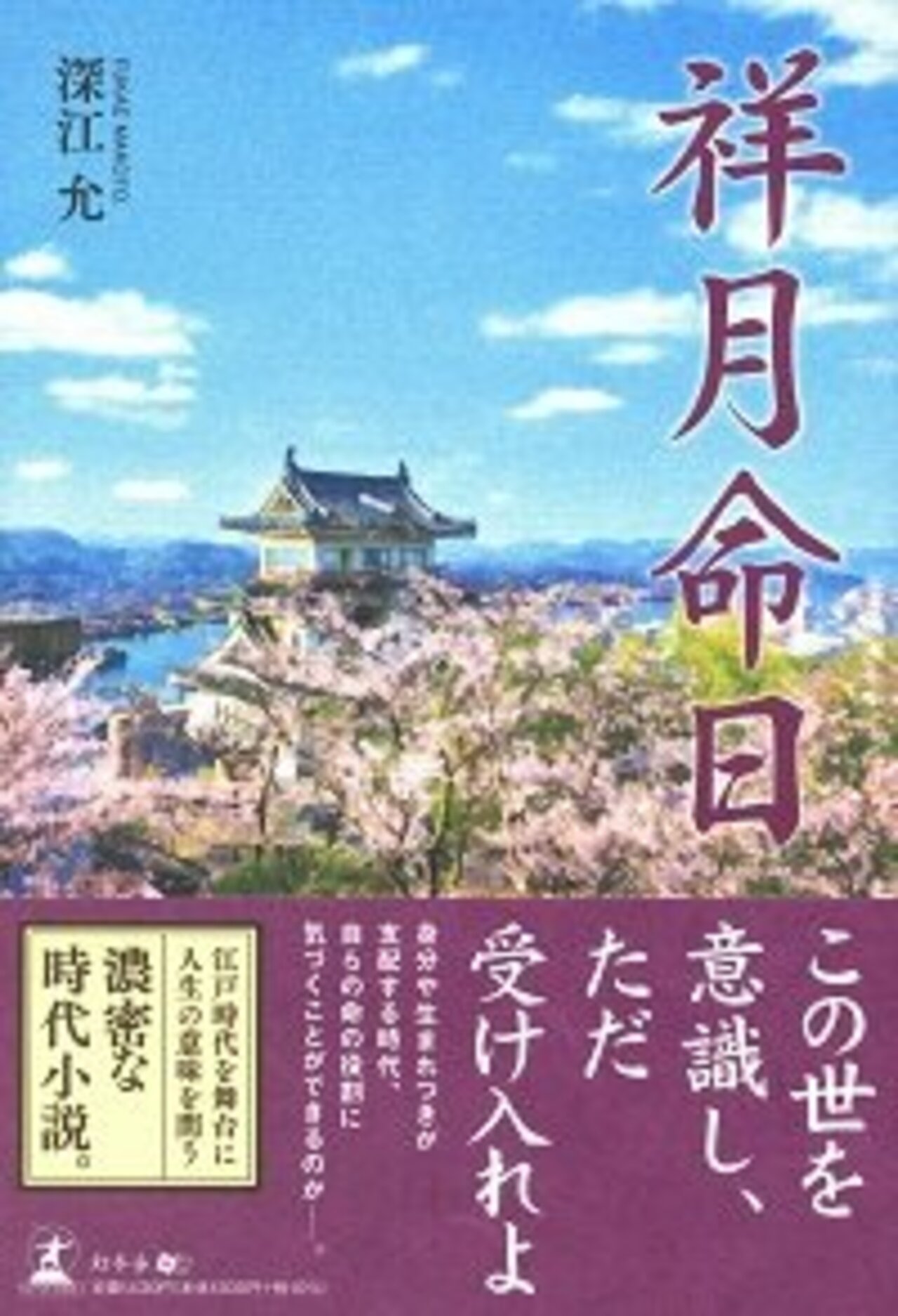【前回の記事を読む】【小説】「生きているということは、いいもんでござんすよ」
坊の入り江
三
勢戸屋は坊の岬沖で抜け荷の荷を瀬取りし、坊の入り江の南端の断崖に沿って蕪木川の河口に向かい、さらに、川を遡って陸揚げしていた。
吹の村人は、坊の岬の先からどこからともなく帆をはった小舟が現れて、入り江の中央に連なる岩礁の陰を、蕪木川の河口に向かって上っていくのを幾度となく見ていた。舟が見えるのは潮が止まったときか、上げ潮のときである。ただ、帆かけ舟が漁の邪魔になることはなかったので、村人はべつに気に留めることもなかった。
ましてや、蕪木川が入り江に流れこむところは灌木と芦原で覆われた荒れ地で、小舟がそこにさしかかると、その先はすぐに見えなくなるので、なおさらのことだった。
人が立ち入らない蕪木川下流域は湿地帯で広く、その上流は脇坂家老の知行地と繋がるのを利用して、勢戸屋がそこに一時保管場所をつくった。人に知られずに抜け荷の荷を運び入れるのには最も適している場所だったのだ。
吉三が坊の入り江での抜け荷のことを調べられなかったのは、冬の間は海が荒れていて抜け荷は休止だったことによるのと、坊の入り江の荒れ具合を知っていたから、まさかという思いがあったことは否めない。それでも、坊の入り江の抜け荷にもう少しで気づくところまでいったのだが、そこに異国船の海難事故が起き、勢戸屋が抜け荷を中断してしまったことが大きい。
しかしながら、疑惑が消えたわけではなく、続けて勢戸屋を調べたことでわかってきたことは、勢戸屋が頻繁に次席家老の脇坂兵頭の屋敷に出入りしていて、かなり親密らしいことであった。
四
坊の入り江は人が近づかない場所であったが、入り江の北岸の奥まったところに吹とよばれる半農半漁で生活している二十戸ほどの村があった。
吹に行くには、坊の入り江の北岸の突端の鷲の嘴を回るか、疾川沿いの道を上流に向かい、滝壺に行きつく手前を右に折れ、道とも言えない山間の道を登って下って、坊の入り江の北岸に出るかである。
そこは三の窪と呼ばれる砂浜の窪地に繋がり、吹の村はそこからさらに東の、入り江の奥まったところにあった。やはり広い砂浜が続く窪地で、一の窪と呼ばれているところである。
鷲の嘴は干潮時にならないと岩場が現れないので、吉三と重太郎は疾川沿いの道をさかのぼり、三の窪から吹の村に入った。吉三は村長の友左衛門に事情を話し、一晩世話になることになった。
「御苦労様なことでございます」
春になったとはいえ、夜はまだ寒い。囲炉裏の火を絶やさないようにしながら、友左衛門はめったに来ない客を歓待するために、自分でつくった芋を発酵させた飲み物を勧めた。いまみたいに蒸留してないからすっきりとした味というわけにはいかないが、吉三は喜んでお相伴にあずかった。重太郎はまだ酒の味はわからなかったから遠慮した。