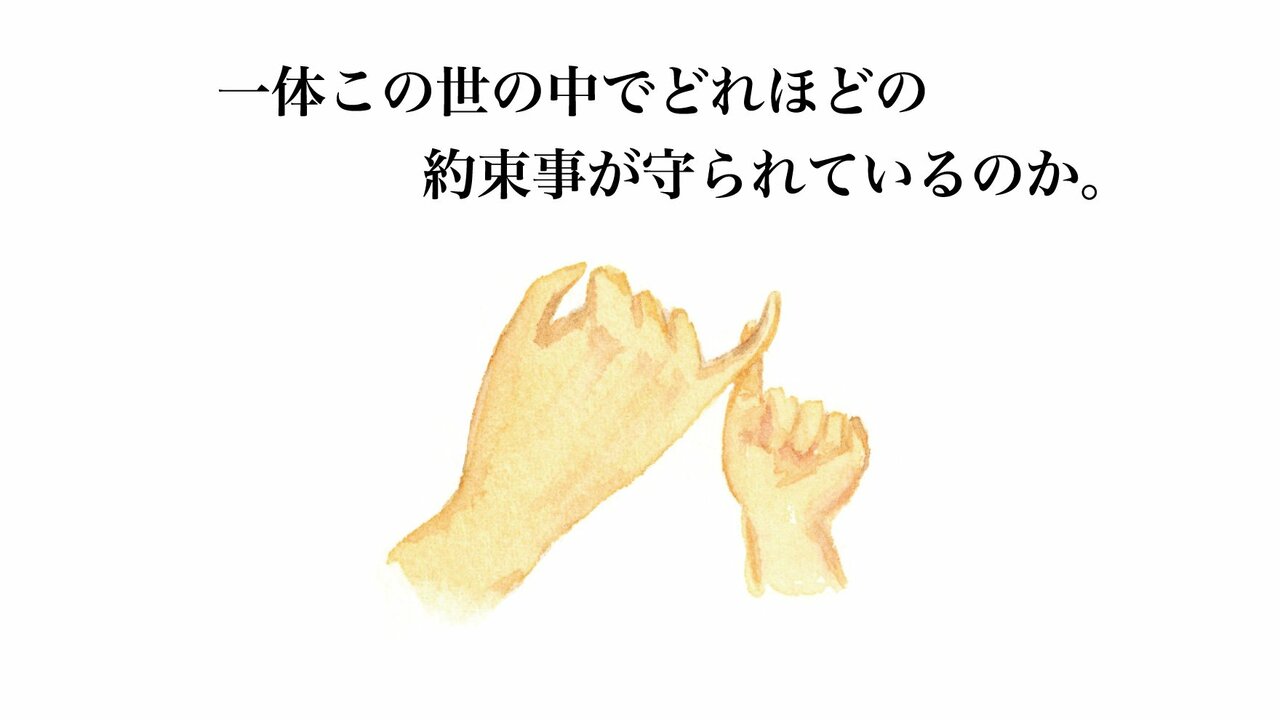スノードロップの花束
新藤と待ち合わせたのは会社の隣にある「樅」というカフェで、社内外の打ち合わせによく利用する店だった。古くからの喫茶店だったのを、数年前に新藤の設計でいわゆる和モダン風にリノベーションした。大きな梁と吹き抜けを見上げながら、「全く私は雑用係だ」と穂波はつぶやき、出先から帰って来る彼を待っていた。カフェラテを飲み終える頃、約束の時刻に十五分ほど遅れて、新藤は駆け込んで来た。
「すみません、現場が立て込んで。申し訳ない」
「お疲れ様。忙しいのに悪かったわね」
「いやいや、穂波さんからのお誘いなんで、どんな案件もキャンセルしますよ」
そつなく答えまっすぐ視線を合わせてくる新藤を、穂波はにっこり見つめ返す。
「今日は何ですか? また木遣り歌の練習じゃないですよね」
「その記憶は封印して。今日は設計課の社員の相談案件です」
「はあ、パワハラか何かかな、身に覚えはないけど」
「パワハラではないの。手短にきくけど、宇佐美麻奈さんの仕事ぶりはどう?」
「うさこか。悪くないですよ。もう二、三年経験を積めば一人前の仕事はできるでしょう」
「ではうさこちゃんと呼ぶのはやめるよう、課長から課員に徹底してください」
「なるほど、わかりました」
「それから、彼女はある男性からの度重なるアプローチに困惑しています。プライベートな問題ではあるけど相手は同僚なので、仕事に対するモチベーションに関わると思うの」
「志賀ですか?」
「知ってるのね。京都で二人きりにした新藤課長の責任だと思っているみたい」
「あれは、志賀のために僕がセッティングしたようなものなんだけど。宇佐美もはっきり断らないから、志賀も押せばどうにかなるかと思っている、かな」
「宇佐美さん、あんなにストレートにものを言う人なのに、空気を悪くしたくないのか、本人には言いづらいみたい」
「女同士だと言いたいこと言えるらしいけど、男の前ではあまり言わないよ。誰にでもいい顔しようとする、八方美人だな」
「そうなの? まあ、女のサガね。若いときは私も言えなかったな」
穂波が澄まして言うと、新藤は眼をむいて、
「穂波さんは全然違うよ」と肩を揺らして笑った。
「あのとき、完膚なきまで叩きのめされた。僕も、塩田さんも」
「え?」
話の脈絡が読めず、突然出てきた塩田という名前に穂波は動揺した。
「塩田君、今どこにいるのかな」
「さあ、沖縄から絵葉書が来たのが二年くらい前かな。どこかで生きているでしょう」