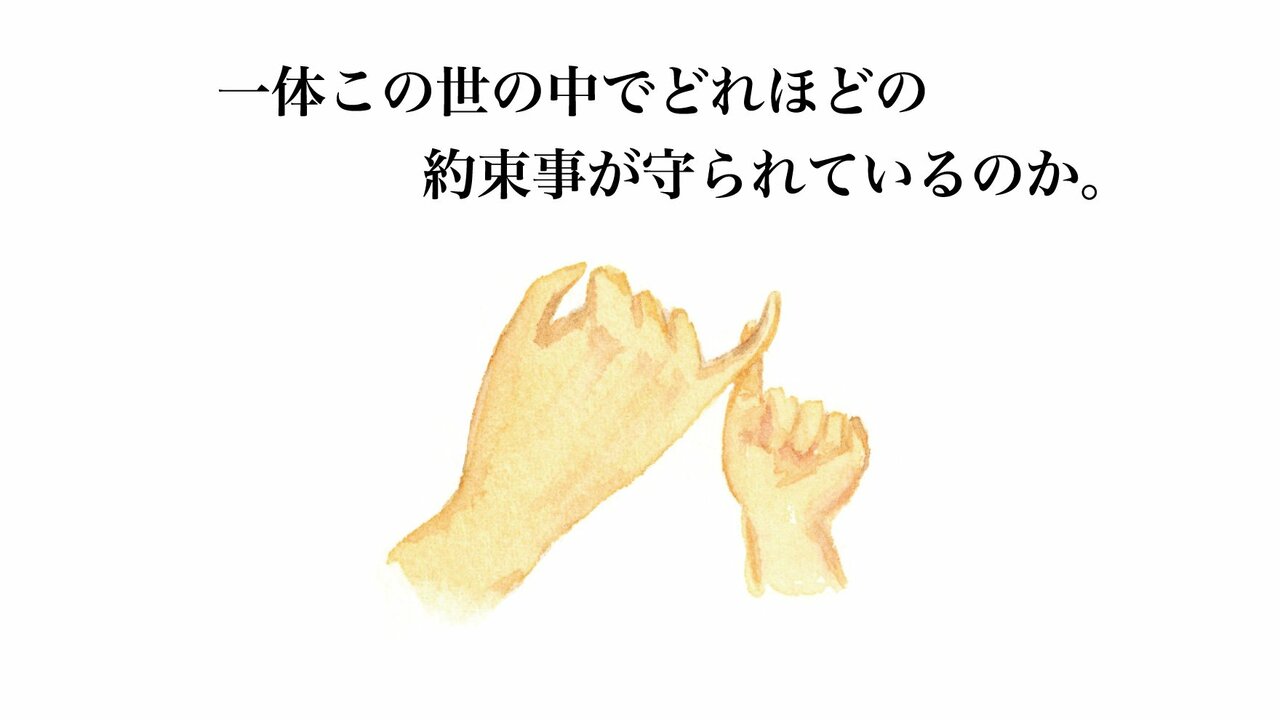【前回の記事を読む】「君の結婚の話、白紙に戻してくれないか」「関係ないでしょ」
スノードロップの花束
太一は会社員として働く傍ら地域の消防団に所属し、また南アルプス北部の山岳救助隊という、遭難した登山者の救助にあたるボランティアにも参加していた。個人の自己実現に躍起になっている塩田と、縁の下で力を尽くすことを惜しまない太一。
太一は「俺について来い」とは言わないが、穂波と共に歩む未来を真摯に考えてくれている。それは愛の多少ではなく、自分の生き方の選択だった。穂波がこの選択を後悔することはなかったが、思い出せば長い結婚生活の間には、道に迷いそうなことは何回もあった。
「たしかにあのときは、私は塩田君にきっぱり言った。でも新藤君、あなたを完膚なきまで叩きのめした覚えはないんだけど」
「あのね、穂波さんは気遣いのできる人だけど、とても鈍感なところがある」
「わからないけどごめん、デリカシーがない女だと太一にも言われる」
「僕にとって塩田さんは大学の先輩、穂波さんは会社の先輩だった。僕は塩田さんのアクティブな、世界を股にかける生き方に憧れていたし、穂波さんの仕事ぶりを尊敬してもいた。そして太一さんは堅実で間違いのない人だと思ったけれど、塩田さんが言ったように、穂波さんは普通の奥さんに収まるような人ではないとあのときは思ったし、結婚をとりやめてくれればいいとも願っていた」
「そうだったの?」
「そうでした。でも穂波さんの宣言を聞いて、太一さんとの結婚は揺るがないとつきつけられた。それ以上に、僕自身がこの会社を腰掛け程度に思っていたのを、この土地で建築士を続けていくんだという方向性を、道しるべをあなたに示してもらった。それがなければ東京か横浜の会社へ転職することも考えていた」
「そうなの?それってつまり?」
「僕は穂波さんを……僕は一生穂波さんについていくってことかな」
穂波は下を向いて笑いをこらえ、吹き出した。
「さすが、リップサービスは一流ね。愛人が三人いるだけのことはあるわ」
「おいおい、誰がそんなことを」
「愛人に関してはただの噂だから、私の胸に止めておく。でも宇佐美さんのことは、志賀さんにはっきり伝えてほしいの」
「ひとの恋路を邪魔するのは僕の流儀に反するんだが、お互い管理職は辛いね」
「そうね。ところで、輸入住宅専門の子会社設立の話があるって知ってる?」
「小耳には挟んでいる」
「私がその子会社に行くって言ったらどう思う?」
「僕らからすれば輸入住宅はライバルみたいなものだけど、僕はいつでも穂波さんを応援するよ」
「ふうん、ありがとう」