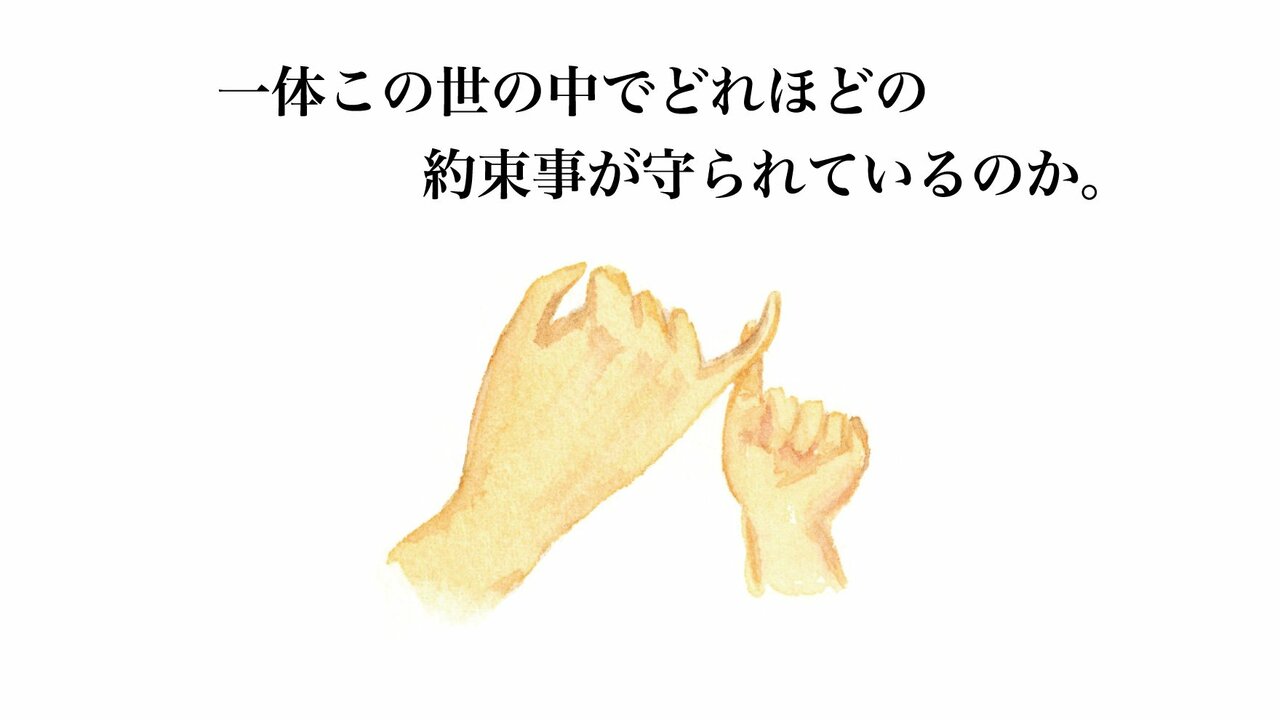【前回の記事を読む】リップサービスは一流ね、愛人が三人いるだけのことはあるわ。
スノードロップの花束
「親父はこの二週間笑顔が増えた」
微笑む太一に穂波が、
「あら、太一だって口数が増えたよ。ステファンはまるでわが家の末っ子だね」
「スエッコ?」
「the youngest or the baby of the family.」
サラが解説して、ステファンが不服そうな顔をした。
「ベイビィだと?」
「うふふ。ステファンも日本に留学する?」
「まだわからないけどー、また夏休みに来ていい?」
「いいよ。私もカナダに仕事で行くことがあったら、ステファンの家に泊めてくれる?」
「それはあなた次第。It's up to you.」
ステファンが言って、皆が笑った。
「ホナミ、見て」
サラが見せてくれたスマートフォンの画面には、ここ数日で次々と開いた花壇の松雪草が写されていた。グリーンの花芯を囲んで、雪のように白い三枚の花びらが下向きに開いている。
「松雪草はスノードロップ。もうすぐ春が来ると告げる花よ」
画像をよく見ると、数本をまとめた茎の下のほうにピンクのリボンが結ばれている。
「花束?」
「present for you.」
花を手折ることなく束ねられたスノードロップは、ずっと輝き続けるだろう。
「いいね。so cute.」
昨夜カナダから電話が来て、ブライト社の役員でもあるサラの母親と話をしたところ、彼女は「サラとはつい口喧嘩をしてしまうが、あの子の芸術的なセンスは認めている。日本に留学するなら信頼できるサポーターを探したいと思っていたので、是非あなたにその役を担ってほしい」と穂波に申し入れた。
「光栄です。私も彼女を見守りたいので」
と答えた穂波は、これが自分にとってビジネスの一環なのか、それともサラに対するある種の愛情なのかそのときは曖昧だった。しかし今はサラに「あなたが大好き」と伝えたいと思い、ぎゅっとハグをしていた。
「私、四月から子会社設立の準備室に異動になるの。ブライト社との交渉も多くなるから、本当にバンクーバーに出張するかもね」
誰に、というでもなく穂波は説明した。
取締役就任の件はまだ太一に伝えていない。
これから先、義父母の介護はさらに深刻化してくるだろうし、新会社設立となれば今まで以上に、登らなければならない山が目の前にいくつも現れるだろう。岩がごろごろしたガレ場のような山かもしれない。穂波自身の問題では老眼と腰痛に加え、人間ドックの検査結果のいくつかの数値も気になっている。優先順位は家庭か、仕事か、それとも健康か。まあ、時と場合によって違ってもいいのではないか。
It's up to you.
ソバージュの娘がショートボブの穂波に言い聞かせた。ほとんどは自分次第。でも自分の意思だけではどうにもならないことがあることも、半世紀近くを生きた穂波は知っている。