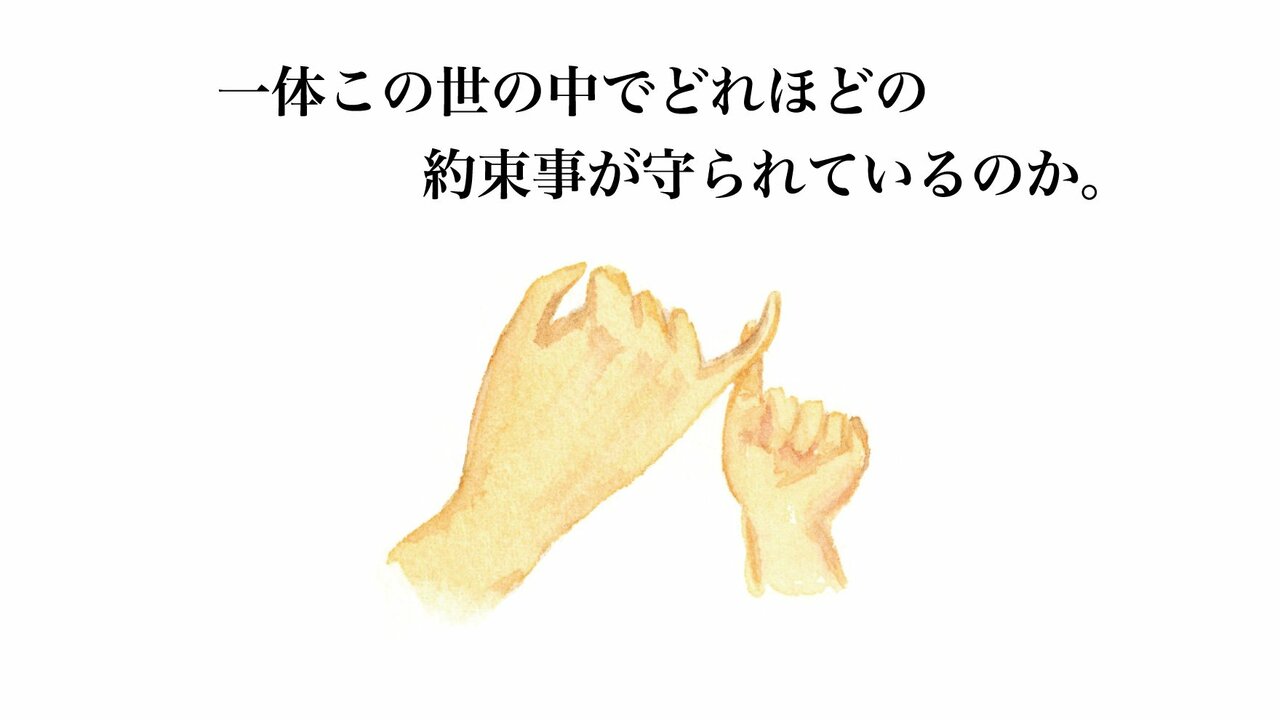マドンナの娘
十和子さんは美人だった、と物心ついた頃からずっと聞かされてきた。
美琴の母である十和子は実家の画材屋の看板娘で、「本町商店街のマドンナ」と呼ばれていたそうだ。商業高校を卒業して店の手伝いをしていた十和子に、画材を買いに店に来たある青年画家が一目惚れし、請われて絵のモデルになったことがあるという。彼は完成した油彩画に「マドンナ」というタイトルを付け十和子に贈呈したので、それは画材屋のショーウインドーに長期間飾られていて、マドンナ伝説を色濃くする要因となった。
「美琴ちゃんはお父さんに似たんだね」
残念そうにそう言われる度に、幼い美琴の胸はずきんと痛んだ。親戚や近所の人、両親の知り合いなどは皆、十和子に似た女の子の誕生を期待したのかもしれないが、娘は美琴一人だった。
「お父さんも美男子だがね」
これは完全な蛇足というものだ。信用金庫に勤める父彰彦は醜男ではないが、切れ長の一重瞼にエラの張った骨格を受け継いだ娘は、微塵も嬉しさを感じない。小学生になると、母のくっきりした二重瞼を受け継いだ兄が三学年上にいたので、教室の後ろで授業参観する十和子を見た同級生の女の子の中には、
「美琴ちゃんのお母さんきれい。お兄さんもハンサムなのに、美琴ちゃんかわいそう」
などと、正直なのか意地悪なのか知らないが、はっきり言う子もいた。
「ふうんだ」
美琴は傷ついていないふりをした。母が美人であるという誇りと自分は母に似ていないというコンプレックス、その対極的な感情を美琴は思春期を迎える頃までにはコントロールしていた。
授業に集中せずマンガを描いたり、家でも自分の興味のある本を読んだり音楽を聴いたりするのに忙しく、宿題はよく忘れる美琴だったが、成績は上位だった。母十和子の学生時代の成績は平均点くらいだったが、スポーツが得意だったと言っていた。美琴が母に似ているのは絵を描くのが好きということくらいで、学力と運動神経は父の彰彦から受け継いでいるように思えた。
中学二年生くらいになり将来の職業を真面目に考えたとき、美琴はモデルや芸能人やキャビンアテンダントのように容姿が武器となるような職業はもちろん度外視した。また「女性ならでは」の優しさや気配りや感性が要求される、保育士とか看護師とか美容師などにも向いていないと思った。
とりあえず漠然と男性と同格に働ける企業を目指し、進学校を受験するための勉強をするようになった。