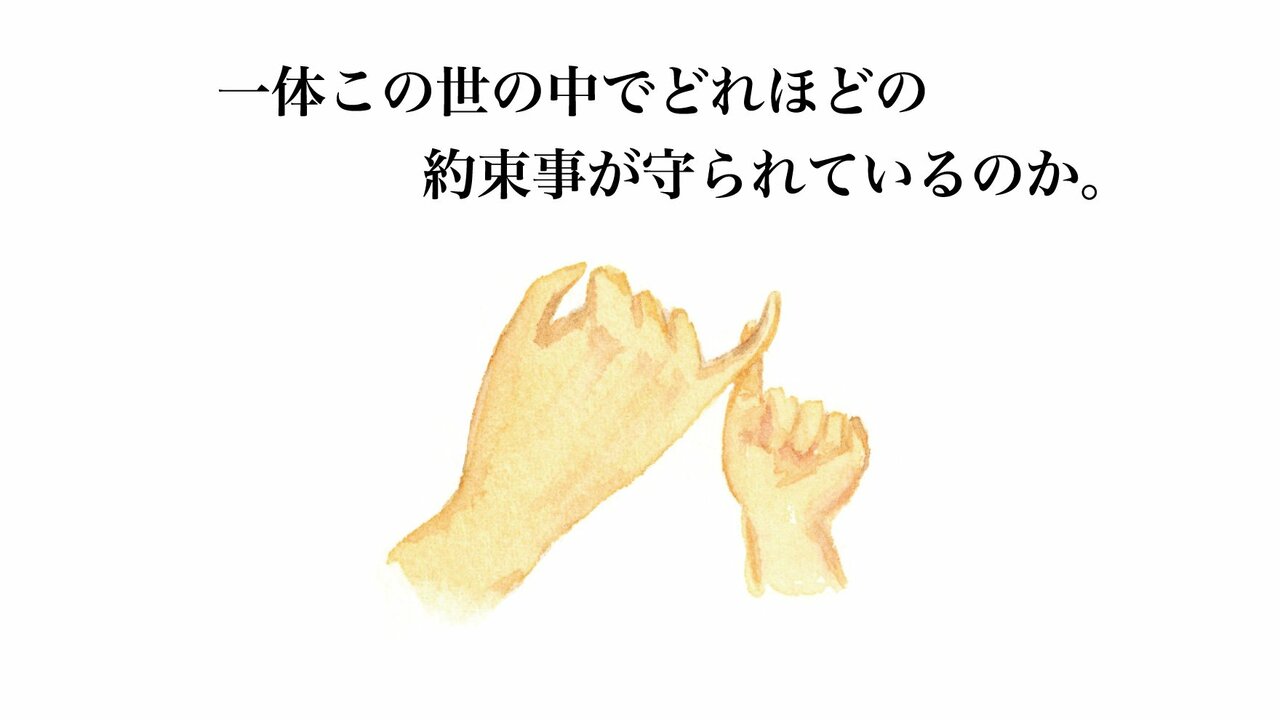塩田は広島出身で、穂波と同じ横浜の大学で西洋建築史を学んでいた。英会話のサークルで出会い、積極的なアプローチを受け友達になり、そのうちにお互いのアパートを行き来するようなつきあいになった。
アルバイトで貯めた資金でイタリアやスペインの建築物を見て回っていた塩田だが、穂波がバッファローにホームステイしていたとき、「ボザール様式のグランドセントラル駅を見にニューヨークへ来た」と突然やって来て、マンハッタンでデートしたこともあった。一緒に過ごす時間は楽しかったが、やがて会う回数が減っていき、穂波が田舎で就職を決めてからさらに疎遠になり、お互い連絡を取らなくなっていた。
ところが穂波が就職した三年後に新藤が建築士として入社すると、同じ学部の先輩後輩だったという伝で、塩田がときどき新藤を訪ねて会社にやって来るようになった。もともと穂波が建築会社を受験したのも、塩田の影響が少なからずあった。
とはいえ塩田に再会した頃には、穂波は地元の異業種交流会を兼ねて企画されたキャンプで太一と知り合い、軽登山やドライブに一緒に行くような交際が続いていた。
最初は地味で寡黙な印象だったが、話してみると太一は読書家で社会問題に対する自分の意見を持っており、言葉のはしばしに独特のユーモアも感じられた。服装も言動も飾り気がなかったが、何より穂波を見る眼が輝いていて、好意を隠そうともしない純朴さが好ましかった。結婚の話も出始めていたので、国内外を旅行しながら建築雑誌に記事を書いていたフリーランスの塩田との復縁は、全く想像がつかなかった。
二十数年前のその日、かつての「樅」で穂波はコーヒーを頼み、塩田と新藤はウイスキーの水割りを飲んでいた。それまで[オルセー美術館の大改修]について熱く語っていた塩田は、一定量を越えてアルコールが回ってきたのか、突然穂波に迫った。
「君の結婚の話、白紙に戻してもらえないか」
「どうしてそうなるの? 私の結婚は、あなたとは関係ないでしょ」
「穂波はこんな山と川しかない田舎で事務員をやってるような女じゃないんだ。外へ出ていくべきだ。島国ニッポンから出て、俺と一緒に世界の建築を見て回ろう」
いつもの彼のビッグマウスだったのだが、地に足が着いていないように見えた塩田の言葉の何かが、穂波のスイッチを押した。
「世界って何? 確かにここは山と川しかない田舎だけど、人々が集まり住んで町を作り、連綿と営みが続いている。私はここで、市井の人々が住む住宅や人が集う建物を作りたい。新藤君みたいに設計はできないし、技術も資格もないけれど、雑用係として家を作る手伝いをする。私のそばには、口下手だけれど誠実な太一さんと子どもたちがいて、家族を作る」
そんな趣旨のことを言った。塩田は、
「昔のフォークソングにあったな。家を作るなら、あれ、家を建てたなら……」
とつぶやいた後しばらく一言も発せず、ふいに立ち上がると何やら鼻歌を歌いながら店を出て行った。それきり一度も会うことはなかった。そのときの塩田への返答が穂波の思いの全てではなかった。塩田の旅する世界にも、彼のおおらかな人間性にも魅力があった。強く手を引かれたら、ついていきたい気持ちも少しはあった。ただ、穂波自身に何ができるのかを考えたとき、身につけた仕事をレベルアップさせていくことに現実味があって、この地で生きるパートナーとしては太一がしっくりきた。