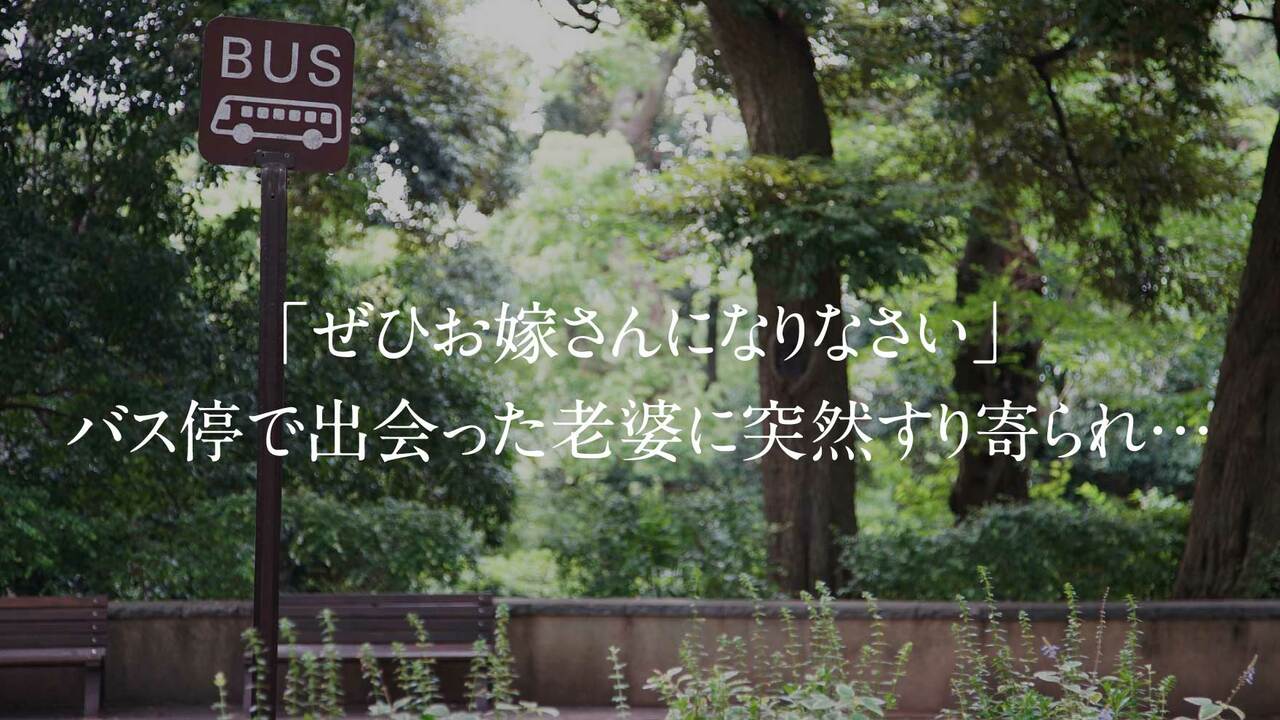一つの死
ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず
あの日のことを思い出すと、『方丈記』の一文が浮かんでくる。そして、赤いダリアは私にとって悲しみにあふれる受苦の花で、庭に植えたいとは思わない。
私は五歳だった。同じ年のえりちゃんとは一番仲良しだった。お手玉をしたり、祖母の家の裏にある銀杏の木の下でのままごと遊びも忘れられない。秋の金色の葉が降るような木の下で、私たちは空想の世界で夢中になった。
ある日、私たちは疫痢に罹ってしまったのだ。下痢が止まらず、私の変調に不安になった母が、隣村の診療所に担ぎ込んだ。白いベッドに寝かされ命拾いをしたことがあった。五歳の子どもにとってどうして病院に寝かされているのか、理由がわからなかった。
毎日が退屈で、太いリンゲルの注射針を太ももに打たれ、じっと動かずに寝ていることが苦痛で仕方がなかった。病室の窓辺から、真っ赤なダリアが咲き誇っているのが見えた。たぶん、季節は夏だったのだろう。そして退院した日、母は私にえりちゃんが死んだこと、もうこの世にいないことを諭すように告げた。
母は泣いていた。死の意味を深く理解することはできなかったが、何か途方もない恐ろしい出来事に、私も泣き出した。祖父の妹の家の階段の所で、母が私にそう告げた。私たちは祖父の妹を「おば」と呼んでいて、後に彼女と一緒に暮らすようになった。おばの家は川の畔に建っていて、田代山から新潟の信濃川へと続く渓流が白い水飛沫を上げていた。
私は泣きじゃくりながら、川の近くに行って、しゃがみ込んで泣き続けた。あの時の記憶は、どうしてこんなにも鮮明なのだろう。得体の知れない悲しみに押し潰されそうになりながら、えりちゃんはどこへ消えてしまったのだろう……と考えながら泣き続けた。
後に下痢が止まらないのを、えりちゃんのお母さんは「五歳にもなって!」と叱りつけて叩いたことを知り、またショックを受けた。母は医学書を読んでいた。えりちゃんの家に医学書があれば、一緒に入院してまた遊ぶことができたのに。それにしても、母親に叩かれて死んでしまうなんて、猛烈な怒りが込み上げてきた。
あんなに仲良しで、大切な友だちだったのに。この不条理な出来事のせいなのか、その他に理由があったのか定かではないが、私はそれから兄弟で一人だけ癇癪を起こすようになった。訳もなく怒りが込み上げてきて、その興奮が収まらなくなるのだ。それとも、御先祖様の誰かの血を受け継いだのだろうか。