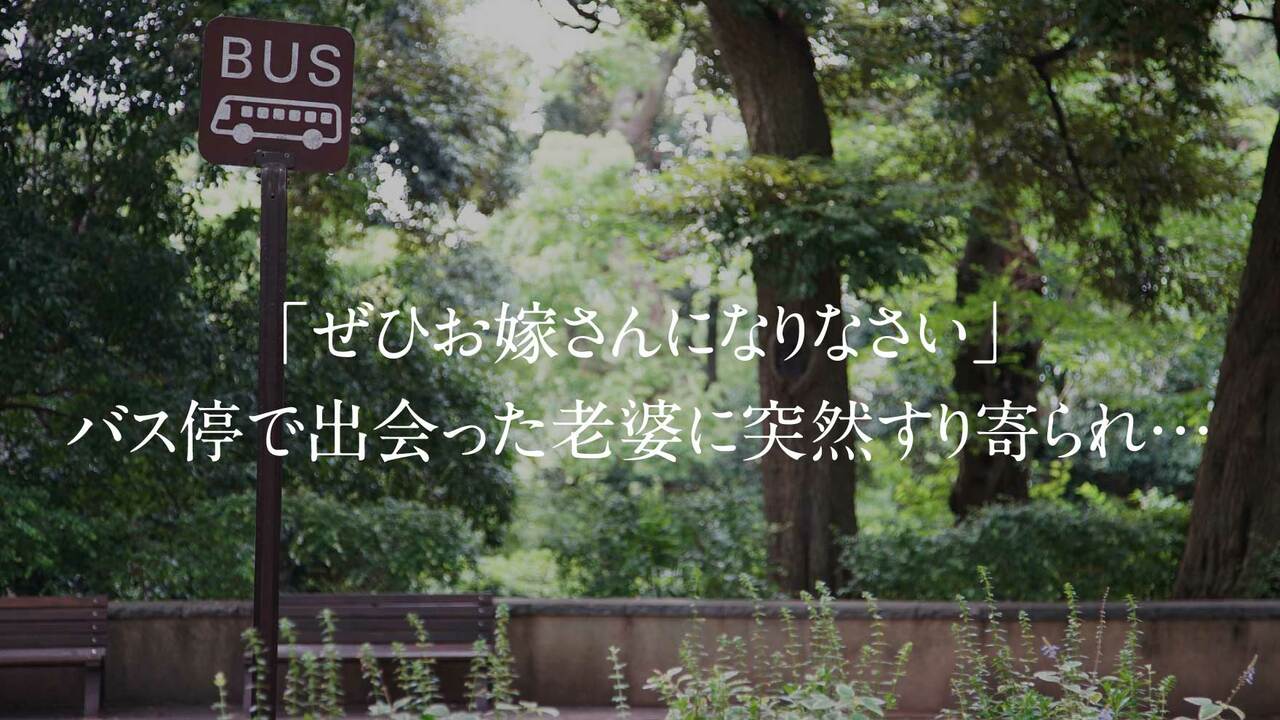マツばっぱ
私は、栃木県と福島県の県境にある山奥の村で生まれ、中学を卒業するまでその村で過ごした。今のように自家用車などはどこにもなく、時折大型トラックが丸太を積んで、砂ぼこりをあげて通り過ぎるのと、一番近い町を往復する乗り合いバスが、一日三回通り過ぎるだけの、のどかでそして寂しい村だった。
村全体が森のような風景に囲まれていて、静かな共同体の暮らしがあった。堀辰雄の『風立ちぬ』や立原道造の詩の信州の自然の描写の中に、同じような雰囲気を感じると何だか嬉しくなる。
しかし、冬は過酷だった。来る日も来る日も雪が降り続き、村は深い雪に覆われた。小川に氷が張り、息をつくこともできないほどの寒風が吹き荒れた日もあった。
私の家は川の畔にあり、雪解けの季節がやって来ると、一番最初に、川沿いにネコヤナギが顔を覗かせた。ネコヤナギを見ると、春が来たんだなぁと嬉しかったことをよく覚えている。
村には幼稚園がなかったので、その頃の子どもたちは幼稚園も知らなかった。日用品やわずかな食料を売っているお店が二軒あるだけで、この世にたくさんの物が存在していることすら知らないで育った。私の家から、小さな木造校舎の小学校までは三キロあり、吹雪の日ももちろん歩いて通った。
村は孤立した単独社会のように思え、点在する農家の家々とそこで暮らす人々の生活。様々に変わる季節の風物だけが私の知る世界のすべてだった。時折、安心と不安が入り交じったざわめいた感情にとらわれることがあり、私はあまり現実志向の子どもではなかったように思う。
当時、父は材木関係の事業を営んでいたが、決して順調とはいえなかった。父の実家からの援助があることもわかっていたので、引け目という感情が芽生えたのもその頃である。あの頃私たちは土蔵の家に住んでいて、父の実家はすぐ近くにあった。
祖父は四代目興惣左衛門を名乗り、私たちは「おじい様」と呼ばされ、敬うように躾けられた。祖父は、いつも囲炉裏の前に座っていて、家長制度特有の威厳を放っていた。私が新聞を届ける役目で、「おじい様、おはようございます」と言って、馬鹿丁寧な挨拶をして新聞を手渡すのだが、祖父はいつも不機嫌な顔で黙ったまま新聞を受け取った。
でも、あの頃を振り返ると、どこの家も貧しかったし、豊かな文化生活を知らないことは、さして不幸ではなかったとこの頃つくづく思う。田んぼには馬がいたし、私は村の人たちが働く姿、頑張る生活を美しいと思って育った。畔道を歩くのも好きだった。