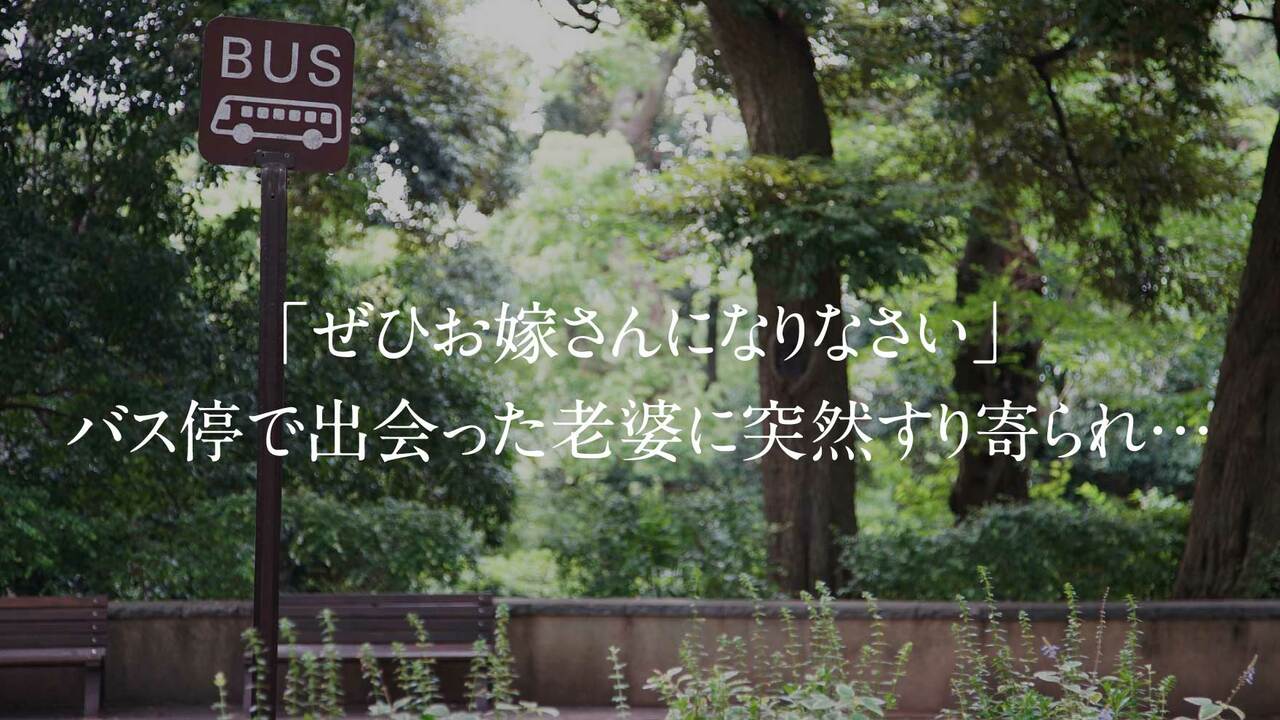春になると家の近くの湧き水に生えるクレソンのほろ苦い味も、秋のまろやかに熟したグミの実もアケビの味も格別だった。母は家計を助けるために駄菓子屋をしたり、四人の子どもを育てるのに必死だった。三歳年上の姉が小児結核を患ったことがあったらしく、そのせいもあったのだろう。父の事業を手伝ってくれていた人の奥さんが私の子守の役目をしてくれた。
血のつながりはなかったが、私たちはその人を「マツばっぱ」と呼んで、彼女は亡くなるまで私を慈しんでくれた。あれは何歳頃の記憶なのだろう。夕暮れが来るまで、私はマツばっぱの背中におんぶされていた。忙しい母を気遣って、きっとそんな時間まで私を預かってくれていたのだと思う。
秋が終わり冬が始まる季節が来ると、奥会津の山峡の集落には冷たい風が吹き始めた。ばっぱは寒くないように自分の肌と着物の間に私を入れて背負い、その上にねんねこを羽織ってくれた。「なかぽった」と呼ばれていた雪深い寒村の子守の姿である。ばっぱの背中はいつも温かくて居心地が良かったが、そこから眺める大人と同じ目線の夕暮れは何だかいつも寂しかった。
山々が薄紫に染まり、稜線が黒く沈んでいく頃にはいつも胸が締めつけられた。たまらなくなると、私は急いでばっぱの背中に顔を埋めた。その背中は、いつも柔らかくて、今もどこかにその温もりが残っている。そして、安心するとまた顔を上げ、一番星や深みを帯びて変幻するブルーのグラデーションの世界を眺め続けた。
闇が深くなるにつれ、その星はもっと輝き出した。一番星と人肌の温もりと、薄紫の山々の後に仄かに、そして確実にやって来る漆黒の闇。あの頃村には外灯がなかったので、闇は今よりももっと深い闇で、泣きたくなるような寂しさを幼い心にもたらした。でもばっぱの背中がいつも守ってくれた。これが、私の記憶の始まりである。